
「こども」という言葉は、「子供」「子ども」「こども」のように複数の表記があります。ただ、そもそもなぜ漢字と書く場合とひらがなで書く場合があるのか気になる人も多いかと思います。
特に公用文などの公的な文書に関しては、正しい書き方を把握しておきたいところです。そこで今回は、「こども」の違いや使い分けについて詳しく解説しました。
[toc]
子供・子ども・こどもの意味
まず、「こども」の意味を辞書で引くと次のように書かれています。
【子供(こども)】
①自分の得た息子や娘。古くは複数をいった。
②小児。児童。
③幼稚なこと。
④江戸時代、舞台に立つほか、色を売った年少の歌舞伎俳優。歌舞伎子。陰間(かげま)。子供衆。
⑤遊郭の禿(かぶろ)。
⑥自分より若い人たちに親しんで呼びかける語。
出典:三省堂 大辞林
上記のように、辞書では「子供」と書かれています。その他の辞書でも「子供(こども)」などと表記されるのが一般的です。
「こども」のみが書かれている辞書、あるいは「子ども」のみが書かれている辞書などは存在しません。
すなわち、国語辞典の表記に従うならば、「子供」を優先して使うということになります。
ただ、実際の使われ方としては「子供」「子ども」「こども」と3つのパターンがそれぞれ用いられています。
そのため、なぜ現在複数の表記がされているのかという理由や経緯を詳しく説明していきたいと思います。
子供・子ども・こどもの違い
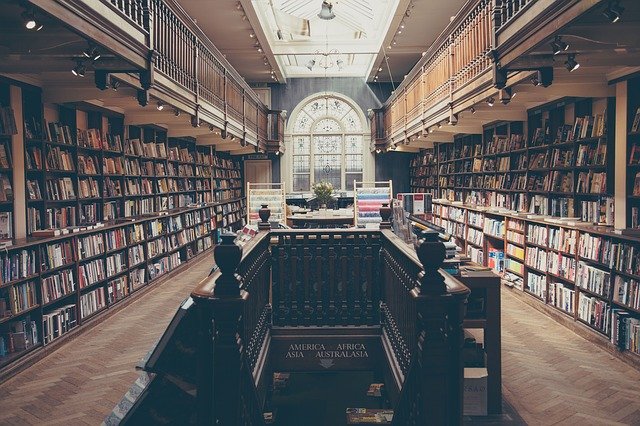
まず、元々この言葉は「子供」と書いていました。ところが、次第に「子供」のことを「子ども」と書くべきだと主張する人が増えてきました。
その理由は、主に以下のようなものです。
- 「子供」の「供」という字は「お供」、すなわち子供が大人の附随物や所有物であると連想させるため。
- 「子供」の「供」という字は、神に奉げる「供え物」「供養」などの意味があり、不謹慎なため。
- 「子供」の「供」は単なる当て字なので、漢字ではなく平仮名にすべきと考えられたため。
主に差別的な理由によりこれらの主張が行われていることが分かるかと思います。
要するに「子どもは親の所有物や従者ではない」「子どもをお供えするとはどういうことだ?」などという主張です。
一方で、こうした主張に対して反対の意見も当然あります。
- 「供」は教育漢字なので、表外字との交ぜ書きならともかく、わざわざ漢字とひらがなを混ぜる必要はない。
- 「こども」という言葉は万葉集まで遡るが、「ども」の原義は「男共」「女共」などと同じで複数を表す「ども」に由来するのでお供の意味はない。
- 「子供」よりもむしろ「子ども」や「こども」の方が差別的である。なぜなら「豚ども」「白人ども」「黒人ども」などのように見下した表現である「ども」と重なるからだ。
- それならば「児童」も「児どう」と表記しなければならない。理由は「児」には「愚か」「しもべ」などの意味が含まれているからだ。
このような経緯もあり、現在では複数の表記がされているというわけです。
「一種の言葉狩りなのでは?」という意見もありますが、漢字にはその文字に込められた由来というのが必ずあります。
一方で、「意味が伝達できれば言語はそれでいい」と考える人たちもいます。
したがって、これらの言葉の書き方論争に明確な答えがあるわけではないと考えて下さい。
子供・子ども・こどもの使い分け
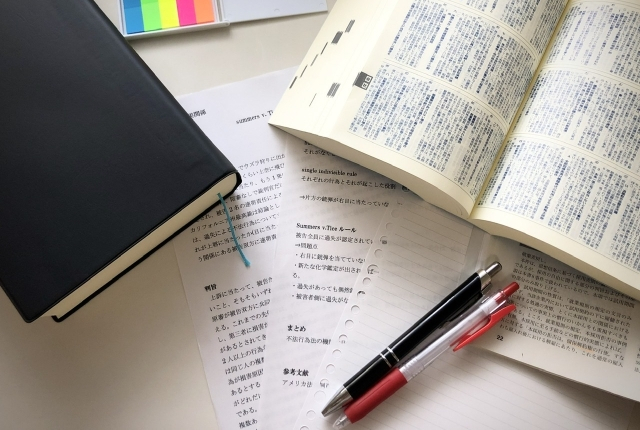
以上の事から考えますと、いずれも意味自体に違いはないので「どれを使っても決して間違いではない」という結論になります。ただ、一般的には大まかな使い分けがされているようです。
まず、新聞やテレビなどの「マスコミ業界」では「子供」を使うことで統一しています。
文字を扱う新聞やテレビなどの報道機関は漢字の混同を嫌う傾向にあります。そのため、「子ども」と「こども」はあえて使わないようにしているのです。
また、「公文書」や「公用文」などでも「子供」と表記することが原則とされています。これは教育機関のトップである文部科学省が決めていることです。
文部科学省は2013年に、「供」には「お供」のような否定的な意味はないという見解を示しました。その証拠に、常用漢字表には「子ども」や「こども」ではなく、「子供」という表記がされています。
「漢字と平仮名の交ぜ書きは国語を破壊する」との指摘もあったので、文部科学省はこのような判断を下したのです。
一方で、「法令文」などでは「子供」「子ども」「こども」のいずれも使用例があります。中でも「子ども」という表記が最も多いです。
「子供」の使用例⇒「選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。」(公職選挙法第85条より。この法律のみ)
「子ども」の使用例⇒「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育」。(その他187個の法律で使用)
「こども」の使用例⇒「こどもの日」「認定こども園」(その他48個の法律で使用)
「子ども」という表記が多い理由は、こどもの人権に配慮されているからだと思われます。先ほども説明したように、「供」は「供養」「お供え物」などと同じ漢字です。
したがって、人権問題などを扱う側面もある法律の世界では、無難な方の漢字を選択しているということでしょう。
また、国民の祝日に関する法律では、毎年5月5日を「こどもの日」と定めています。これは小さな子供でも読みやすいようにという配慮で、全てひらがなにしたと言われています。
いずれにしろ、どれを使っても間違いではありませんが、状況や場面も加味して上手く使い分けるのがよいでしょう。
例えば、前後の文脈によってはひらがなだけだと読みにくくなってしまう場合もあります。
【例】⇒「こどもも大人も参加する大会」
このような場合は字面が繋がってしまうので「子供も大人も~」と書いた方が読者としては読みやすいです。逆に、漢字ばかりが続いて字面的に読みにくくなってしまう場合もあります。
【例】⇒「子供達全員参加の大会」
このような場合は、「子供たち全員参加の大会」と書いた方が読みやすいです。
ただ、最終的にどれを使えば分からないとなった場合は、「子供」を使っておけば問題ありません。なぜなら、文部科学省が「子供」を使うことを原則として決めているからです。
したがって、もしも使い方の判断に迷った場合は「子供」を使うようにしてください。
本記事のまとめ
以上、本記事のまとめとなります。
「子供」=文部科学省が推奨している表記。公用文や報道関係は原則これを使えば問題ない。
「子ども」=法律文でよく使われる表記。差別的な要素を排除するために生まれた書き方。
「こども」=「子ども」をさらに柔らかくした表現。「こどもの日」など限定的な使い方のみ。
私的な文章を書く時はどれも使うことができます。ただ、公用文など公的な要素が絡む場合は「子供」を使うようにしましょう。






