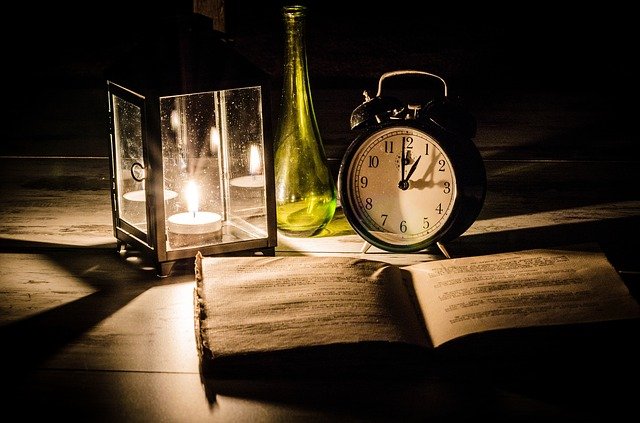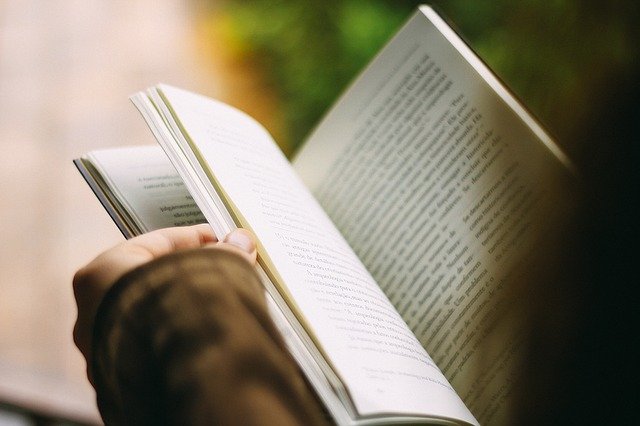
『言語と記号』は、丸山圭三郎による有名な評論文です。高校現代文の教科書にも載せられています。
ただ、本文を読むとその内容や筆者の主張が分かりにくいと感じる部分も多いです。そこで今回は、『言語と記号』のあらすじや要約、テスト対策などをなるべく簡単に解説しました。
[toc]
『言語と記号』のあらすじ
本文は、内容により3つの段落に分けることができます。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①私たちの日常生活は記号だらけである。数学の演算記号、交通信号、モールス信号、地図の標識といった典型的なものに限らず、人の表情やジェスチャー、衣服やアクセサリーなども記号と見なすことができる。記号とは「自分とは別の現象を告知したり指示したりするもの」であり、特定文化内の儀礼、音楽、絵画、建築なども広義の記号性を免れていない。また、「言語も記号の一つ」と考えられる。
②言語記号も他の一般記号と同じく、言語以前の事物や概念の存在を前提とするとされてきた。しかし、同じ記号と呼ばれてはいても、言語記号とその他一切の記号類との間には、本質的な違いがありはしまいか。例えば、メルロ・ポンティの考えや古代神話の世界では、名は事物の本質であって事物そのものが名付けられることによって認識され、別々のものとして分けられ、存在を開始するとされる。したがって、言語記号の「名付ける」という行為は、一次的にはそれまで分節されなかった観念や事物に区切りを入れて、これを存在させていく根源的作用であり、二次的にはそのようにしてつくられた存在にラベルを貼る作用だと言える。
③言語記号の根源的作用には、言語が可能にした思考によって道具がつくられ、その道具類やそれを用いた生産活動が、新たな世界をつくり出すというはたらきも含まれている。道具の使用は宇宙の秩序が人間の介入を許し、また、道具を変えることで、外界を変化させ、自分たちの世界像や世界観も変えていく。人間が道具によって作り出した、風や水、空間などの身近な違いが、そのまま世界観の違いや人間関係の把握の違いに通づるのも、世界と意識の相互差異化がもたらす結果と言えるだろう。
『言語と記号』の要約&本文解説
本文で注目すべきは、「言語によって名付けられることで、事物が存在する」というものです。
私たちは通常、「ある事物がまず存在し、それに対して人間が名前を付ける」と考えがちです。しかし、筆者はそうではないのだと主張します。
筆者は、「事物」というのは、言葉によって名付けられることで初めて存在するのだと述べています。この事を本文中では、「名というのはむしろ事物の本質であって、事物そのものが名とともに初めて分節され、存在を開始する」と書かれています。
例えば、日本語では「犬」と「狸(たぬき)」は別の動物であるかのような意識がありますが、フランス語だと両者はどちらも「chien」と呼びます。
「犬」と「狸」という別の名前を付けられることにより、初めてその二つの動物は別の動物として存在を始めることができます。
つまり、名づけというのはこの世界に対する一つの解釈でありお互いを差異化するものであり、その事により人間の主体の意識の方も差異化されるということです。
初めからこの世界は分けられているのではなく、名付け(言語)によってこの世界は分けられている、という筆者の主張を読み取るのがポイントとなります。
『言語と記号』のテスト問題対策
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①テンケイ的な症状。
②チョウコクを趣味とする。
③真理をツイキュウする。
④絵具でノウタンをつける。
⑤カッショクを帯びる。
⑥コトダマを信じる。
⑦政府がカイニュウする。
⑧ジャグチをひねる。
次の部分は、それぞれどのような記号を表しているか?本文中の語句を用いて答えなさい。
①「同一の意味を送り返す」
②「微妙な差異が生じてくる」
次の内、本文の内容を表したものとして適切でないものを選びなさい。
(ア)古くからある<記号=代表品>という考え方は、本物の存在を前提としており、言語以前の事物や普遍的カテゴリーの存在自体は、一度として疑われることはなかった。
(イ)メルロ・ポンティの考えや古代神話の世界では、名は事物の本質を表し、事物そのものが名とともに初めて分節され、存在を開始するとされる。
(ウ)私たちは言葉以前に何かを明確に認識して、それからその認識した対象に名前をつけるため、「名付ける」という行為からは、「存在が名称に先立つ」ということが言える。
(エ)名付けとは、言葉による言語外現実の一つの解釈であり、差異化であり、世界が差異化されると同時に、主体の意識の方も同様に差異化されるという相互作用がある。
まとめ
以上、今回は『言語と記号』について解説しました。ぜひこの記事を見直して復習して頂ければと思います。なお、本文中の重要語句については以下の記事でまとめています。