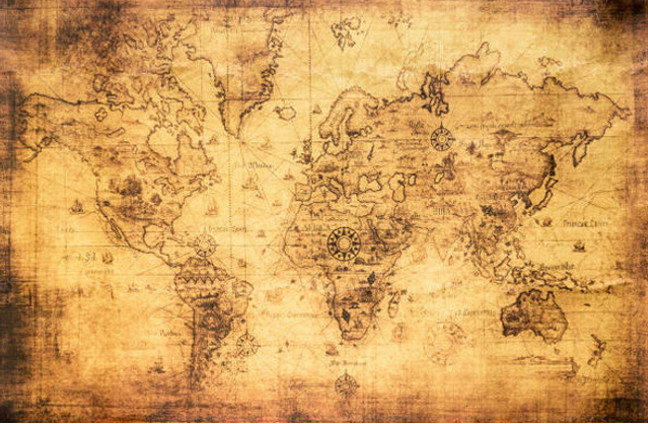
『地図の想像力』は、論理国語の教科書で学習する評論文です。そのため、定期テストの問題にもよく出題されています。
ただ、実際に文章を読むとその内容が分かりにくいと感じる人も多いと思われます。そこで今回は、『地図の想像力』のあらすじや語句の意味、テスト対策などをわかりやすく解説しました。
『地図の想像力』のあらすじ
本文は、行空きによって3つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを紹介していきます。
①地図が世界に対するイメージの表現であり、概念的な描像であることは、「T-O図」と呼ばれる中世ヨーロッパの世界図を見れば納得できるだろう。「T-O図」のような「地図」は、世界に対する科学的な知識の不足と測量術の未熟さからくる、未発達な地図の姿だと思われるかもしれない。しかし、今日の地図における科学性とは、地図が世界を概念化しイメージ化する一つの方法にすぎない。そして、地図の歴史の中にはそのような「科学」とは異なる多様な世界の概念化とイメージ化の方法が見いだされる。
②概念やイメージとしての地図が表現する世界とは、「世界そのもの」などではない。「人間にとっての世界」、人間によって見られ、読み取られ、解釈された「意味としての世界」である。それは、ある社会で人々が世界や社会を見る見方を表現した集合的な表象なのだ。ここで言う「意味」とは、例えば「客観」に対置されるような「主観」のことではない。世界を記号によって記述し、理解する人間の営みにおいて記述され、表現されるもの全てを指す。山の標高も地点間の距離も、人間が「数」というシンボルによって作り上げた規準に従って測定し、表現することなしには存在しないのだ。
③ある社会に属する人々にとっての「世界」の姿は、その社会の言語が世界をどのように分節化しているかということに強く規定されている。人間は言語という媒体(メディア)を通じ、意味を通じて出会う。地図もまた、人間が世界と出会う際に用いる一つのメディアである。地図は描き取った対象としての世界の文字通りの「再現」ではない。それは地図製作者によって再び読み取られ、再解釈された世界なのだ。つまり、「地図とは世界に関するテクストである。」と言うべきであろう。
『地図の想像力』の要約&本文解説
筆者の主張を一言で言うなら、「地図というのは人間にとっての世界である」ということになります。この事を筆者は「地図」=「概念的な描像」「意味としての世界」などと言い換えています。
私たちが一般に目にする「地図」というのは、書店に売っている紙の地図やネット上で見れるグーグルマップのような地図です。日々、当たり前のようにこれらの地図を見ていて、なおかつそれが正確なものだと思っています。
そのため、「T-O図」のような中世ヨーロッパの世界図を、未熟で不正確な地図だと思ってしまいがちです。筆者はこの事を近代的リアリズムの思考によるものであり、誤りなのだと指摘しています。
第一段落では「T-O図」を例として挙げ、それが未発達なものではないことを述べて、地図の本質についての議論へと導いています。
第二段落では、「地図」が表現する世界とは「人間にとっての意味としての世界」であり、「世界のリアルな再現」ではない、ということが述べられています。
最後の第三段落では、そこから発展させて「地図」もまた「一つのメディア」であるとして、解釈され続ける「テクスト」であるとされています。
全体を通して筆者が主張したいことは、第二段落の「地図」=「人間にとっての意味としての世界である」という箇所に集約されていると言えます。
『地図の想像力』の語句・漢字一覧
【概念的(がいねんてき)】⇒物事の把握の仕方が大まかであるさま。
【描像(びょうぞう)】⇒描いた像。概念をわかりやすくイメージ化したもの。
【リアリズム】⇒現実をあるがままに再現しようとする芸術上の立場。写実主義。
【忠実(ちゅうじつ)】⇒実際の通りに正確に行うこと。
【科学的(かがくてき)】⇒考え方や行動の仕方が、実証的で筋道が立っているさま。
【未熟(みじゅく)】⇒学問や技術などの経験・修練がまだ十分でないこと。
【理性(りせい)】⇒道理によって物事を判断する心の働き。論理的、概念的に思考する能力。
【暗黙の(あんもくの)】⇒黙って口に出さない。
【抜きがたい】⇒取り除くことが困難である。
【ひと括りにする(ひとくくりにする)】⇒多くのものを一つにまとめる。
【豊饒さ(ほうじょうさ)】⇒豊かでたくさんあること。
【表象(ひょうしょう)】⇒ものやことをかたちに表すこと。ものやことをかたちとして捉えること。また、そうして表されたり捉えられたりしたかたち。
【客観(きゃっかん)】⇒自分の見方や考え方を離れ、第三者がそうだと納得できること。
【主観(しゅかん)】⇒自分だけの感じ方や考え方。
【シンボル】⇒ある意味をもつ記号。
【存在様態(そんざいようたい)】⇒存在する様子、ありさま。
【デフォルメ】⇒対象を変形させて表現すること。
【位相的(いそうてき)】⇒ここでは、「ある路線間における位置のありさま」という意味。「位相」は「物事の中でのある位置」を示す。
【分節(ぶんせつ)】⇒ひとつながりものに区切りをつけること。また、その区切られたもの。分節されることにより、差異が生まれる。
【媒体(ばいたい)】⇒中間、つなぐものという意味の語。メディア。
【中性的(ちゅうせいてき)】⇒何の特徴もないさま。
『地図の想像力』のテスト問題対策
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①ナットクが行かない。
②ミジュクな考え方を持つ。
③ゲンミツな審査をする。
④シュクシャクの大きい地図。
⑤暗号をカイドクする。
⑥ゴカイを招く表現。
⑦トウメイな色を持つ。
次の内、本文の内容を表したものとして適切でないものを選びなさい。
(ア)「T-O」図と呼ばれる中世ヨーロッパの世界図が、未熟で未発達だと思われるのは、科学主義的な地図観によるものである。
(イ)地図に標高や距離が正確な縮尺により表現されているのは、それらが地図の製作者や利用者などに「有意味」な情報だと認められているからである。
(ウ)人間は言語という媒体を通じ、意味を通じて世界と出会い、書記記号により描かれた地図もまた、人間が世界と出会う際に用いる一つのメディアである。
(エ)地図とは世界に関するテクストであり、テクストは世界をありのままに映し出すものであるため、地図の中ではさまざまな意味=「世界」が生産されることになる。
まとめ
今回は『地図の想像力』について解説しました。この評論文は、地図とは何かという問題が明快に述べられています。もう一度本文を読み、私たちはどのようにこの世界と接しているか考えてみるのもよいでしょう。