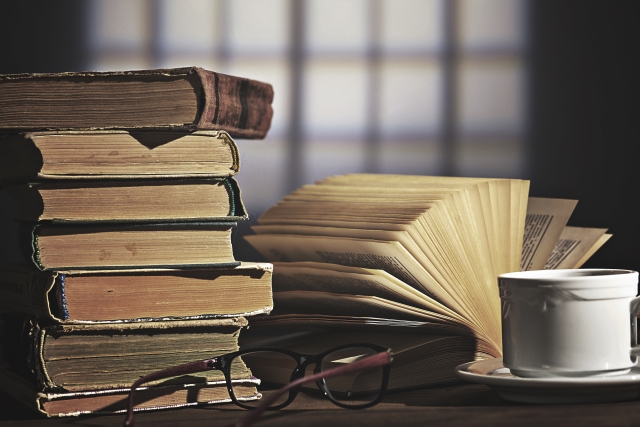
「堂に入る」という慣用句を目にする機会は多いです。ただ、気になるのは読み方、そして語源だと思います。
つまり、「入る」は「はいる」と読んでいいいのか?そして、どこに入ることを指しているのか?という疑問です。
そこで今回は、「堂に入る」の意味や読み方、由来、類語などを含め詳しく解説しました。
堂に入るの意味・読み方
最初に、読み方と基本的な意味を紹介します。
【堂に入る(どうにいる)】
⇒学問や技術が奥深いところまで進んでいる。転じて、物事に習熟している。身についている。
出典: 三省堂 大辞林
「堂に入る」は「どうにいる」と読みます。「どうにはいる」とは読みません。これは読み間違える人が多いので注意してください。「入る」は「はいる」ではなく「いる」と読みます。
そして意味ですが、「堂に入る」とは「学問や技術が奥深いところまで進んでいること・物事に習熟していること」などを表します。
例えば、英語を全く話せなかった女性が、長年かけてようやく英会話ができるようになったとします。そして、ついには自分で英会話スクールを開き、生徒に教えられるような立場にまで成長しました。
このような場合、彼女は英語という学問を深く理解し、なおかつ体に染みついている状態と言えます。よって、「堂に入るようになった」などと表現するわけです。
また、今までプログラミングをやったことがない男性がいたとしましょう。しかし、ちゃんと専門の教室に毎日通い、ついには自分でプログラムを打てるようになりました。
そして、プログラマーとして収入も得られるレベルにまで成長を遂げました。このような場合も、プログラミングという技術がしっかりと身に着いている状態なので、「堂に入るようになった」と言うことができます。
つまり、「堂に入る」とは学問や技術などが深い領域に達し、それらを習熟している様子を表す慣用句ということです。簡単に言えば、「しっかりと身に付いている」という意味だと考えて問題ありません。
堂に入るの語源・由来
「堂に入る」は、『論語』に出てくる一文が元となっています。『論語』とは中国の思想家である孔子とその弟子たちのやり取りをまとめた書物のことです。
以下、実際のセリフとなります。
「堂に升りて室に入らず(どうにのぼりてしつにいらず)」
「堂」とは中国の建物における「応接間」のことで、「室」とは「奥の間」のことを指します。応接間にのぼった程度では、建物の奥の様子はほとんど分かりません。すなわち、「何も知らない未熟な状態」だと言えます。
この事から、学問や技術に対してまだまだ道を究めていないことを「堂に升りて室に入らず」と言うようになったのです。現在使われている「堂に入る」は、この「堂に升りて室に入らず」を肯定形にした「堂に入りて室に入る」を省略した言い方だと言われています。
「堂に入りて室に入る」を略すと「堂に入る」となります。省略された部分の「室に入る」というのは、先ほども説明したようにその道の奥義を究めた様子のことです。
したがって、「堂に入る」=「学問や技術などを深く身につけている」という現在の意味につながるわけです。
堂に入るの類義語

続いて、「堂に入る」の類義語を紹介します。
類義語は「多くの経験を積んだことにより、物事を上手く扱えるようになる」という意味のものが多いです。さらにそこから派生して、「ふさわしい姿になる」という意味の言葉も類義語に含まれます。
この中でも特に「板につく」はよく使われる慣用句です。元々は役者が経験を積み、その演技が舞台(板)にぴったりと調和することからできた言葉です。
なお、「堂に入る」と混同しやすい慣用句で「悦に入る(えつにいる)」がありますが、全く意味が異なるので注意して下さい。
「悦に入る」とは「物事がうまく運び、満足して喜ぶ様子」を意味します。「悦」は「喜び」を表し、喜びを心の中に入れたままにしているので、「一人心の中で喜びに浸っている状態」を表します。
堂に入るの英語訳
「堂に入る」は、英語だと次のように用います。
①「be master of the art(その道の達人)」
②「be quite at home(板についている)」
①の「master」は「職人」、「art」は「芸術」の他に「技術」「腕前」「熟練」といった意味があります。そのため、「技術の職人」「熟練した職人」という意味で「堂に入る」と訳すことができます。
また、②の「quite」には「かなり」、「at home」には「精通している」という意味があります。こちらも合わせることで、「かなり精通している」⇒「堂に入る」「板につく」などと訳すことができます。
例文だと、以下のような使い方です。
The “phantom the opera” you act is a master of the art. (あなたが演じるオペラ座の怪人は堂に入ってる。)
He is quite at home with computers.(彼はコンピューターにかなり精通している。)
堂に入るの使い方・例文
最後に、「堂に入る」の使い方を例文で紹介しておきます。
- 彼の司会は堂に入ってるので、安心して任せることができる。
- 俳優の堂に入った演技に、周囲の者は皆一様に感心させられた。
- あの人は長年絵を描き続けただけあって、やはり堂に入った作品を描く。
- 質疑応答を聞くだけで、彼が研究者として堂に入っているのは明らかであった。
- 彼女の演説は父親譲りの堂に入ったもので、周囲の人から高く評価されている。
- 堂に入ったバッティングフォームを見ても、彼がただのアマチュア選手じゃないのは確かだ。
- 今回の社長の堂に入ったスピーチには感動した。やはり彼は一流の経営者と言える。
「堂に入る」は、何かしらの知識や技術に関して深く理解しており、それらがしっかりと身についている状態を表します。したがって、基本は相手を称賛するような場面で使われると考えて問題ありません。
学問や技術に限らず、知識や演技、立ち振る舞い、トーク力など、人が身につけられるものであれば何でも対象となります。相手に対して感心したと時はぜひとも「堂に入る」を使ってみましょう。
なお、用例としては「堂に入る」よりも、「堂に入った~」「~が堂に入ってる」などが多いです。
まとめ
以上、本記事のまとめです。
「堂に入る」=学問や技術が奥深いところまで進んでいること・物事に習熟していること。
「語源・由来」= 「論語」の「堂に升りて室に入らず」から。応接間にのぼった程度では、建物の奥の様子はほとんど分からないため。
「類義語」=「様になる・板につく・熟練する・こなれる」
「英語訳」=「be master of the art」「be quite at home」
「堂に入る」は、学問や技術などの物事に習熟していることを表す慣用句です。身の回りで「この人は堂に入っているな」と思う人がいたらぜひ使ってみてはどうでしょうか?