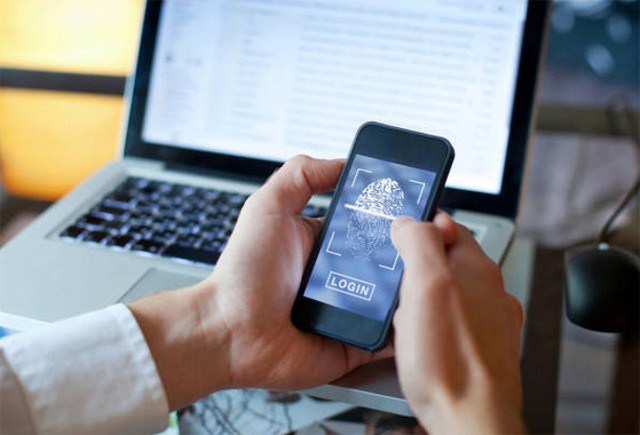
『身体の疎外』は、高校現代文の教科書に出てくる評論です。ただ、本文を読むとその内容が難しく感じるという人も多いと思われます。
そこで今回は、『身体の疎外』のあらすじや要約、語句の意味などを含めわかりやすく解説しました。
『身体の疎外』のあらすじ
本文は、大きく分けて4つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①哲学にとって「身体」は、重要なテーマであると同時に、やっかいな問題でもあった。デカルトは、「われ思う故にわれあり」と、身体よりも精神の優位性を示す「デカルト的身体疎外」を主張した。しかし、20世紀になると、コンピュータ・ネットワークにより、脳の部分、神経系の部分だけが急速に拡張し、身体に関わらない「電脳的身体疎外」という状況が生じてきた。
②二十世紀後半の、私と身体をめぐるあり方を最もはっきりと表現していたのは生命倫理の問題だろう。特に、臓器提供による「自己決定権」という考え方は明らかである。臓器提供では、ドナー・カードによって、私が臓器提供の意志を表明したときのみ、私の身体は臓器を提供可能となる。つまり、私の本体とは私の意識であり、身体はそれに従属するものと考えられてきたわけである。
③ところが二十一世紀には、私の意識とは無関係に私が私であることをアイデンティファイする技術であるバイオメトリックス認証が発達した。その結果、<私と身体>をめぐる問題に、デカルト的疎外、電脳的疎外とは逆の、「物質としての身体」が独り歩きを始めるようになった。つまり、私の意識とは無関係なところで私が私であるかどうかをアイデンティファイしようとする動きである。
④脳科学の進展はすさまじいものがあり、さまざまなテクノロジーを使い、リアルタイムで私の脳状態を見て私の意識を測ろうという方向へ進んでいる。これは、精神が身体を疎外することの逆転現象である。「私(精神)」が主語なのではなく、デジタルの眼を通した「身体」が主語になり、「私」を疎外していく構造なのである。
『身体の疎外』の要約&本文解説
哲学において、「身体」と「精神」の関係性というのは常に注目されてきました。まず、近世哲学ではデカルトの「われ思う故にわれあり」という考え方が出発点となっています。ここでの「思う」とは「意識」のことを表しています。つまり、私の意識が私の存在を表しているのだという意味です。
デカルトは、「世の中のすべてのものの存在を疑ったとしても、それを疑っている自分自身の存在だけは疑うことができない」と考えました。要するに、人間の本質は意識や精神であるため、身体はその従属物に過ぎないと彼は考えたわけです。これが本文中で述べられている「デカルト的身体疎外」の意味です。
そして、次の二十世紀にはコンピュータ・ネットワークによってデカルト的身体疎外とは別の意味で、神経系のみのつながりである「電脳的身体疎外」という現象が現れるようになりました。これは、インターネットにより私たちの神経系はますます拡張され、身体性がさらに私の存在として希薄になっていったということです。
このように、二十世紀までは人間の本質は身体ではなく「意識・精神」であり、人間の身体性が置き去りにされるという状況になっていました。
ところが、二十一世紀に入ると、バイオメトリックス認証と呼ばれる新たな技術が登場することになります。これは、意識とは無関係に私を体で認識する技術のことです。例えば、顔の形や目の虹彩といったものから、その人を自動的に判断するような技術です。
筆者はこの事を「意識が身体を疎外するのではなく、身体が私を疎外する逆転現象」だと述べています。つまり、私の意識が身体を疎外するのではなく、身体が私の意識や心を疎外するということです。
最終的に筆者は、「私」が主語なのではなく、デジタルの眼を通した「身体」が主語になり、身体がデジタルの眼と結託して主導権を握っていく時代に入りつつある、と述べています。
簡単に言えば、「私」が主語ではなく「身体」が主語となり、私(精神)を疎外していく時代に入りつつある、ということです。
『身体の疎外』の意味調べノート
【哲学(てつがく)】⇒世界や人生などの根本原理を追求する学問。
【近世(きんせい)】⇒16世紀頃~18世紀後半・19世紀初頭くらいまでの期間。
【所以(ゆえん)】⇒理由。いわれ。
【復権(ふっけん)】⇒一度失った権力を回復すること。
【声高(こわだか)】⇒声の高いこと。大きな声。
【疎外(そがい)】⇒ヘーゲル哲学で、「自己を否定して、自己にとってよそよそしい他者になること」という意味。ここでは、「精神・身体の対立項の一方を否定して、私の存在の本質を捉えようとすること」を表している。
【拡張(かくちょう)】⇒広がって大きくなること。
【齟齬(そご)】⇒物事がうまくかみあわないこと。食い違うこと。
【にっちもさっちも】⇒物事が行き詰まり、どうにもできないさま。どうにもこうにも。
【生命倫理(せいめいりんり)】⇒生と死に医療がどう関わるべきかの考え方。本文中の「臓器提供」以外では、「人工授精」「人工妊娠中絶」「安楽死」「終末期医療」などが生命倫理の問題として挙げられる。
【自己決定権(じこけっていけん)】⇒個人が公権力から干渉されることなく、自分で意思決定することができる権利。
【脳死(のうし)】⇒大脳および脳幹のすべての機能が完全に失われた状態。
【ドナー・カード】⇒臓器提供意思表示カード。
【主体的(しゅたいてき)】⇒自分の意思や判断に基づいて行動するさま。
【次元(じげん)】⇒物事を考える時の立場や基準。
【端的(たんてき)】⇒簡潔に要点だけをとらえているさま。
【押捺(おうなつ)】⇒印鑑や指紋などを押すこと。
【虹彩(こうさい)】⇒眼球の角膜と水晶体との間にある円盤状の薄膜。眼球内に入る光の量を調節する。
【遂行(すいこう)】⇒物事をやりとげること。なしとげること。
【徹底的(てっていてき)】⇒どこまでも一貫して行うさま。
【生体(せいたい)】⇒生物の生きているからだ。
【総体(そうたい)】⇒物事の全て。全体。
【進展(しんてん)】⇒物事が進歩・発展すること。
【結託(けったく)】⇒示し合わせて事に当たること。
『身体の疎外』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①身体のソガイ。
②意思をヒョウメイする。
③任務をスイコウする。
④指紋によるニンショウ機能。
⑤アンイな考えを持つ。
⑥テッテイ的に管理する。
次の内、本文の内容を表したものとして適切でないものを選びなさい。
(ア)デカルトの考え方では、意識、精神こそが人間の本質であり、身体はその容れ物にすぎないことになる。
(イ)コンピュータ・ネットワークとは、人間の身体性の側面を置き去りにして、神経系のみを拡張するものである。
(ウ)バイオメトリックス認証は、私の意識とは無関係に、私が私であるかどうかをアイデンティファイしようとするものである。
(エ)「身体」が主語なのではなく「私(精神)」が主語となり、「私」がデジタルの眼と結託して主導権を握っていく時代に入りつつある。
まとめ
以上、今回は『身体の疎外』について解説しました。身体と精神の関係性について論じた文章は、入試でも出題されやすいです。ぜひ正しい読解ができるようにしておきましょう。