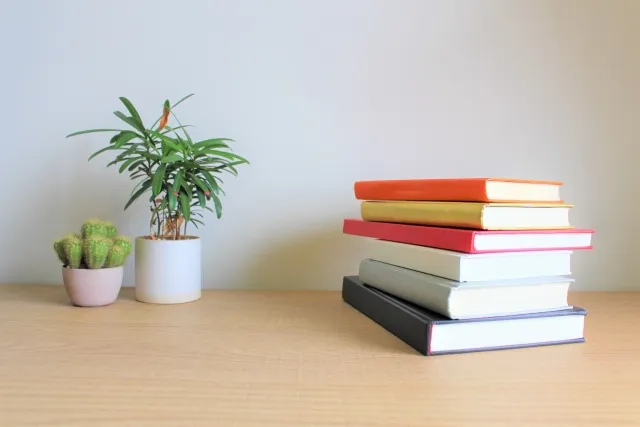『何のための自由か』は、仲正昌樹による評論文です。高校の教科書「論理国語」にも掲載されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『何のための自由か』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『何のための自由か』のあらすじ
この文章は、大きく三つの段落から構成されています。以下に、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①ベンサムは、各人が感じる幸福の総和を最大化することを図る「功利主義」を、「統治」の原理として提唱した。彼の「功利主義」は、「幸福」は「快楽」という形で客観的に計量化することが可能である、という前提から出発する。計量化された「快楽」の計算に基づいて合理的な統治を行うことが可能であり、そうした統治を追求すべきという立場である。この考え方は、国家が人々にとっての「幸福の状態」を定義することを意味するため、諸個人の「自由意志」と衝突することになる。そのため、功利主義的な考え方は、福祉や公共事業など特定の公共政策の策定に際して応用されることは多いが、一つの国家の包括的な統治原理として採用されることはなかった。
②しかし、ここ数年日本ではアーキテクチャー論という形で、功利主義的な統治の実現可能性が論じられている。「アーキテクチャー」とは、人々が社会的に望ましくない行動を取るのを技術的に不可能にする環境の「設計」を意味する。すでに現実化されている例だと、ネットやテレビなどの情報が不正にコピーされるのを防止するために、最初からコピーすることが技術的に不可能なように「設計」するということがある。個人の「自由意志」という意識とは関係なく、物理的環境だけを制御するアーキテクチャーでは、言語を介する人間的な面倒くささが省かれる。その分だけ、統制する側/統制される側双方にとって、エネルギーを節約し、不快感を減らせる可能性がある。
③私たちの内なる欲望に無意識レベルで働きかけ、最初から"悪いこと"を望まず、"最大多数の幸福に適ったこと"="善いこと"だけを欲望するように誘導できる超アーキテクチャーが開発されたとしたら、議論の様相は全く異なってくる。生まれた時から超アーキテクチャーに囲まれて生活し、プログラム化された”快適さ”を”自然”だと感じる人ばかりになれば、管理している/管理されている、支配/被支配、自由/従属といった、現在の"私たち"の「自由」感覚を支えている境界線が相対化されていくはずだ。そうなると、"みんなの幸福"を合理的に設計しようとする超功利主義的な方向に流れていかないとも限らない。「何のための自由か?」という問いが、近い将来、極めてアクチュアルな意味を持つことになるかもしれない。
『何のための自由か』の要約&本文解説
本文は、功利主義と現代技術による環境設計(アーキテクチャー)を手がかりに、私たちが「自由」と呼んでいるものの本質を問い直す評論文です。
筆者は、「自由」が当たり前に存在するものではなく、むしろ技術による管理によって静かに姿を変えている可能性に注目し、「そもそも自由は何のために必要なのか?」という問いを私たちに投げかけています。
功利主義と自由の対立
まず筆者は、18~19世紀の哲学者ジェレミー・ベンサムによる「功利主義」の考え方を紹介しています。功利主義とは、「多くの人にとっての幸福=快楽を最大化することが善である」という考え方です。
この考え方では、「幸福」は快楽という形で数値化・計算可能とされ、それに基づいて合理的な政策が決定されるべきだとされます。つまり、国家が「みんなにとっての幸福」を定義し、その実現を図るというわけです。
しかし、この考え方には大きな問題があります。それは、「幸福の内容を誰が決めるのか?」という点です。国家が幸福の中身まで決めてしまえば、個人の自由意志、つまり「自分でどう生きたいかを決める自由」は大きく制限されてしまいます。
このように、功利主義には合理性の一方で、個人の自由との衝突という根本的なジレンマがあるのです。
アーキテクチャーによる行動制御
続いて筆者は、近年注目されている「アーキテクチャー論」を取り上げています。
アーキテクチャーとは、人間の行動を技術的に制御するための環境設計のことです。たとえば、違法コピーを防ぐために最初からコピーできないように設計されたソフトウェアなどがその例です。
このような仕組みは、私たちが「それをやるか・やらないか」を選ぶ余地をなくしてしまいます。つまり、意識的な判断や自由な選択を経ずに、人の行動を“望ましい方向”へ誘導してしまうのです。
この手法は、説得や教育のような“手間”を省き、コストや不快感を減らす効果があるとされます。しかし同時に、「自由に選ぶ」という人間らしさが見えにくくなるリスクもはらんでいるのです。
超アーキテクチャーと「管理される幸福」
さらに筆者は、未来の技術発展によって「超アーキテクチャー」が生まれる可能性について論じます。
それは、人間の「欲望」そのものを操作する技術です。たとえば、人が最初から「悪いこと」を望まず、「善いこと」だけを自然に望むような社会が作られたとしたら、そこでは「自由」とは何かを問う必要すらなくなってしまうかもしれません。
そうした社会では、支配と被支配、自由と不自由といった概念が曖昧になります。そして、結果的に「みんなの幸福を最大化する」ことが唯一の正しさになる、超功利主義的な社会へと進んでいく可能性があります。
筆者の主張:私たちは何のために自由でありたいのか
このような未来を見据えて、筆者が私たちに訴えているのは次のことです。
「テクノロジーによって無意識に管理されるような社会が現実のものになったとき、自由の意味はどう変わるのか?そして、自由は本当に必要なのか?」
快適で便利な社会の裏側で、「自由」は見えないかたちで失われているかもしれません。筆者は、暴力や圧政といった古典的な抑圧ではなく、むしろ「便利さ」や「快適さ」が自由の最大の敵になるかもしれない、という新しい視点を提示しているのです。
「私たちは、何のために自由でありたいのか?」
その問いは、技術が進歩し、選択肢が見えなくなる未来において、ますます切実な意味を持つようになるでしょう。自由は「あるのが当然」ではなく、あえて「守る理由」を考え直すべき時代が来ているのかもしれません。
『何のための自由か』の意味調べノート
【総和(そうわ)】⇒ いくつかの数や量をすべて合計したもの。
【功利主義(こうりしゅぎ)】⇒ 多くの人の利益や幸福を求めることが、人生・社会の最大の目的であるとする思想的立場。
【主観的(しゅかんてき)】⇒ 個人の感情や価値観に基づくさま。
【客観的(きゃっかんてき)】⇒ 個人の感情に左右されず、事実に基づくさま。
【計量化(けいりょうか)】⇒ 目に見えないものを数値で表せるようにすること。
【合理的(ごうりてき)】⇒ 無駄がなく、理にかなっていること。
【矯正(きょうせい)】⇒ 欠点や誤りを正して直すこと。
【本末転倒(ほんまつてんとう)】⇒ 大事なこととそうでないことを取り違えること。
【福祉(ふくし)】⇒ 人々の生活の幸福と安定、特に社会的弱者への支援。
【策定(さくてい)】⇒ 計画や方針などをしっかりと定めること。
【包括的(ほうかつてき)】⇒ すべてを包み込むような、広い範囲を含むさま。
【論壇(ろんだん)】⇒ 世の中のさまざまな社会的・思想的な意見が交わされる場。
【遵法(じゅんぽう)】⇒ 法律や規則に従い、固く守ること。
【可視的(かしてき)】⇒ 目に見えるようになっているさま。
【論調(ろんちょう)】⇒ 論じるときの主な方向性や語り口の傾向。
『何のための自由か』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①レイボウを弱める。
②それは規則にテイショクする。
③重いケイバツが科された。
④レポートをテンサクされた。
⑤基礎体力をイジする。
次のうち、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)功利主義は自由を尊重する立場であり、現代でも国家統治の基本原理として広く用いられている。
(イ)アーキテクチャーは人間の自由意志を強化する技術であり、自由の拡大に貢献している。
(ウ)快適さを追求する環境設計が進むことで、自由という概念の意味が見えにくくなる可能性がある。
(エ)人間の欲望は本質的に自由であり、どんな環境であっても制御することはできない。
まとめ
今回は、『何のための自由か』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。