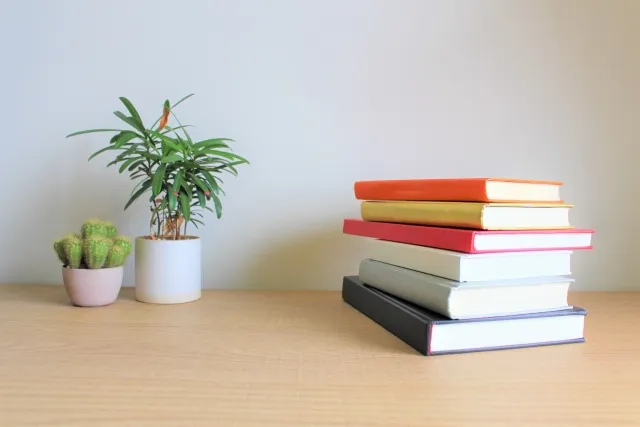『心に「海」を持って』は、教科書・論理国語で学習する文章です。そのため、定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『心に「海」を持って』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『心に「海」を持って』のあらすじ
本文は、三つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①かつて海は、巨大な文明の篩(ふるい)であった。文明どうしを繋ぎながら隔て、選ばれた人と文物だけに、交流を許した。海の篩は、文明を伝えて文化を伝えなかった。海はまた、文明を間隔を置いて断続的に伝播させることで、内部からの変革を促した。文明を運んだ人びとは、二重の孤独になりがちであった。だが、その孤独のなかで彼らは異文明の全体を理解し、文明交流の難しさも、どんな覚悟が必要かも学んだ。海は文明を相互に開かせるとともに、そのそれぞれに求心力を与え、生きた有機体として統一する力を持っていた。
②二十世紀は、海のそうした力が失われ始めた時代であった。海を渡る手段が船から航空機に代わり、大量の普通の人間が、文明の空白の時間を持たずに異文明を訪れる。旅人は日常から別の日常へ移るだけで、自他の文明を強く意識する機会は乏しくなった。憂慮すべきは、このことが受容する側の人間を二つに分け、文明の立場と文化の立場を思想として対立させることである。争点になる世界標準とは、れっきとした外国文明であり、日本はそれを受容するほかないのが現実だが、どちら側にもその覚悟が薄れがちである。文化ぐるみの文明の異質性を噛みしめ、その融合を図った鴎外の忍耐が忘れられているのだ。
③現実の海の喪失は避けがたい以上、いま必要なのは心に海をもつことである。世界を知るには、インターネットの映像ではなく、生きた外国人と違いの見える近さでつきあうことである。逆に、風俗の表面的な共通性には距離を置いて、何が真に普遍的な文明かを徹底した思索の篩にかけることが必要である。
『心に「海」を持って』の要約&本文解説
この文章では、過去の「海」が文明交流において果たした役割と、現代における異文化理解のあり方について述べられています。
過去の「海」:文明の篩(ふるい)
かつて、海は文明同士を繋ぎながらも隔てる「篩(ふるい)」のような存在でした。
限られた人々だけが海を渡り、異文明と交流することで、それぞれの文明は独自の発展を遂げました。例えば、遣唐使は命がけで海を渡り、中国の進んだ文化を日本に持ち帰りました。
ただし、それは文化の一部分であり、全体ではありません。海は、文明を伝える一方で、文化を完全に伝えることはなかったのです。
現代:容易になった交流と深まる対立
現代は交通手段が発達し、誰もが容易に異文化に触れられるようになりました。ところが、その結果、異文化理解が表面的になり、文化と文明の対立が生まれています。
例えば、グローバル化が進む現代では、世界共通の基準(文明)が求められますが、それぞれの国や地域には独自の文化があります。このギャップが摩擦を生んでいるのです。
筆者の主張:心に「海」を持ち、異文化理解を深めよ
筆者は、このような現代において、過去の「海」のように、異文化に対して深く理解しようとする姿勢を持つべきだと主張しています。
表面的には同じように見える風俗や文化でも、その根本にある文明は大きく異なることを理解し、相手の立場に立って考えることが重要だということです。
具体例:
- 外国語を学ぶだけでなく、その背景にある歴史や文化を深く学ぶこと。
- インターネットで海外の情報を手軽に入手できる現代だからこそ、実際に現地の人と交流し、その文化や価値観に触れること。
これらの行動は、まさに「心に海を持つ」ことの実践だと言えます。
『心に「海」を持って』の意味調べノート
【篩(ふるい)】⇒ 物をふるい分けるための道具。
【文明(ぶんめい)】⇒生活を豊かにするもの。特に物質的なもの。
【立ち振る舞い(たちふるまい)】⇒ 行動や姿勢、振る舞い。
【固有(こゆう)】⇒ そのものに特有であること。他に類を見ないこと。
【恩恵(おんけい)】⇒ ありがたい助けや利益。
【文化(ぶんか)】⇒ 人間が作り出した精神的なもの、およびその活動。
【断続的(だんぞくてき)】⇒ 継続することなく途切れながら行われるさま。
【伝播(でんぱ)】⇒ 物事が広がっていくこと。
【飛躍(ひやく)】⇒ 進歩や発展を急激に遂げること。
【渡航(とかう)】⇒ 海外に行くこと。特に船で移動すること。
【にわかに】⇒ 突然。急に。
【伝道師(でんどうし)】⇒ 宗教や思想を広めるために活動する人。
【孤独(こどく)】⇒ 一人でいること。
【求心力(きゅうしんりょく)】⇒ 集団や団体が一つにまとまる力。
【有機体(ゆうきたい)】⇒ 生物として生命を持つ存在。
【海峡(かいきょう)】⇒ 海と海を繋ぐ狭い水路。
【含有量(がんゆうりょう)】⇒ 物の中に含まれる量。
【間断なく(かんだんなく)】⇒ 途切れることなく。連続して。
【普遍化(ふへんか)】⇒ あらゆる場所で共通して認められること。
【憂慮(ゆうりょ)】⇒ 心配し、気にかけること。
【焦慮(しょうりょ)】⇒ 何かを心配して落ち着かないこと。
【れっきとした】⇒ 明確で正当な。確かな。
【融合(ゆうごう)】⇒ 異なるものが一つになること。
【喪失(そうしつ)】⇒ 失うこと。失われること。
【思索(しさく)】⇒ 深く考え、思い巡らすこと。
『心に「海」を持って』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①企業からオンケイを受ける。
②その文化はコユウの特徴を持つ。
③突然の報告にショウゲキを受ける。
④彼はコドクな生活をおくっている。
⑤カイキョウを渡り、新しい土地に着く。
まとめ
今回は、『心に「海」を持って』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。