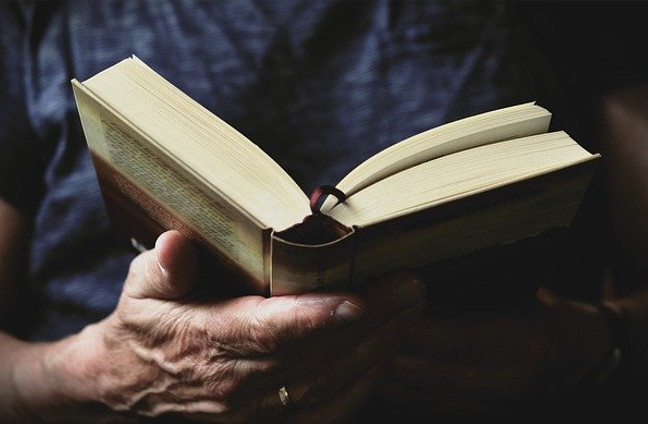「海抜」と「標高」は、どちらも高さや高度を表すものとして使われています。
この2つは「同義語」あるいは「類義語」に含まれるのでしょうか?それとも異なる意味の言葉として使い分けるべきなのでしょうか?
今回は、「海抜」と「標高」の違いについて詳しく解説しました。
過去の新聞記事での用例

まず、「海抜」と「標高」が過去の新聞ではどのように使われていたのかを調べてみます。以下は、昭和62年6月下旬に起こったフィリピン航空機の遭難事故を報じた新聞記事の一部です。
① 現場は、標高二、一〇〇メートルのプゴ山の山頂近く。事故当時、~。/バギオ市はマニラ北方約二百五十キロにあり、標高一、五〇〇メートルの避暑地として有名だ…
出典:朝日新聞 昭和62・6・27 第1面
② 低く垂れ込めた雨雲をかいくぐるように、事故機は低空飛行をしてきた。極度に視界が悪い中で、パイロットが目前に迫った海抜二千メートルを超えるプゴ山に気づいたらしい。
出典:朝日新聞 昭和62・6・27 第31面
③ 離陸後約七分、ウゴ山(標高二、一〇〇メートル)の山頂が雲海の上に見えた。
出典:朝日新聞(夕刊)昭和62・6・27 第15面
山の名前が朝刊ではプゴ山、夕刊ではウゴ山となっているのは別として、朝刊の第1面では「標高」、第31面では「海抜」と書かれています。また、同日の夕刊では「標高」と書かれています。
このように、過去の新聞記事では、同じ山の高さを表すのに同じ新聞、同じ日にち、同じ内容の報道記事に対して「海抜」と「標高」が用いられています。
地理教科書における記述

次に、明治から昭和にかけて用いられていた小学校用の地理教科書の記述をみてみます。実際の用例は以下の通りです。
① 富士山ハ其ノ高一万二千三百七十尺。
出典:『地理小学 巻一』(明治16・11)
② 加賀ノ白山本道第一ノ高山ニシテ直立凡ソ八千九百尺余アリ。
出典:『地理小学 巻二』(明治16・11)
③ 富士山は日本第一の高山にして、高さは海面より一万二千尺余アリ。
出典:『日本地理小誌 巻之上』(明治20・8)
④ 中にも乗鞍が丘は高さ一万四百尺余あり。
出典:『日本地理小誌 巻之下』(明治20・8)
⑤ 此山ハ、~直立一万二千尺~。
出典:『日本地理初歩 巻之上』(明治26・8・19)
⑥ 其最モ高キ峯ヲえべれすとト云フ、海面ヲ抜クコト二万九千尺。
出典:『万国地理初歩 巻之上』(明治27・1・10)
⑦ 此湖水ハ、あんです山脈中ノ高知ニ在リテ、海面ヲ抜クコト一万三千尺。
出典:『万国地理初歩 巻之下』(明治27・1・10)
⑧ 富士山は直立、一千二百丈余。
出典:『小学校用 日本地理第壱巻』(明治27・1・3)
⑨ 富士山は、高さ一万二千四百尺。
出典:『小学地理 巻一』(明治33・12・27)
⑩ 富士山直立一万二千三百七十尺。
出典:『修整 新定地理 巻之一』(明治34・11・14)
⑪ 雲取山ハ西境ニアリテ。其高サ七千三百尺余。
出典:『東京府郷土誌』(明治26・9・12)
⑫ 山名及び高度。
出典:『三重県地理』(明治32・2・25)
上記のように、過去の地理教科書においては「海抜」も「標高」も用いられていません。しかし、「海面より」「海面を抜くこと」などの言い方で用いられているものもあります。
いずれの場合も民間の教科書のものですが、文部科学省著作の教科書においても明治37年から昭和10年代まで常に「高さ」を用いていたという経緯があります。
国語辞典及び百科事典では?
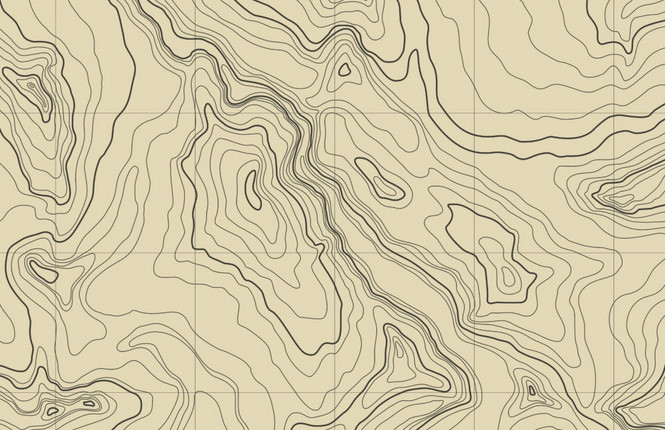
続いて、明治時代から今日に至るまでの、「国語辞典」及び「百科事典」の用例を確認してみます。
国語辞典・百科事典では、エベレスト、富士山の項目で高さをどのように記述しているか抜き出しました。
| 辞典名 | エベレスト | 富士山 |
| ことばの泉(M34) | 高さ一千四百十七丈余 | |
| 改修 言泉(S5) | 高さ一二四六七尺 | |
| 大辞典(S10) | 標高約八六四〇米 | 標高三七七六米 |
| 辞苑(S11) | 海抜八八四〇米 | 剣ヶ峯が最も高く三七七八米 |
| 広辞苑(S34) | 海抜八八四〇メートル | 剣ヶ峯が最も高く三七七六メートル |
| 新潮国語辞典(S40) | 高さ三七七六メートル | |
| 新選国語辞典(S41) | 高さ三七七六メートル | |
| 三省堂新国語中辞典(S42) | 高さ八八四七メートル | 高さ三七七六メートル |
| 角川国語辞典(S51) | 海抜八八四八メートル | 標高三七七六メートル |
| 国語大辞典(S57) | 標高八八四八メートル | 標高三七七六メートル |
| 言泉(S61) | 標高八八四八メートル | 標高三七七六メートル |
| 学習百科事典(S12) | 高さ八八四〇米 | 高さ三七七八米 |
| 世界山岳事典(S46) | 標高八八四八メートル | 標高三七七六メートル |
| 小百科事典(S49) | 標高8,848メートル | 標高3,776メートル |
| 国民百科事典(S51) | 標高8,848m | 標高3,776m |
| 現代百科辞典(S56) | 標高8,848m | 標高3,776m |
| 世界大百科事典(S56) | 標高は8,848m | 標高3,776m |
| 講談社百科事典(S57) | 〔標高〕8848m | 標高3376m |
※「S」は「昭和」「M」は「明治」を表し、空欄部分は記入無しを意味する。
見て分かるように、前半の「国語辞典」の方では山の高さを表す際に、辞典によって「海抜」と書いたり「標高」と書いたりしています。また、富士山の方には「高さ」が多く用いられています。
一方で、後半の「百科事典」の方も同様ではありますが、こちらは「海抜」よりも「標高」としているものの方が優勢です。
結局のところ、「海抜」と「標高」は、国語辞典及び百科事典では同じ意味の語として用いられています。
したがって、辞典及び事典としての意味は、どちらもほぼ同じような内容として使われていることになります。
なお、採録時期について見てみると、「標高」よりも「海抜」の方が早くから採録されているという事実があります。
新聞・放送界での使い分け

新聞やテレビなどの放送業界では、山や高原などの高さを言う際に「海抜」「標高」ともに意味を区別しないで用いています。
どちらかと言えば、「海抜」よりも「標高」の方が使用頻度は高いです。
しかし、例えば「海抜0メートル」などと言う場合は、「標高」を用いないという原則はあります。
また、後ろに「差」が付いて「標高差」などと言う場合も、「海抜差」とは言わないという原則があります。
これらのルールは、NHKがまとめた「放送のことば ハンドブック」に記されています。
「海抜ゼロメートル地帯」などは「海抜」であるが、その他の場合は「標高」を使ってもよい。普通は両者を厳密に区別しないで、同じような意味に使っている。「海抜」は古くからの語であるが、「標高」は比較的新しい語である。学校教科書では、「高さ」「山の高さ」を一般に使っている。
出典:「NHK 放送のことば ハンドブック」
また、学術的な観点で言うと、「学術用語集 地理学編」には「標高」は掲げていますが「海抜」は掲げていません。
以上の事から考えますと、複合語の一部を除いて、「海抜」「標高」のどちらを用いても構わないが、どちらか一方を選ぶとすれば「標高」の方を選ぶという結論になります。
なお、現在の日本では、東京湾の潮位の平均値(平均海水面)を基準とし、これを0メートルとしています。
地点の実際の測量には、東京都千代田区永田町に日本水準地点を設け、この高さを二四・四一四メートルとして高さを算出します。
これは、海は波の影響があるため、正確な数値を出すことができないためです。
ただし、離島に関してはそれぞれの島の湾における平均潮位を定め、それを高さの基準としています。
場所によって測定方法の違いがある両者ですが、現在は一部の離島を除き「海抜」と「標高」は同じ基準をとっています。
よって、実質的には「海抜」と「標高」は同じということになります。
まとめ
以上、内容をまとめると下記のようになります。
「海抜」と「標高」は、どちらも同じ意味。過去の「新聞」や「国語辞典・百科事典」では、ほぼ同じような意味として使われてきた。
放送界では、「海抜」よりも「標高」の方が使用頻度は高い。ただし、「標高0メートル」や「海抜差」などとは言わない。正しくは「海抜0メートル」「標高差」。
「海抜」と「標高」に、明確な意味の違いはありません。どちらも使うことができます。仮にどちらか一方を使うとするならば、汎用性のある「標高」の方を使うようにしましょう。