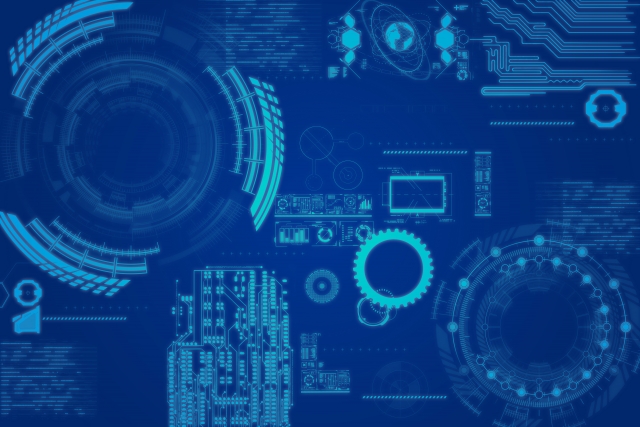
『文化としての科学』は、教科書・現代の国語で学習する評論文です。そのため、定期テストなどにも出題されています。
ただ、本文を読むとその内容や筆者の主張などが分かりにくい箇所もあります。そこで今回は、『文化としての科学』のあらすじや要約、テスト問題などを含め解説しました。
『文化としての科学』のあらすじ
本文は、大きく分けて4つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①西洋では、精神的生活に関わるものを「文化」、物質的所産に関わるものを「文明」と呼ぶのが普通である。その立場をとるなら、科学は文化の中核を成し、技術は文明の基礎と言うことができるだろう。科学と技術は本来別物であったし、その役割も異なっていたことを認識する必要がある。科学は文化として役に立つのであり、技術は文明の手段として役に立つ。文化としての科学は、私たちが精神世界を健全に生きていくうえで不可欠なものである。
②科学は芸術や宗教と同じような人間の精神的活動の成果である。科学研究に税金が使われるのは、市民の間で文化を大事にするという合意が基礎になっている。科学の営みを科学者に託し、科学者はその負託に応え、市民はそれを応援しつつその成果を享受する。科学が文化であるためには、社会的受容が欠かせないのである。精神的な安心感・充実感をもたらす科学は、人々の世界観や自然観と強く結びつき、社会に大きな影響を与える。そのため、科学者は科学が社会に円滑に受容されていくよう努める義務がある。
③だが、現代では科学の内実が変質し、技術とより強く結びつくようになる「科学の技術化」が進んでいる。いくつか理由があるが、「科学の最前線が特殊化・専門化し、自然全体を大きく切り取る基本理論に欠けているため」、「原理的な世界の発見が滞り、技術的な側面に力点を置かざるを得ないため」、「微視的世界の制御を通じて科学の前線を広げる動きが活発になり、科学と技術が重なり合っているため」、などがある。科学者も実用の役に立つという意識が強くなり、それに迎合する姿勢も強まっている。
④科学の技術化において問題なのは、企業の「経済的合理性」が優先され、環境倫理や安全性などの観点からの「技術的合理性」が問われなくなってしまうことである。科学者は、技術は現実との「妥協」の上に成立していることを認識し、安全が保証される限度を社会に伝えるという社会的責務があることを忘れてはならない。また、科学と技術の相違を見極め、技術的合理性がどこまで貫徹し、どこから破綻するかを常に言い続けなければならない。科学者は技術の危うさを知ったうえで、技術化への道を歩むべきことを常に自戒する必要がある。
『文化としての科学』の要約&本文解説
「科学」は文化として役に立つものであり、「技術」は文明の手段として役に立つものです。例えば、学問や芸術などはその国の文化として役に立ちますし、農業・工業技術などは文明の手段として役に立ちます。
また、科学が文化として成り立つためには、国民の税金が必要なため、社会的受容(社会に受け入れられること)が欠かせません。そのため、科学が社会に受容されていくように科学者は努める義務があると筆者は述べています。
ここまでが、第一段落~第二段落(前半)の内容ですが、筆者は次の第三段落で現代における科学と技術の問題点について触れています。
それは、科学の技術化(科学が技術と強く結びつくこと)により、「経済的合理性」が優先され、「技術的合理性」が問われなくなっているという問題です。
「経済的合理性」とは、できるだけ費用を抑えながら高い利益を上げる、という経済的な価値基準から見た考え方のことです。一方で、「技術的合理性」とは、科学の原理や法則を使い人工物として製品化する際に、どのような方式が最も合理的であるかという考え方のことです。
つまり、いかにお金をかけずに利益を上げるかという「経済的合理性」ばかりが優先され、安全や環境といった観点からの「技術的合理性」が後回しになってしまったということです。
本文中では、こういった問題点により、地震や津波などによって道路や原発が想定外の被害を受けてしまったことが例として挙げられています。
最終的に筆者は、科学者は科学と技術の違いをはっきりと見極め、どこからが破綻するかを常に言い続け、技術の危うさを知った上で技術化へ進むべきであると述べています。
つまり、危ないことを危ないとはっきりと言い、技術の危険さを理解した上で科学者は技術化を進めるべきということです。
全体を通して筆者が主張したいことは、最後の第四段落に集約されていると言えます。
『文化としての科学』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①組織のチュウカクを成す人物。
②相手のためにベンギを図る。
③代理人に一切をフタクする。
④彼は権力にゲイゴウする人物だ。
⑤将来についてキグする。
まとめ
今回は、『文化としての科学』について解説しました。ぜひ内容を正しく理解できるようになって頂ければと思います。なお、本文中の重要語句については以下の記事でまとめています。