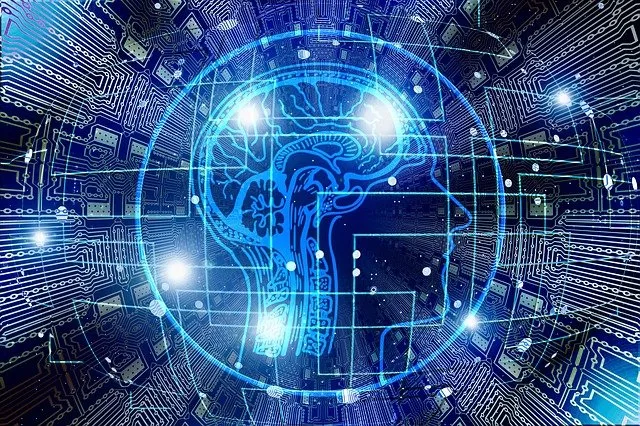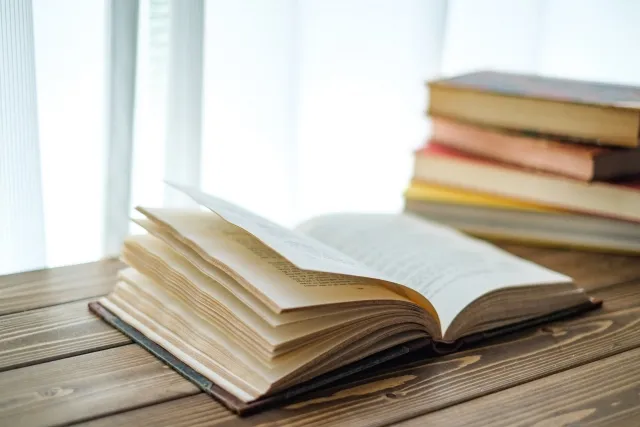
『わからないからおもしろい』は、木内昇によって書かれた文学作品です。教科書・文学国語にも取り上げられています。
ただ、本文を読むと筆者の考えが分かりにくいと感じる部分も多いです。そこで今回は、『わからないからおもしろい』のあらすじや要約、語句の意味などを解説しました。
『わからないからおもしろい』のあらすじ
本文は四つの段落から構成されています。以下に、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①私はあるトークショーで、一人の青年から「この本を読んだけど難しかったので、次はもっと簡単でわかりやすい内容にしてください」と言われた。私は、江戸の奇術に『胡蝶の舞』というのがあり、お客が想像して物語を見いだし、涙するという話をしてお茶を濁した。
②先のひと幕は、精魂こめて成した仕事を「ニーズに合わない」と切り捨てられた瞬間とも言える。このとき、私の中には動揺による青年への苦言に次いで、あらゆることを考えたうえでこの形に行き着いたのだから変えられないという思い、自分がもっと修練すれば、より多くの人に届かせることができるかもしれないという思いが順に湧いた。携わる事業に対する自分自身の信念と、世の需要とは必ずしも一致するとは限らない。二つの間で揺れ動きつつ、支柱となるところを見いだそうと努めるのが、仕事人の日々である。私は消費者の需要に配慮しつつ、結局は自分の信念を通してしまうことも多い。
③二十代の頃、伝統芸能や工芸の第一人者と呼ばれる方々にインタビューをした。その際に、ある方が「突き詰めれば突き詰めるほど、その先にあるものが見えてくる、だからわからなくなる。仕事には終わりがない」と話された。仕事において、人はすぐに結果を出したくて必死で平坦な近道を探す。だが、道を省けば、必ずその分の取りこぼしが出る。地道な作業の中にこそ、道を極めるのに必要な鍵が紛れ込んでいるのだ。
④私はかつて、「これはこうだ」と言い切れるものが好きだった。悟りを開いて悠然としている人に憧れていた。だが、社会に出て二十余年、いくら経験を積んでも明快な答えにはたどり着けない。人は、わからないから考え、想像し、工夫をし、成長する。「すぐにわかる」ような薄っぺらい場所ではなく、奥行きある世界に身を置いて、なかなかわからないものに、いつまでもおもしろがって関わっていけることこそが、仕事をするうえで至高のぜいたくであり、幸せなのではないか。
『わからないからおもしろい』の要約&本文解説
この文章で筆者が伝えたいことは、「仕事や学びにおいて、すぐにわかることよりも、わからないことと向き合うことの方が本当の面白さや価値につながる」というものです。
筆者は冒頭で、自身の著書を「難しいからもっと簡単にしてほしい」と読者に言われた経験を語ります。
これは自分の信念を込めた仕事が「ニーズに合わない」と切り捨てられた瞬間でもあり、筆者は需要と信念の間で揺れる苦悩を示しています。しかし、同時に「より多くの人に届くよう努力すべきだ」という前向きな気づきも描かれています。
続く部分では、伝統芸能や工芸の名人の言葉が紹介されます。名人は「突き詰めれば突き詰めるほど、わからなくなる」と語りました。
これは、表面的な理解や近道では到達できない深い世界があることを示しています。例えばスポーツでも、基礎練習を繰り返すことでしか得られない感覚があるように、仕事や芸術でも「わからないもの」と向き合う中で人は成長するのです。
筆者自身も若い頃は「明快な答え」に憧れていましたが、社会経験を重ねるうちに、世の中には簡単に割り切れないことが多いと知ります。だからこそ、人は考え、工夫し、成長していくのです。
そして「わからないこと」を面白がり、奥行きのある世界に関わり続けることが、仕事における最大の幸せであると結論づけています。
まとめると、この文章は「すぐに結果を求めるのではなく、わからないことに挑み続ける姿勢こそが成長と充実をもたらす」というテーマを伝えています。
受験勉強に置き換えれば、「わからない問題」こそが自分を鍛えてくれるチャンスだということです。わからなさを恐れず、むしろ楽しむことが大切なのです。
『わからないからおもしろい』の意味調べノート
【しかと】⇒しっかりと。確実に。
【一喝(いっかつ)】⇒一声、大声でしかること。
【一席をぶつ(いっせきをぶつ)】⇒大勢の人の前で演説や威勢のいい話をする。
【お茶を濁す(おちゃをにごす)】⇒その場しのぎの言葉や行動でごまかすこと。
【ひと幕(ひとまく)】⇒一つの場面や出来事。
【精魂(せいこん)】⇒精神と力。心身すべて。
【ニーズ】⇒需要。要求。相手の求めるもの。
【四の五の言わずに(しのごのいわずに)】⇒文句を言わずに。ごちゃごちゃ言わずに。
【煎じ詰めて(せんじつめて)】⇒結局のところ。要するに。
【二言(にごん)】⇒一度言ったことを取り消して違うことを言うこと。
【修練(しゅうれん)】⇒技芸や武道を磨き鍛えること。
【くだを巻く(くだをまく)】⇒酒に酔って同じことを何度も愚痴っぽく言う。
【短絡的(たんらくてき)】⇒物事を単純に結びつけて考えるさま。
【思惟(しい)】⇒論理的に深く考えること。
【需要(じゅよう)】⇒商品やサービスを買いたいという欲求。
【先鞭をつける(せんべんをつける)】⇒まだ誰も手をつけていないことに取り組む。
【創意工夫(そういくふう)】⇒新しい考えや方法を考え出すこと。
【のみならず】⇒そればかりでなく。それに加えて。
【煙たがられる(けむたがられる)】⇒敬遠される。疎まれる。
【おもねる】⇒相手にこびへつらう。
【支柱(しちゅう)】⇒支えとなるもの。指針。
【座右の銘(ざゆうのめい)】⇒常に心に留めて指針とする言葉。
【霞を食う(かすみをくう)】⇒世間離れして、収入が乏しい生活を送る。
【まっぴら御免(まっぴらごめん)】⇒絶対に嫌だ。かたく断る。
【些末(さまつ)】⇒取るに足らない細かいこと。
【アシスト】⇒助けること。補助。
【至難の業(しなんのわざ)】⇒きわめて困難なこと。
【悠然(ゆうぜん)】⇒落ち着いてゆったりしているさま。
【道標(みちしるべ)】⇒進むべき方向を示すもの。指針。
【違わず(たがわず)】⇒間違いなく。正しく。
【汲んでくれる(くんでくれる)】⇒思いやってくれる。理解してくれる。
【目を凝らす(めをこらす)】⇒注意してよく見る。
【証(あかし)】⇒証拠。証拠。
【至高(しこう)】⇒この上なくすぐれていること。最高。
『わからないからおもしろい』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①大声でコウギをする学生。
②セイコン込めて絵を描く。
③毎日シュウレンを積む選手。
④長い会議にタイクツした。
⑤シコウの一品を味わう。
次のうち、本文の内容と合っているものを一つ選びなさい。
(ア)仕事は常に消費者の要望に合わせることが第一であり、自分の考えを通すことは避けるべきである。
(イ)早く成果を出すためには近道を選ぶことが重要であり、地道な努力はあまり意味がない。
(ウ)わからないものと向き合い、考え、工夫し続ける中で成長し、それを楽しむことが仕事における最大の幸せである。
(エ)筆者は若い頃から一貫して「答えのない世界」に魅力を感じ、迷うことなくそれを追い求めてきた。
まとめ
今回は、『わからないからおもしろい』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。