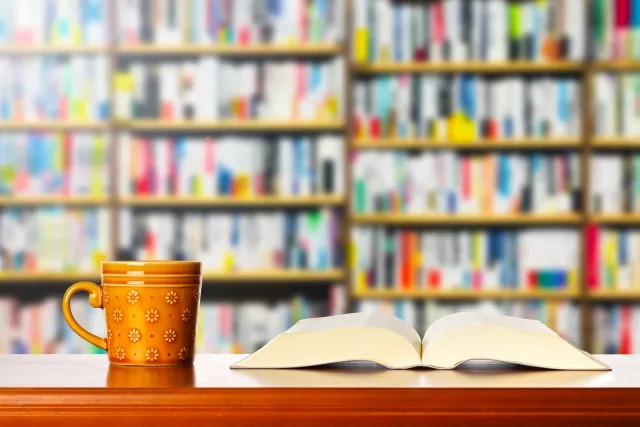
『哲学的思考とは何か』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『哲学的思考とは何か』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『哲学的思考とは何か』のあらすじ
本文は、三つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①哲学とは何か?それは、さまざまな物事の「本質」を捉える営みである。現代は、相対主義の時代である。この世に絶対に正しいことなどはない。だからといって、「共通了解」にたどり着けないわけではない。対話を通して物事の「本質」を理解し合える可能性はある。哲学は答えのない問題を考えているだけだと言われるが、それは全くの誤りだ。もっと大事な哲学の本質がある。それは、問題をとことん考え抜き、ちゃんと答え抜くことだ。それは決して絶対の正解ではない。だが、哲学はできるだけ誰もが納得できるような「共通了解」を見いだそうと探究を続けてきた。
②哲学思考法の初歩として、二つのポイントがある。一つは「一般化のワナ」に陥らないことだ。「一般化のワナ」とは、自分の経験を過度に一般化して、それが絶対に正しいこととして主張することである。「本質観取」とは、物事の「本質」を洞察する思考の方法であり、誰もが「本質的」とうなるような言葉をつむぐことである。この本質観取をやるにあたっても、私たちは「一般化のワナ」に陥らないよう、気を付ける必要がある。自分の意見が「一般化のワナ」に陥っていないか、たえず振り返る必要があるのだ。
③哲学的思考の初歩の二つ目は、「問い方のマジック」にひっからないことである。「問い方のマジック」とは二項対立的な問いのことだ。「問い方のマジック」は、まるでどちらかが正しい答えであるかのように人を欺く。たとえば、「人間は生まれながらに平等な存在か、それとも不平等な存在か?」という問いは、「問い方のマジック」にひっかかった「ニセ問題」だ。この問いを、「私たちは、互いに何をどの程度平等な存在として認め合う社会を作るべきだろう?」という建設的で意味のある問いに変える必要がある。哲学の本領の半分くらいは、 「ニセ問題」を、意味のある問いへ立て直すところにある。哲学の歴史は、こうした「ニセ問題」との戦いの歴史でもあったのだ。
『哲学的思考とは何か』の要約&本文解説
この文章で筆者が言いたいことをまとめると、次のようになります。
「哲学とは、答えのない問題をただ考えるのではなく、みんなが納得できる答えを探し、意味のある問いを立てるための思考法である」
1. 哲学の本質について
筆者はまず、「哲学は本質を捉える営み」だと述べています。
現代は相対主義の時代で「絶対に正しい答え」は存在しませんが、それでも人と人の間で納得できる「共通了解」は対話によって得られる可能性がある、としています。
そのため、哲学は「とことん考え抜き、できるだけ多くの人が納得できる答えを出すこと」を目的としています。
2. 哲学的思考の初歩(2つの注意点)
筆者は、哲学的思考を身につけるための基本として、次の2つを挙げています。
(1)「一般化のワナ」に陥らない
- 自分の経験を、まるで普遍的な真理のように思い込む危険を避けることが重要である。
- 物事の本質を見抜く「本質観取」を行う際も、このワナに気をつける必要がある。
(2)「問い方のマジック」にひっからない
- 二項対立(○か×か、白か黒か)の形で出された問いは、しばしば「ニセ問題」になりがちである。
- 哲学では、こうした問いをより建設的で意味のある問いに作り直すことが重要である。
例:
×「人間は平等か、不平等か?」
○「私たちは、どの程度の平等を認め合う社会を作るべきか?」
3. 筆者の最終的な主張
- 哲学は「答えがないことを考えるだけ」ではなく、より多くの人が納得できる答えを見つける探究の営みである。
- そのためには、思考のワナ(一般化やニセ問題)を避け、問いの質を高めることが大切である。
- 哲学の歴史は、こうした「ニセ問題」との戦いでもあった。
『哲学的思考とは何か』の意味調べノート
【営み(いとなみ)】⇒行為。行い。
【本質的(ほんしつてき)】⇒物事の根本に関わる重要な性質を持つさま。
【真理(しんり)】⇒いつ、どこでも変わらない正しいとされる事。
【意義(いぎ)】⇒物事の意味や価値。
【過度(かど)】⇒必要以上に多いこと。
【有識者(ゆうしきしゃ)】⇒特定の分野について、深い知識や経験を持つ人。
【従順(じゅうじゅん)】⇒人の言うことや命令に素直に従うこと。
【有り体(ありてい)】⇒ありのままであること。嘘や偽りがないこと。
【列挙(れっきょ)】⇒物事を順に挙げ並べること。
【生来(せいらい)】⇒生まれつき。
【堂々巡り(どうどうめぐり)】⇒同じ事が繰り返されて、進展がないこと。
【建設的(けんせつてき)】⇒ある物事について、現状をより良くしようと積極的な態度で臨むさま。
【域を出ない(いきをでない)】⇒ある範囲や程度を超えない。その範囲内にとどまっている。
【厳密(げんみつ)】⇒細かい点まで正確で手落ちがないさま。
【本領(ほんりょう)】⇒本来持っている能力や得意とする分野。
【撃破(げきは)】⇒打ち破ること。
『哲学的思考とは何か』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①彼のドウサツは鋭い。
②真理をタンキュウする姿勢。
③年功ジョレツを重んじる。
④ゲンミツな計算が必要だ。
⑤イダイな功績を称える。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)哲学は絶対的な正解を見つけることを目的とし、相対主義を否定している。
(イ)哲学は答えのない問題を考えるだけの営みであり、結論を出す必要はない。
(ウ)哲学は共通了解を探究し、一般化のワナや問い方のマジックを避けて思考する営みである。
(エ)哲学は二項対立的な問いを重視し、賛否を明確にすることを本質としている。
まとめ
今回は、『哲学的思考とは何か』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







