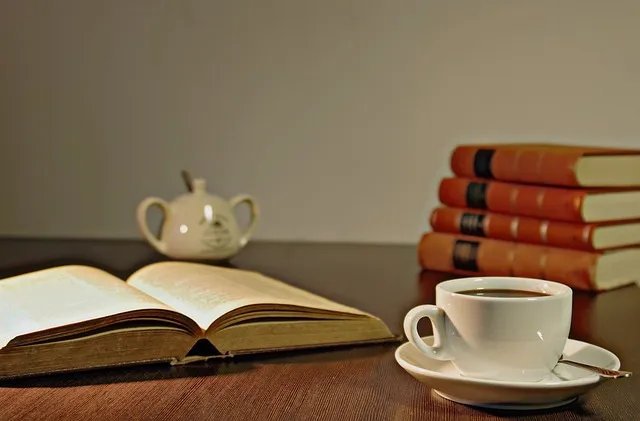
『思考の誕生』は、蓮實重彦という作者によって書かれた文章です。高校教科書・論理国語にも掲載されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『思考の誕生』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『思考の誕生』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①「自分で考えること」の重要さが教育の場で指摘されている。だが、そんなことばかりが推奨されているのは、危険な兆候である。この指摘は、自分ひとりで考えたことの帰結としてそう宣言しているわけではない。多くの場合、まったく「自分で考えること」などせず、あたりに流通する言葉を機械的に反復してみたにすぎない。この種の指摘は抽象的なものだが、あいかわらず「自分で考えること」の重要さを指摘する人が多いのは危険な兆候だ。
②「自分ひとりで考え」たことなど「たかが知れている」のは、まぎれもない事実である。そもそも、教育とは「他人とともに考えること」の実践である。だが、現代の教育現場では「他人」を互いに自己の内面のイメージを投影しあうこと、「他人」の「他人性」を希薄にすることが「他人」を理解することが考えられてしまっている。そのため、「自分で考えること」の重要さという抽象的な思考が生まれている。
③実際に「自分ひとりで考え」れば、「自分で考え」たことなどたかが知れていることに気が付くはずだ。学問の体系と歴史は「他人が考えたこと」の総体であり、それと触れることなく形成された思考など、思考の名には値しない。日常生活においても同じで、「自分で考えること」のほとんどは「他人が考えた」ことのくりかえしである。だから、重要なのは「自分で考えること」ではなく、「他人とともに考えること」である。「他人とともに考えること」とは、たやすくはイメージとして内面化しがたい「他人」に触れ、「自分」が変化する過程で新鮮な驚きとして、「自分の考え」が形成されることである。これが思考の誕生である。
④思考の誕生はきわめて具体的な体験であり、「自分で考えること」の抽象性から導き出されるものではない。あなたの知性は、思考の誕生に立ち会う感性をはぐくむために使われるべきだ。
『思考の誕生』の要約&本文解説
この文章では、一見すると「自分で考えること」を否定しているようにも読めます。しかし、筆者が本当に言いたいことは、「本当の意味での思考とは何か」を問い直し、「他人とともに考えること」の大切さを強調することにあります。
「自分で考えること」は本当に自分だけの考えか?
筆者はまず、「自分で考えること」が教育現場で強調されすぎている現状に対して疑問を投げかけます。そのような主張の多くは、実は本当に自分で深く考えた末に出た意見ではなく、社会の中に流通している決まり文句や価値観を繰り返しているにすぎないと指摘します。
つまり、「自分で考えることが大事だ」と言う人ほど、実はそれを自分の頭で考えたわけではない可能性が高い、ということです。ここに、筆者は危うさを見出しています。
「自分ひとりで考えること」には限界がある
次に筆者は、「自分ひとりで考えること」には限界があると述べます。
私たちが学ぶ知識のほとんどは、過去の他人が考えてきたことの積み重ねです。学問も日常生活の知恵も、他人の考えと切り離しては成り立ちません。
それにもかかわらず、「自分で考えること」が強調されすぎると、他人の考えを無視した、表面的で自己中心的な思考にとどまってしまう危険があるのです。
真の思考とは「他人とともに考えること」
ここで筆者は、思考とは「他人とともに考えること」から生まれると述べます。これは、単に他人の意見を聞くという意味ではありません。
自分とは異なる「他人」の存在と本気で向き合い、その違いや違和感から、自分の考えが揺さぶられ、変化する体験――その中にこそ、新しい思考の芽生えがあるというのです。
このような思考の誕生は、机の上で一人きりで生まれるものではなく、他人との関わりや対話の中でこそ育まれる「具体的な体験」だと筆者は強調しています。
知性の使い道とは
最後に筆者は、「あなたの知性は、思考の誕生に立ち会う感性を育てるためにこそ使うべきだ」と述べています。これは、ただ頭が良くなることを目指すのではなく、「他人とともに考え、自分が変わる体験をする力こそが、知性の本質である」というメッセージです。
筆者の主張
筆者の主張を簡潔にまとめると、「思考とは、自分ひとりで行うものではなく、他人とともに考え、影響を受ける中で初めて成立する」ということです。
「自分で考えること」はもちろん大切ですが、それを過信せず、他者との対話や関わりの中で思考を深めていく姿勢こそが、現代において本当に必要とされているのだと筆者は訴えています。
『思考の誕生』の意味調べノート
【概念(がいねん】⇒ 物事の意味や内容を、言葉でまとめたもの。
【無闇(むやみ)】⇒ 結果を考えずに行動すること。また、そのさま。
【推奨(すいしょう】⇒ よいとして人にすすめること。
【兆候(ちょうこう】⇒ 何かが起こるきざしや前触れ。
【帰結(きけつ】⇒ 最終的にそうなること。また、その結果。
【抽象的(ちゅうしょうてき】⇒ はっきりとした形がなく、具体的でないさま。
【趨勢(すうせい】⇒ 物事が今後どの方向に進みそうかという流れ。社会全体の流れ。
【萌芽(ほうが】⇒ 物事の始まりや芽生え。
【にわかには~しがたい】⇒ 急には~できない。すぐには~できない。
【擁護(ようご】⇒ 侵害・危害から、かばい守ること。
【言説(げんせつ】⇒ 物事についての言葉や論じ方。
【希薄(きはく】⇒ ある要素が少ないこと。
【蔓延(まんえん】⇒ 広がっていくこと。特に悪いものが広がること。
【基盤(きばん】⇒ 物事の土台となるもの。
【統御(とうぎょ】⇒ 全体をまとめて支配・管理すること。
【投影(とうえい】⇒ 自分の考えを他の人や物に映し出すこと。
『思考の誕生』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①シテキされて考えを改める。
②全ての行動はキケツを生む。
③強いシゲキが成長を促す。
④シンセンな野菜を購入する。
⑤作者の思いが作品にトウエイされる。
「希薄さ」=「自分」とは異質な存在である「他人」との遭遇は、めったにない体験であるということ。
「残酷さ」=自分の「思考」の枠組みやあり方が否定され、変化せざるをえない状態になるということ。
次のうち、本文の内容を表したものとして最も適切なものを一つ選びなさい。
(ア)「自分で考えること」は、他人に左右されずに意見を持つために重要であり、教育はその力を徹底的に養うことを目指すべきである。
(イ)真に自立した思考とは、自分ひとりで考えた末に到達する結論であり、他人の意見に頼らず形成されたものでなければならない。
(ウ)思考とは「自分で考えること」ではなく、「他人とともに考えること」の中で「自分」が変化し、新たな考えが生まれる具体的な体験である。
(エ)教育においては、他人の考えよりもまず自分の考えを重視し、それを抽象的にまとめる力を育てることが思考の基礎となる。
まとめ
今回は、『思考の誕生』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







