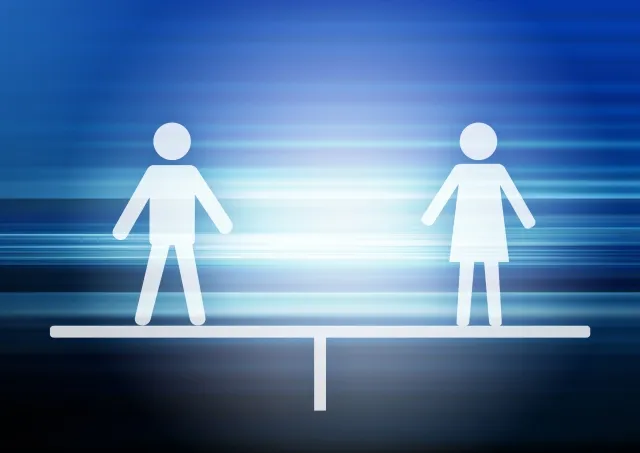
『男の絆、女たちの沈黙』は、教科書・論理国語で学習する文章です。そのため、定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『男の絆、女たちの沈黙』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『男の絆、女たちの沈黙』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①私は電車の中で失礼な態度の男性に腹を立てた。そのことを考えていると、ホモソーシャル、つまり男同士の「絆」ということに行き着いた。
②序列に基づいた男同士の関係というものがある。非礼な男もそんな慣習による言動かもしれないと思った。女性の友人に「僕が女性ならば、彼はもっと横柄な態度に出たのではないか」と電話で話すと、「女がそのような軽蔑を受けるのは日常茶飯だ。」と返された。女性の怒りの深さの一端に触れたような気がした。「社会」とは、男性には「社会」としか見えないが、女性には「男社会」に他ならない。女性にインタビューセッションを行うと、「何を話していいか分からない」と言う人が多い。その理由は、話してきたことを男たちに拒絶されてきたからだ。彼女たちは独自の文法と語彙を持っているが、それは男社会では価値を置かれない。
③いまだに「女性は感情論で話す。」と言う男性がいる。そう結論づけている男たちの論理の質を問うていくと、そもそも僕らの体験を構成しているあり方を検討しなくてはいけないのではないかと思えてくる。自分が何を感じているかに着目せず、言葉の上で破綻がなければ筋道が通っていると判断する感性からすると、女性たちの話しぶりは論理的には聞こえないかもしれない。だが、彼女たちの語りには感覚の一貫性がある。女性は男性とは違う論理を展開しているかもしれない。
④論理ではなく、「論理的」であることを重んじ、ディテールを把握する余裕のない、縮約したことを聞きたがる男性の耳には、彼女らの声が届かない。彼女たちは「(男)社会」の既存のやり方に従って話すことが求められる。古参のメンバーからは、ちゃんとしたコミュニケーションに見えるだろう。だが、それは彼女たちが現に話していることを受け取らない、拒絶のメッセージでしかない。どうして一方が当然と思っている理解の形にはまらないとコミュニケーションと呼ばれないのか。そのことについて男たちは考えたことがあるだろうか。考えずに済んでいるのは、やはり社会とは「(男)社会」であり、(男)の箇所が見えていないからだ。
『男の絆、女たちの沈黙』の要約&本文解説
本文は、筆者が電車で出会った無礼な男性をきっかけに、男性同士の「絆」=ホモソーシャルな関係や、女性が日常的に受けている抑圧について考えを深めています。
まず、男性同士の世界には、上下関係や力の関係があり、それに沿って言動が決まることがあります。電車の中での無礼な男性も、もしかするとそうした男性社会の文化に影響されていたのかもしれません。
筆者が「もし自分が女性だったら、あの男はもっとひどい態度をとったのでは」と話すと、女性の友人から「そんな扱いは日常茶飯事」と返されます。つまり、女性たちは日常的に無視や軽視される経験をしているということです。
また、女性たちが話すときに「何を話していいか分からない」と感じてしまうのは、これまで男性たちに話を否定された経験があるからだと筆者は述べます。女性は自分たちの感じ方や話し方を持っているのに、それが男性社会では評価されず、意味がないとされてしまうのです。
そして筆者は、「女性は感情的で論理的でない」と決めつける男性の側こそ、本当に論理的なのかと疑問を投げかけます。女性の語りには、論理ではなく感覚の一貫性があります。男性が重視する「筋の通った話」だけが正しいとするのは、偏った見方であり、女性の言葉を正当に受け取ろうとしない態度こそが問題だという主張です。
つまりこの文章のテーマは、「男性中心の社会の中で、女性の声が無視されていること」への問題提起です。そして、男性側が「当たり前」と思っている会話や論理のルールが、実は女性を排除しているのではないかと読者に問いかけているのです。
『男の絆、女たちの沈黙』の意味調べノート
【横あいから】⇒横の方から。
【律儀(りちぎ)】⇒まじめで融通がきかないさま。
【一瞥(いちべつ)】⇒ちらっと見ること。
【掌中(しょうちゅう)】⇒手のひらの中。
【一人ごつ】⇒ひとりでつぶやく。独り言を言う。
【不穏さ(ふおんさ)】⇒何かよくないことが起こりそうな不安な様子。
【恰幅が良い(かっぷくがよい)】⇒体つきがどっしりとしていて立派な様子。
【軽輩(けいはい)】⇒身分や地位の低い者。
【ぞんざい】⇒言葉や行動がていねいでなく、いい加減な様子。
【思い当たる節(ふし)がある】⇒心あたりがある。
【不均衡(ふきんこう)】⇒つり合いが取れていないこと。
【序列(じょれつ)】⇒地位や順序などの並び。上下関係の順位。
【不埒(ふらち)】⇒言動が許せない限度を超えているさま。
【指弾(しだん)】⇒非難すること。
【機を逃す(きをのがす)】⇒よいタイミングを逃してしまうこと。
【不遜(ふそん)】⇒へりくだる気持ちがなく、傲慢なようす。
【何の気なしに】⇒深く考えずに。無意識に。
【透明性(とうめいせい)】⇒物事がよく見える状態。
【語彙(ごい)】⇒ある人の使う語の総体。
【通俗的(つうぞくてき)】⇒一般大衆に分かりやすく、なじみやすい様子。
【単線的(たんせんてき)】⇒一本の線で。単純な関わりで。
【破綻(はたん)】⇒物事がうまくいかず、くずれること。
【話法(わほう)】⇒話し方。話す技術。
【縮約(しゅくやく)】⇒内容を要点だけに縮めてまとめること。
『男の絆、女たちの沈黙』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①リチギな性格が周囲の信頼を集める。
②レンソウから思わぬ答えが浮かぶ。
③ユウレツをつけるのは無意味だ。
④オウヘイな態度に不快感を抱く。
⑤全体の流れをハアクすることが大切だ。
次のうち、本文の主張として最も適切なものを選びなさい。
(ア)女性の語りは論理的であるため、男性社会でも常に正当に評価されてきた。
(イ)男性は感情に流される傾向が強く、女性の語りを理解できない。
(ウ)社会の中で当然とされている「論理性」には、男性中心の偏りがある。
(エ)女性が沈黙するのは本質的に話す能力に欠けているからである。
まとめ
今回は、『男の絆、女たちの沈黙』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







