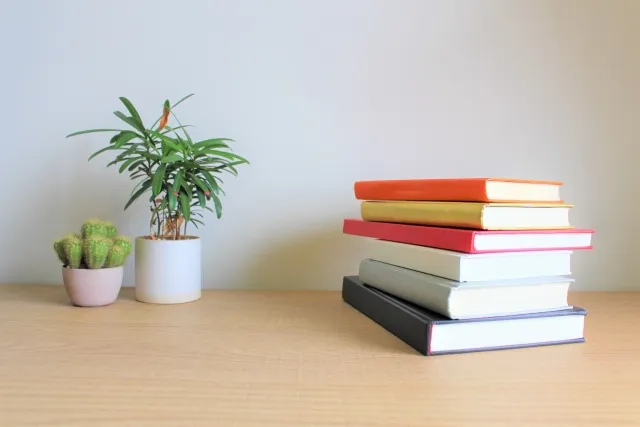『日本文化私観』は、坂口安吾によって書かれた文章です。高校教科書・論理国語にも掲載されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『日本文化私観』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『日本文化私観』のあらすじ
本文は、五つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①小菅刑務所という大建築物は、一か所の美的装飾もなく、どこから見ても刑務所以外の何物でも有り得ない構えである。だが、私はその美しさに不思議と心を惹かれた。
②聖路加病院の近所に、ドライアイスの工場があった。その工場が、奇妙に僕の心を惹いた。工場には一切の美的考慮というものがなく、ただ必要に応じた設備だけで一つの建築が成り立っている。この工場は僕の胸に食い入り、遥か郷愁につづいていく大らかな美しさがあった。
③ある春先、港町へ旅行に行くと、その小さな入り江の中に無敵駆逐艦が休んでいた。軍艦の美しさは私の魂をゆりうごかし、小菅刑務所とドライアイスの工場と軍艦という三つのものを一つにして、その美しさの正体を思いだした。それは、ただ必要なもののみが、必要な場所に置かれて、必要のみが要求する独自の形が出来上がっているということである。すべては、ただ必要ということである。そして、ここに何物にも似ない三つのものが出来上がったのだ。
④私の仕事である文学の美しさも同じである。美は、特に美を意識して成された所からは生まれない。書く必要のあること、そのやむべからざる必要にのみ応じて、書きつくされなけらばならない。終始一貫ただ「必要」のみであり、それが散文の精神であり、小説の真骨頂である。問題は、汝の書こうとしたことが、真に必要なことであるか、ということだ。そして、それが要求に応じて、汝の独自なる手により、不要なる物を取り去り、真に適切に表現されているかどうか、ということだ。
⑤見たところのスマートだけでは、真に美なる物とはなり得ない。すべては、実質の問題だ。美しさのための美しさは素直ではなく、本当の物ではない。つまり、空虚なのだ。それは有っても無くても構わない代物である。法隆寺も平等院も焼けてしまって困らない。その代物をこわしても、我が民族の文化や伝統は決して亡びはしない。西洋のものを模倣しても、我々の文化は健康であり、我々の伝統も健康である。真に生活する限り、猿まねを羞じることはない。それが真実の生活である限り、猿まねにも独創と同一の優越がある。
『日本文化私観』の要約&本文解説
この文章では、「美しさとは、必要性に基づいて自然に形づくられたものに宿るものであり、見た目の装飾や形式だけを追い求めても生まれない」という主張がされています。
筆者は、小菅刑務所、ドライアイス工場、軍艦といった、一見すると無骨で装飾のないものに心を惹かれました。これらに共通するのは、「必要なものが、必要な場所に、必要な理由で存在している」という点です。
このように、余分なものを一切持たず、機能のためにだけ形づくられた姿に、筆者は本質的な美を見出しています。
この考え方は、筆者自身の仕事である文学にも当てはまると述べられています。文章や小説も、美しく見せようとして装飾的に書くのではなく、「書かなければならない必然性のある内容」を、無駄を削ぎ落として表現することが重要だとされています。
つまり、美しさは内容の本質から自然と生まれるものだということです。
また、筆者は文化や伝統についても同様の姿勢を示しています。たとえ歴史的建造物が失われても、文化の本質が生活の中に息づいていれば、それは失われないと主張しています。
そして、西洋の模倣であっても、それが必要に基づいて生まれたものであれば、模倣もまた独創と同一の優越があると述べています。
要するに筆者は、見た目の華やかさにとらわれるのではなく、「必要性と実質」に根ざしたものこそが、本物の美や文化を形づくると考えているのです。
『日本文化私観』の意味調べノート
【大概(たいがい)】⇒ だいたい。おおよそ。
【獄舎(ごくしゃ)】⇒ 囚人を収容する建物。
【刑務所然(けいむしょぜん)としており】⇒ 刑務所そのままであるさま。接尾語の「然」は「~らしい」「~のような」という意。
【威圧的(いあつてき)】⇒ 圧力をかけておさえつけるような様子。
【終夜運転(しゅうやうんてん)】⇒ 夜通し運転すること。一晩中の運転。
【同人(どうじん)】⇒ 同じ目的や志を持つ人。仲間。
【変哲もない(へんてつもない)】⇒ 特に変わったところがない。普通である。
【美的考慮(びてきこうりょ)】⇒ 美を考えに含めている様子。
【魁偉(かいい)】⇒ 体つきや姿かたちが人並み外れて大きく立派なさま。また、いかついさま。
【異観(いかん)】⇒ 珍しい光景。
【頭抜けて(ずぬけて)】⇒ とびぬけて。なみはずれて。
【たあいもない】⇒ 幼稚だ。
【郷愁(きょうしゅう)】⇒ 故郷をなつかしく思う気持ち。
【強いて(しいて)】⇒ 無理にでも。ことさらに。
【尖端(せんたん)】⇒ 物の一番先の部分。
【飽かず(あかず)】⇒ 飽きることなく。
【鋼鉄(こうてつ)】⇒ 非常に硬くて丈夫な鉄。
【旧来(きゅうらい)】⇒ 昔からの。
【汝(なんじ)】⇒ おまえ。
【疾走(しっそう)】⇒ 速く走ること。
【専ら(もっぱら)】⇒ ひたすら。そのことだけをする様子。
【詮ずるところ(せんずるところ)】⇒ つまるところ。結局。
【光輝(こうき)】⇒ ほまれ。
【落日(らくじつ)】⇒ 沈む夕日。沈みかかった太陽。
【累々たる(るいるいたる)】⇒ 物がいくつも重なって並ぶ様子。続々と続く様子。
【高架線(こうかせん)】⇒ 高い位置に架けられた鉄道や道路。
【猿まね(さるまね)】⇒ 深い理解なく、ただ真似すること。うわべだけ他人の真似をすること。
【羞じる(はじる)】⇒ 恥ずかしく思う。恥じ入る。
『日本文化私観』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①ヒンコン家庭を支援する。
②個人情報のセンサクは控えるべきだ。
③努力がルイセキして成果につながる。
④アナウンサーが試合をジッキョウする。
⑤失敗に対してカンヨウでいる。
次のうち、本文の内容を最も適切に表しているものを選びなさい。
(ア)文化や伝統は形を守ることが最も重要であり、古い建造物を保存することこそが日本文化を継承する道である。
(イ)美しさとは形式美にあるのであり、文学や建築においても見た目の美しさを優先すべきである。
(ウ)美しさとは、必要に応じて生まれた形に宿るものであり、文化や表現もその「やむべからざる必要」によって成立するべきものである。
(エ)猿まねによる創造は文化の堕落を意味し、日本文化は西洋文化の影響を排除すべきである。
まとめ
今回は、『日本文化私観』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。