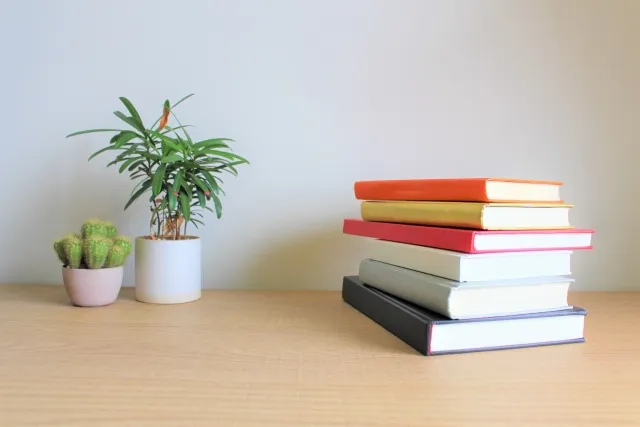『ものとこと』は、木村敏によって書かれた評論文です。高校教科書・論理国語にも掲載されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『ものとこと』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『ものとこと』のあらすじ
本文は、三つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①われわれは至るところ、"もの"に取り囲まれて生きている。ものはわれわれの生活空間を満たしている。ものが空間を満たしているということは、われわれの外部の世界についてだけではない。意識と呼ばれるわれわれの内部空間も、ものによって満たされている。外部的な眼で見るにしても内部的な眼で見るにしても、見るというはたらきが可能であるためには、ものとのあいだに距離がなければならない。見られるものとは、ある距離をおかれて眼の前にあるもののことである。それが「対象」あるいは「客観」という言葉の意味である。ものはすべて客観であり、客観はすべてものである。
②しかし、われわれが世界を客観的に見ることをやめるなら、"こと"の世界が立ち現れる。ことは、すべてきわめて不安定な性格を帯びている。ことは、客観と主観の内側、あるいはあいだにあり、色も形も大きさもなく、場所も指定できない。私たちの意識は、そうした不安定さを好まない。ものとことのあいだには、決定的な差異があるのだ。
③"ことば"はそれ自体一種の"もの"でありながら、その中に生き生きとした"こと"を住まわせている。そこでは、ものとこととのあいだに一種の共生関係がある。この共生関係が認められるのは、俳句や詩のような言語芸術の場合だけではない。芸術作品といわれるものはすべて、もの的な表現素材を通じてこと的な世界を開いている。さらに、人間の表現行為に属するすべてのものも、ものに即してことを感じとるという構造をもっている。
『ものとこと』の要約&本文解説
1. 「もの」とは何か?
私たちは常に「もの」に囲まれて生きています。「もの」は目に見える形で私たちの外の世界を満たしているだけでなく、心の中の世界=意識の中にも存在しています。
そして重要なのは、「もの」を見るためには、それとのあいだに距離が必要だという点です。つまり、「見る」という行為は、ある対象(=もの)との間に空間的・心理的な隔たりがあることで成り立ちます。筆者はこのように見える「もの」のことを、「客観」あるいは「対象」と呼んでいます。
✔️ ポイント:「もの」とは、私たちが見ることのできる外の世界や心の中の“対象”。距離をおいて捉えるもの。
2. 「こと」とは何か?
一方、「こと」とは「もの」とはまったく異なる世界です。「こと」は色も形もなく、不安定でつかみどころがありません。それは、「もの」のように目の前にあるわけではなく、主観(わたし)と客観(対象)のあいだに浮かぶような存在です。
たとえば、誰かとけんかした「こと」や、心が揺れ動いた「こと」は、形として目に見えませんが、確かに存在しています。
しかし私たちの意識は、このような不安定であいまいな「こと」をあまり好まない傾向があります。だからこそ、世界を「もの」として整理し、安定して捉えようとするのです。
✔️ ポイント:「こと」とは、感情や出来事のように目には見えないが、確かに感じられる“不安定な経験”。
3. 「ことば」は「もの」と「こと」のあいだにある
筆者は、「ことば」はこの「もの」と「こと」の橋渡しをしていると述べています。言葉は、紙に書かれた文字や声として存在するので「もの」でもありますが、その中に人の思い・感情・出来事(=「こと」)を宿しています。
俳句や詩などの芸術では、この関係が特にはっきりと見られます。たとえば、一句の中に自然の風景(もの)を描きながら、そこに込められた感情や空気(こと)を読み取ることができます。
さらに、この「ものを通じてことを伝える」という構造は、芸術だけでなく、人間のあらゆる表現行為に共通していると筆者は言います。
✔️ ポイント:「ことば」や芸術は、「もの」と「こと」の両方を含み、私たちに深い意味や感情を伝える。
4. 筆者の主張まとめ
筆者の主張は、「世界をただ『もの』として見るだけではなく、そこにある『こと』を感じ取る視点が大切だ」ということです。さらに、「ことば」や「芸術」は、そうした「こと」の世界を私たちに開いてくれる重要な手段であるとも述べています。
つまり筆者は、「もの(客観的な世界)」に偏りがちな私たちの意識に対して、「こと(主観と主観のあいだに生じる経験)」の重要性を再認識させようとしているのです。
日々の生活の中では、つい目に見える「もの」ばかりに意識が向きがちですが、その背後には必ず「こと」があります。誰かの言葉に感動したり、音楽に心を揺さぶられたりするのは、そうした「こと」に私たちが触れているからなのです。
『ものとこと』の意味調べノート
【趣旨(しゅし)】⇒文章や詩で言おうとしている事柄。
【想念(そうねん)】⇒ふと心に思い浮かべた考えやイメージ。
【占有(せんゆう)】⇒ある物や空間を自分のものとして実際に使っていること。
【対象(たいしょう)】⇒意識や行為の向かう相手やものごと。
【客観(きゃっかん)】⇒主観の認識および行動の対象となるもの。
【主観(しゅかん)】⇒認識・行為・評価などを行う、意識をもつ自我。
【余韻(よいん)】⇒物事が終わった後にも残る味わいや感じ。
【自然科学(しぜんかがく)】⇒自然の現象を観察・実験によって解明する学問。
【哲学(てつがく)】⇒根本的な問いを考え、世界や人生の意味を探求する学問。
【金科玉条(きんかぎょくじょう)】⇒絶対に守るべき大切な規則や教え。
【本領(ほんりょう)】⇒本来、専門とする領域。
【所在(しょざい)】⇒存在するところ。
【様相(ようそう)】⇒物事のありさまや様子。
【命題(めいだい)】⇒証明や検討の対象となる問題や主張。
【共生(きょうせい)】⇒異なる存在がともに関係を保ちながら生きること。
【不可避(ふかひ)】⇒避けることができないこと。
【即する(そくする)】⇒ぴったりと合う。
【合致(がっち)】⇒考えや条件などがぴったりと一致すること。
『ものとこと』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①リンカクがぼんやりと浮かび上がる。
②歴史についてジョジュツされた資料。
③不要なデータをショウキョする。
④会議の内容をすぐにホウコクした。
⑤彼は質問に対してチンモクを貫いた。
次のうち、本文の内容を表したものとして最も適切なものを一つ選びなさい。
(ア)ものとは目に見えず形もないが、主観と客観のあいだに生じる不安定な存在である。
(イ)こととは私たちの意識の内部空間を満たす存在であり、距離を置いて見ることで客観となる。
(ウ)ことばとは、ものとことの性質をあわせ持ち、ことを宿すことで芸術や表現行為を可能にしている。
(エ)人間の表現行為は、すべて客観的な対象であるものを通じて、安定した意味を明確に伝えることにある。
まとめ
今回は、『ものとこと』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。