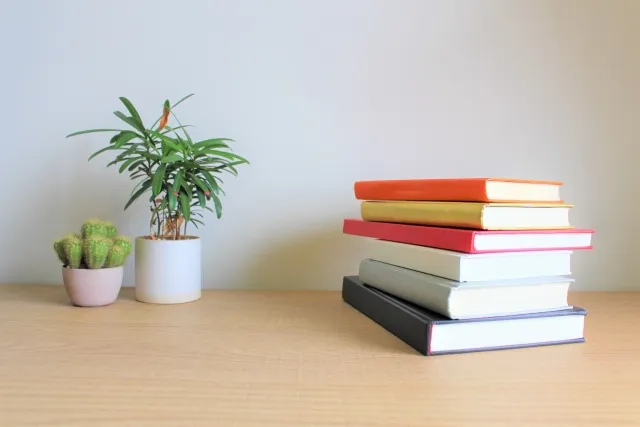『名所絵はがきの東西』は、教科書・論理国語で学習する文章です。そのため、定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくい部分も多いです。そこで今回は、『名所絵はがきの東西』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『名所絵はがきの東西』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①国内でも外国でも、初めての場所や名所旧跡を訪れると、必ず絵はがきを買う。それは記念の意味もあるが、絵はがきはさまざまな情報を伝えてくれる貴重な資料となるからだ。絵はがきを見れば、町の主要な観光スポットはおよそ見当がつき、教会堂のような巨大な建築物の細かい装飾などもよくわかる。
②西欧の名所絵はがきは、余計なものを切り捨て、対象そのものを正面から画面いっぱいに捉えるというやり方を採っている。日本の観光絵はがきは、お寺でもお城でも、建物だけを捉えたものはまれで、周囲の自然と一体になった建造物をモチーフとしたものが多い。
③これは、名所についての日本人の考え方、自然観と密接に結びついている。もともと日本人にとって名所とは、自然景と一体になったものであった。つまり、「名所」とは、単に空間的な場所であるだけでなく、時間、それも循環する時間と一つになった場所なのである。だが、西欧のモニュメントは、自然の変化や時間の経過を超えて永続するものを目ざして造られた。それは、記憶の継承のための装置として、容易に失われない堅牢な石の建造物になっている。もちろん日本人も思い出を大切にするが、日本人は昔から、記憶の継承を物質的な堅牢性に頼るのではなく、自然の運行の中にその保証を見いだした。
④そのことは、都市作りのあり方にも表れている。西欧のモニュメントは、町のランドマークとしての機能も果たす。だが、日本においては、都市のランドマークとなるのは、やはり自然である。このように、浮世絵や観光名所絵はがきは、東と西の自然観や美意識の違いを物語っていると言える。
『名所絵はがきの東西』の要約&本文解説
筆者は、名所を訪れた際に「絵はがき」を買う理由として、さまざまな情報を伝えてくれる貴重な資料となるからだと述べています。
そして、日本と西欧の絵はがきの特徴を比較し、それが文化的背景と結びついていることを論じています。
西欧の絵はがきは、観光名所を正面から大きく捉え、建物そのものを強調する傾向があります。一方、日本の絵はがきは、建物だけでなく、その周囲の自然を含めて表現することが多いです。
この違いの背景には、それぞれの文化の「名所」への考え方や、「自然」との向き合い方が関係しています。
西欧では、モニュメント(記念建造物)は、時間や自然の変化を超えて存続するものとして作られます。
それに対し、日本では、名所は自然と一体化し、時間の流れとともに移り変わるものと捉えられます。日本人は、記憶を堅牢な石の建造物に残すのではなく、自然の移り変わりの中に見いだすのです。
この考え方の違いは、都市の作り方にも現れています。西欧では、大聖堂や塔のようなモニュメントが都市のランドマークになりますが、日本では、富士山のような自然がランドマークの役割を果たします。
こうした違いが、浮世絵や観光名所絵はがきにも反映されているのです。
このように、筆者は、名所絵はがきの違いを通して、日本と西欧の文化的な価値観や自然との向き合い方の違いを読者に説明しています。
『名所絵はがきの東西』の意味調べノート
【名所(めいしょ)】⇒観光地。歴史的に重要な場所。
【旧跡(きゅうせき)】⇒過去の遺物や建造物。
【絵はがき(えはがき)】⇒裏面に写真や絵などのある葉書。
【見当がつく(けんとうがつく)】⇒予想や目安がつく。
【装飾(そうしょく)】⇒美しく飾ること。飾りつけ。
【愛嬌(あいきょう)】⇒魅力的で人を引きつける性質。
【由緒(ゆいしょ)】⇒その物事の歴史的背景や由来。
【特筆(とくひつ)】⇒特に注目すべきこと。
【郊外(こうがい)】⇒都市の周辺地域。
【華麗(かれい)】⇒華やかで美しいさま。
【傑作(けっさく)】⇒非常に優れた作品。
【驚嘆(きょうたん)】⇒驚き、感心すること。
【祭壇(さいだん)】⇒宗教儀式などで使用される、神に捧げる台。
【遊び心(あそびごころ)】⇒楽しむことを意識した軽い気持ちや工夫。
【もどかしい(もどかしい)】⇒物事が思うように進まず、イライラする様子。
【凱旋門(がいせんもん)】⇒軍の勝利を記念して作られた門。
【モチーフ(もてぃーふ)】⇒作品の中心となるテーマや素材。
【排除(はいじょ)】⇒不必要なものを取り除くこと。
【循環(じゅんかん)】⇒物事が繰り返し回ること。流れが繰り返されること。
【モニュメント(もにゅめんと)】⇒記念碑。記念建造物。
【継承(けいしょう)】⇒前のものを受け継ぐこと。
【忘却(ぼうきゃく)】⇒すっかり忘れてしまうこと。忘れ去ること。
【容易(ようい)】⇒簡単であること。
【堅牢(けんろう)】⇒非常に頑丈で壊れにくいこと。
『名所絵はがきの東西』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①ソウショクが壁に飾られている。
②イリョクのある武器を使う。
③彼は絶好のキカイを逃した。
④ケイカを追うたびに状況が変わる。
⑤商品にはホショウがついているので安心だ。
まとめ
今回は、『名所絵はがきの東西』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。