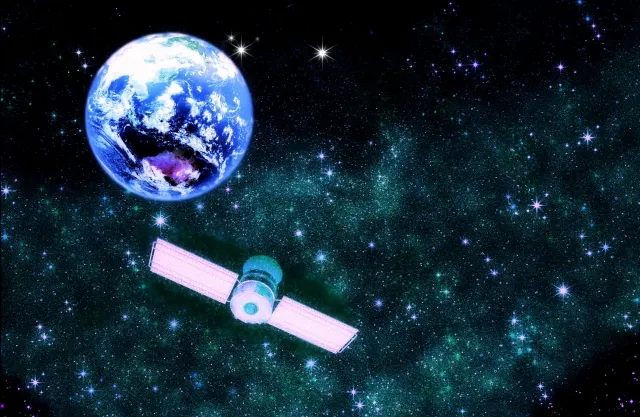
『ヒトはなぜヒトになったか』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる部分も多いです。そこで今回は、『ヒトはなぜヒトになったか』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『ヒトはなぜヒトになったか』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①ヒトの祖先としていちばん古い種類は、サヘラントロプスとオロリンだと言われている。サヘラントロプスは、背骨が頭の下についている。また、オロリンは大腿骨の仕組みから直立二足だとわかる。だから、彼らがヒトの祖先だとわかるのだ。最近の研究では、人は平原に出る前の森で暮らしている段階から二足歩行をしていたと考えられるが、理由は謎のままである。
②ではなぜヒトは、過酷な平原やサバンナに進出していったのか。その時代、地球上では乾燥・寒冷化が進み、生息地であるアフリカの森林が少なくなっていた。その際に、環境変化のためにサバンナに出ていかざるを得なかったのがヒトであった。サバンナには水も食料もほとんどないため、大変に苛酷な生活環境だった。しかし、ヒトは、食料を確保するために、自然を利用して道具を製作し、活用することを覚えた。また、目標のために役割分担し、複数で共同作業することを知った。このときを契機として、ヒトは、ほかの動物と比べて格段に大きな脳を持つようになった。
③ヒトの脳は、サバンナに出ていき環境に適応したホモ属が出てきたころから、急激に大きくなった。とくに、自分を「客観的に見る」感覚を司っている前頭前野が大きくなった。その結果、他人の心を読んで共同作業をし、社会生活を営むようになった。
④人間の脳は、二回大きく拡張している。サバンナに進出したときと、ホモ・サピエンスが登場したときである。二回目に脳が発達した時期は、ホモ・サピエンスがアフリカ大陸からユーラシア大陸に進出していったときである。このことが秘密を解く手がかりになるかもしれない。ヒトはなぜ、アフリカ大陸から外界に出て行ったのか。その理由は、好奇心であり、冒険心からだと私は考える。それは、現在も我々が宇宙という空間に思いをはせ、ステーションを建設し、惑星を探査することと同じではないだろうか。
『ヒトはなぜヒトになったか』の要約&本文解説
ヒトはどのように進化し、なぜサバンナに出て行ったのか? さらに、なぜアフリカを離れたのか?これらの疑問に答えるのが、本文のテーマです。
① ヒトの祖先と二足歩行
ヒトの祖先として最も古いとされるのが「サヘラントロプス」と「オロリン」です。サヘラントロプスは、頭のつき方から二足歩行をしていた可能性が高く、オロリンも大腿骨の構造から直立歩行をしていたことが分かります。つまり、ヒトはかなり早い段階から二足歩行をしていたのです。しかし、その理由は現在でもまだはっきり分かっていません。
② サバンナへの進出と脳の発達
ヒトが森林からサバンナに出た理由は、気候変動によって森林が減少し、新たな生息地を求める必要があったからです。しかし、サバンナは食料も水も少なく、過酷な環境でした。そこで、ヒトは道具を作り、仲間と協力しながら食料を確保する知恵を身につけました。この適応が、脳の発達を促すことになったのです。
③ 脳の進化と社会性
サバンナに適応したヒトの仲間である「ホモ属」は、脳の発達が進みました。特に前頭前野が大きくなり、自分を客観的に見たり、他者の気持ちを理解する能力が発達しました。例えば、仲間同士で情報を共有し、協力して狩りをすることで、生存率を高めることができるようになったのです。
④ アフリカを出た理由は好奇心
ヒトの脳は二度大きくなりました。一度目はサバンナ進出時、二度目はホモ・サピエンスがアフリカからユーラシアへ移動したときです。ヒトがアフリカを出た理由は、生存のためだけではなく、より良い環境を求める中で生まれた「好奇心」や「冒険心」によるものだと考えられます。この探究心は、現在の宇宙開発にも通じるものです。
このように、ヒトの進化は「環境の変化」と「好奇心」の両方によって促されたものだと筆者は考えているのです。
『ヒトはなぜヒトになったか』の意味調べノート
【祖先(そせん)】⇒その家系や種族の先代にあたる者。
【系統(けいとう)】⇒共通の起源を持つもののつながり。
【解明(かいめい)】⇒不明なことを明らかにすること。
【過酷(かこく)】⇒非常に厳しく容赦のないこと。
【適応(てきおう)】⇒環境に合うように変化すること。
【外殻(がいかく)】⇒外側を包んでいる殻 (から)。
【難局(なんきょく)】⇒対処が難しい局面。困難な状況。
【分岐点(ぶんきてん)】⇒進路が分かれる重要な地点。
【契機(けいき)】⇒物事のきっかけ。
【司る(つかさどる)】⇒支配する。管理に置く。
【解析(かいせき)】⇒細かく分けて分析し、明らかにすること。
【客観的(きゃっかんてき)】⇒主観を交えず、事実や他者の視点に基づくさま。
【想像に難くない(そうぞうにかたくない)】⇒容易に想像できること。
【飽和(ほうわ)】⇒満ちて限界に達し、それ以上受け入れられない状態。
【因果関係(いんがかんけい)】⇒原因と結果が互いに関連し合う関係。
【探査(たんさ)】⇒未知の場所を調査すること。
『ヒトはなぜヒトになったか』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①事件の真相をカイメイする。
②空気がカンソウする。
③新しい環境にテキオウする。
④コンナンを乗り越えて成長する。
⑤市場がホウワ状態になる。
「サヘラントロプス」=背骨が頭の下についていたことで、直立二足歩行をしていたことがわかるから。
「オロリン」=大腿骨の仕組みが、二足歩行の生物の大腿部の仕組みと同じであるから。
ヒトがサバンナに進出した理由として適切なものを選びなさい。
(ア)サバンナの方が住みやすかったから。
(イ)気候変動により森林が減少したから。
(ウ)ほかの動物に追い出されたから。
(エ)新しい食べ物を探すために移動したから。
次の文の空欄を埋めなさい。
ヒトの脳が急激に大きくなったのは、環境に適応した①( )が登場したころであり、とくに②( )が発達したことで、他人の心を読んで共同作業をし、社会生活を営むようになった。
まとめ
今回は、『ヒトはなぜヒトになったか』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







