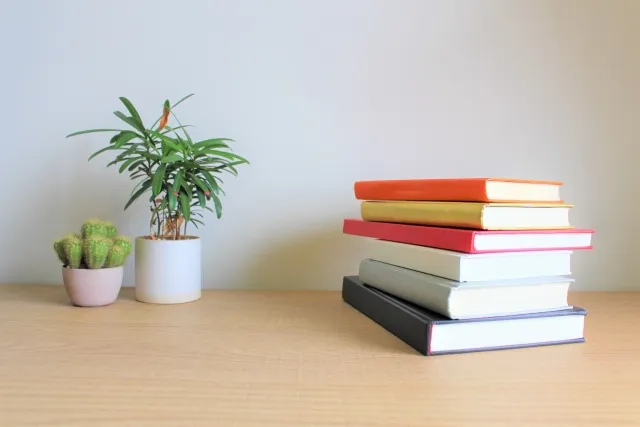『病気の向こう側』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『病気の向こう側』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『病気の向こう側』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを紹介していきます。
①レーウェンフックは、顕微鏡を通して微生物を観察した。それは「細菌」の姿の最初の観察と考えられる。このことは、同時代の自然哲学者たちにとって、「自然」や「世界」の意味を揺るがす大きな意味を持っていた。人間の身体的な感覚だけではとらえられないが、おそらく確かに存在しているものと考えられる世界への認識は、18世紀のヨーロッパでは「生命の起源」という問いにつながり、自然哲学研究が「自然科学的研究」へと質を変えていく原動力になった。これ以降、人間が理解するべき世界のありようと、そのために人間がとるべき方法を本質的に変えていくことになった。
②ただし、人類史にとっての微生物との出会いは、「病原菌」との出会いとイコールではなかった。レーウェンフックの「健康論」は、当時の医学理論自体に影響を与えるまではいかず、当時の医学者たちが彼の「小さな生きもの」に注目して新しい病理学を構想するということも起こらないまま、ヨーロッパの17世紀、18世紀は進行した。
③1870年代の終わり頃、パストゥールとコッホが、「細菌が伝染病の原因である」と証明することに成功した。「病原体」を「細菌」という「生きもの」に結びつける病理学を形成するためには、「無生物」の領野を中心とした思考方法から、「生物」という人間が経験的に古くから馴染んだ「日常的な形象」の水準まで科学的想像力を引き戻す作業が必要だった。パストゥールは「ワクチン」の概念を確立させ、コッホは「コッホの三原則」で細菌の生活環と種々の感染症との特異的な関係を結んでみせた。つまり、「物質」の領野での変容にかかわる知識と、「生きているもの」の領野で経験される現象とを結ぶ技術が、「病原体」を科学的思考のなかに定着させるために決定的な役割を果たした。彼らは、顕微鏡の使い方や証明実験の仕方、つまり物事のとらえ方や、因果関係の納得の仕方に影響を与えるための方法について大変な工夫を凝らした。特にコッホは、純粋培養の技法など、今日まで続く生物史研究の現場の基本的な光景を作り出した。
④19世紀半ば、進化論的思考が、遺伝子という生物学史にとって重要な物質的対象を獲得し、生命を探究する眼は分子のレベルの領野へと跳躍した。ここに、20世紀の生物学と物理学、化学の新たな接合が生じたその後に、私たちの視覚や思考は位置している。生命をどうとらえるべきかという問いは、不確定性や盲点の潜む空間が残っているかもしれない。その空間を思考する手掛かりに、ユクスキュルの「環世界論」がある。彼は、それぞれの生物に対して現象する「環世界」があるのだと論じた。これは、私たちに現れる世界は、「私たちにとっての世界」でしかないという視点を教える。であれば、「細菌」のありようもまた「私たちにとっての世界」にのみ成立する理解である。生きているものは、変わっていき、ときにまったく別のものであるかのように姿を変えていく。「病気」の向こう側には、まったく別の「生きているもの」の世界があるのかもしれない。このような世界に対して、私たちは決して容易に「理解した」と言うことはできない。
『病気の向こう側』の要約&本文解説
この文章は、細菌や病原体の発見から始まる人類の知の変遷をたどりながら、「私たちが生命や病気をどのように理解しているのか、あるいは理解できていないのか」という根本的な問題を問い直すものです。
科学の発展がもたらした「見える世界」は確かにありますが、筆者はそれだけでは見えてこない「生きているものの別の世界」もあるのではないかと主張しています。
1. 微生物の発見がもたらした世界観の変化
第1段落では、17世紀にレーウェンフックが顕微鏡で微生物を観察したことが紹介されています。
この発見は、それまで人間の五感では捉えられなかった「見えない世界」の存在を示し、「自然」や「生命」の概念を大きく揺るがしました。
科学はこの出発点から、「生命とは何か」「世界はどのように成り立っているか」という問いに対して、観察と実験をもとに探究する姿勢へと変化していきます。
2. 微生物と病原菌はイコールではなかった
第2段落では、「微生物の発見=病原体の発見」ではなかったことが強調されます。
レーウェンフックの観察は科学的には重要でしたが、当時の医学にはあまり影響を与えませんでした。
つまり、細菌を見つけたからといって、すぐにそれが病気の原因と理解されるわけではなかったのです。
3. パストゥールとコッホが病原体の存在を証明
第3段落では、19世紀後半にパストゥールやコッホが「細菌=病気の原因」であることを証明したことが語られています。
彼らは、見えない細菌を顕微鏡で観察し、その存在と病気との因果関係を論理的に示す方法を確立しました。
これにより、「病気」は目に見える敵(細菌)として捉えられるようになり、科学的思考や医療技術は飛躍的に進展しました。
4. 科学の視点はさらに分子の世界へ
第4段落では、進化論や遺伝子の発見によって、生命科学が分子や原子レベルの領域へと展開していったことが述べられています。これにより、私たちはますます「生命」をミクロな物質としてとらえるようになりました。
5. 「環世界」からの新たな視点
最後に紹介されるユクスキュルの「環世界論」は、すべての生物がそれぞれ独自の世界(環世界)をもって生きているという考え方です。つまり、私たちが観察し、「理解した」と思っている細菌や病気の姿は、あくまで「人間にとっての理解」に過ぎない可能性があるのです。
結論:筆者の主張は何か
筆者が本当に伝えたいのは次のような主張です。
「科学が病気や生命の本質を解明してきたように見えても、それはあくまで人間の視点にすぎず、生きものや病気には私たちの理解を超えた別のあり方があるかもしれない。だからこそ、私たちは“分かったつもり”になることを戒め、未知の存在に対して謙虚な視線を持つべきである。」
この文章は、科学の進歩をたどりながらも、「理解とは何か」「世界を本当に捉えられているのか」という哲学的な問いへと読者を導いています。
顕微鏡で見える世界、病原体の理論、遺伝子の研究、それらはいずれも重要ですが、最終的に筆者は「病気の向こう側」、つまり、科学ではまだ捉えきれない生命の別の側面があることを読者に気づかせようとしているのです。
『病気の向こう側』の意味調べノート
【誤認(ごにん)】⇒誤って別のものだと認識すること。
【執拗(しつよう)】⇒しつこくて、簡単にあきらめないさま。
【蔓延(まんえん)】⇒病気や悪いものが広がること。
【本態(ほんたい)】⇒本来の姿。
【推奨(すいしょう)】⇒あることをよいとして人にすすめること。
【原子(げんし)】⇒物質を構成する最小の単位。
【領野(りょうや)】⇒ある分野や領域。
【学知(がくち)】⇒学問的な知識や理解。物事を学んで理解すること。
【臨床(りんしょう)】⇒実際の患者を対象にして、治療すること。
【生活環(せいかつかん)】⇒生物が生きていく中でたどる発育や繁殖の過程。
【特異的関係(とくいてきかんけい)】⇒ある対象に特有で、他には見られない関係。
【因果関係(いんがかんけい)】⇒原因と結果とのつながり。
【体得(たいとく)】⇒実際に経験して深く身につけること。
【退行(たいこう)】⇒前の状態や未発達の段階に戻ること。
【分子(ぶんし)】⇒物質を構成する最小単位の一つで、原子が集まったもの。
【接合(せつごう)】⇒二つ以上のものがつながり合うこと。
【盲点(もうてん)】⇒注意が行き届かずに見落とされる部分。気づかない点。
【凝縮(ぎょうしゅく)】⇒一点に集中すること。
【固執(こしつ)】⇒ある考えや態度を頑固に守ること。
【固有(こゆう)】⇒そのものだけに特有で他にはないこと。
【阻害(そがい)】⇒ある働きや進行を妨げること。
『病気の向こう側』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①ザッキンが混入しないよう注意する。
②ショウジョウが急に悪化した。
③ケンマした面が鏡のように光る。
④ゼンモウの画家が個展を開いた。
⑤ラクノウ体験ツアーに参加した。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)微生物の発見により、すぐに病気の原因が明らかとなり、医学は急速に進展した。
(イ)病原体の存在は当初から広く受け入れられ、医学理論に大きな影響を与えた。
(ウ)科学は病気の仕組みを完全に解明したが、生物ごとの感じ方の違いは考慮していない。
(エ)病気の理解は科学の発展とともに深まったが、それは人間の視点に過ぎず限界がある。
まとめ
今回は、『病気の向こう側』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。