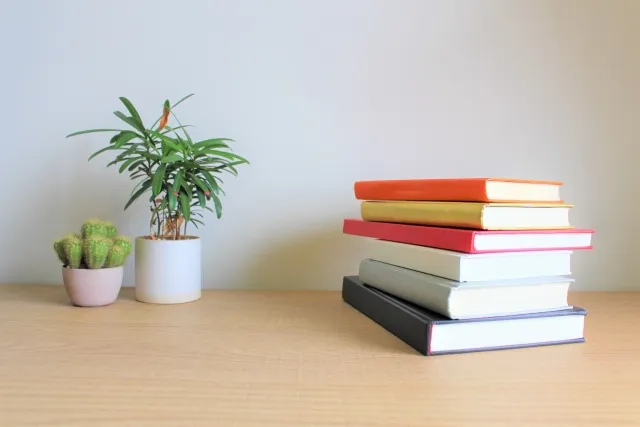『化物の進化』は、教科書・文学国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『化物の進化』のあらすじや要約、意味調べなどをまとめました。
『化物の進化』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①「化物」は、人間文化の進歩の道程で発明されたなかでも最も優れた傑作である。宗教や科学、芸術の世界にも「化物」は出入りしている。時代の推移に応じて化物の表象は変化するが、その心的内容は永久に同一である。自然界の不思議さは、原始人類にとっても二十世紀の科学者にとっても同じくらいに不思議である。昔の人はそれを「化物」と仮定して説明し、今はそれを科学で「分子原子電子」の存在を仮定することによって説明しようとしている。「化物」も「分子原子電子」も見た人はいない。両方とも実在ではないなら、この二つは共通なところもかなりあると言える。自然の怪物が分解して一半は科学へ、もう一半は宗教へ化物へと走って行ったと考えると、両者共に人間の創作であり芸術である。流派がちがうだけである。
②科学が進歩すると共に科学の真価が誤解され、買いかぶられた結果として、この頃は化物への人々の興味が希薄になった。今の子供らにとって、我々が子供のころに感じた化物への鋭い神秘の感じはなくなったように見える。「ゾッとする事」を知らないような豪傑が、仮に科学者になったとしたら、たいした仕事は出来そうもない。これは、かなりの問題ではないか。我々の少年時代の田舎には、化物を語る老人や友人がいた。化物は、当時の我々の世界にのんびりと生活していたのだ。子供心をドキドキさせたり、中学になって化物を物理的存在を信じなくなっても、化物の話は神秘的な存在、不可思議な世界へのあこがれを抱かせた。このような「化物教育」は、科学知識への興味を阻害することなく、かえってそれを鼓舞した。
③科学の目的は、化物を探し出すことである。だが、あらゆる化物は日本から追放された。あらゆる化物に関する事実をすべて迷信という言葉で抹殺することが科学の目的であり、手柄でもあるかのようだ。昔の化物は昔の人にはちゃんとした事実であったように、今の科学的事実が未来には事実でなくなるということもありえる。また、怪異を科学的に説明する事に対して反感を懐く人もいるようである。しかし、それは僻見であり誤解である。一通りの科学的説明で、その現象の神秘感は少しもなくなるわけではなく、本当の科学的研究は実はそこから始まる。すべてを知るのは「神様」だけだ。
④あらゆる化物を科学で説明しても、化物は決して退散も消滅もしない。ただ、化物の顔貌がだんだんに違ったものとなって現れるだけである。人間が進化するにつれて、化物も進化していく。しかし、いくら進化しても化物はやはり化物である。化物がないと思うのは、かえって本当の迷信である。宇宙は永久に怪異に充ちている。それを繙いて、その怪異に戦慄する心持ちをなくしてはならない。
『化物の進化』の要約&本文解説
筆者の主張を簡潔にまとめると、「化物とは、人間が自然の不思議さを理解しようとする心から生まれたものであり、科学が進歩してもその本質は変わらない」ということです。筆者は、「化物」を単なる迷信や空想ではなく、人間の想像力や探究心の象徴として捉えています。
第一段落では、化物は人間の創造物の中でも特に優れたものだと述べられています。昔の人が自然の不思議を「化物」と呼び、現代の人がそれを「分子」や「電子」と呼んで説明するのは、どちらも「見えないものを想像して世界を理解しようとする点」で同じだというのです。つまり、「化物」と「科学」は表現の形が違うだけで、どちらも人間の想像力による芸術だという見方です。
第二段落では、現代人が科学を信じすぎた結果、「化物」のような神秘的な感覚を失ってしまったことを問題視しています。筆者は、子どもの頃に「化物の話」にワクワクした経験こそ、未知への興味や探求心を育てる大切な「教育」だったと述べています。たとえば、「雷の正体を知りたい」「星はどうして光るのか」と思う気持ちは、まさに化物を怖がりながらも不思議に思う心と同じと言えます。
第三段落では、現代の科学が「化物」を迷信として切り捨てすぎていることを批判しています。本当の科学とは、化物を否定することではなく、「なぜそう見えるのか」を探ることから始まるのです。筆者は「すべてを知るのは神様だけだ」と述べ、科学にも限界があることを指摘しています。
そして第四段落では、「化物は決して消えない」と締めくくられます。人間が進化するように、化物も姿を変えて進化していきます。現代では「AI」や「宇宙人」などが新しい「化物」といえるかもしれません。筆者は、未知への畏れや感動を忘れないことが、人間にとって大切だと訴えています。
要するに、この作品のテーマは「科学と想像力の共存」です。化物とは、人間が世界の神秘に触れようとする心の表れであり、それは科学の原点でもあるのです。
『化物の進化』の意味調べノート
【正嫡子(せいちゃくし)】⇒正式な妻(正室)から生まれた男子で、家を継ぐ立場にある人。
【表象(ひょうしょう)】⇒心の中に思い浮かべた姿やイメージ。
【所業(しょぎょう)】⇒しわざ。行い。
【帰納(きのう)】⇒個々の具体的な事実から一般的な法則を導くこと。
【遺憾なく(いかんなく)】⇒十分に。心残りなく。
【省察(せいさつ)】⇒自分の考えや行動を深くかえりみること。
【示唆(しさ)】⇒それとなく知らせること。ほのめかすこと。
【一半(いっぱん)】⇒全体の半分。
【怪異(かいい)】⇒不思議なこと。常識では説明できないこと。
【天地の大道(てんちのだいどう)】⇒自然の道理。
【如実に(にょじつに)】⇒ありのままに。事実のとおりに。
【買いかぶる】⇒実際以上に高く評価する。
【世人(せじん)】⇒世間の人。一般の人。
【稀薄(きはく)】⇒うすいこと。気持ちや関心が弱いこと。
【滑稽味(こっけいみ)】⇒おかしさ。笑いを誘う感じ。
【存外(ぞんがい)】⇒思っていたよりも意外に。
【豪傑(ごうけつ)】⇒勇気や度胸のある人。
【郷里(きょうり)】⇒生まれ育った土地。ふるさと。
【晩酌(ばんしゃく)】⇒夕方や夜に酒を飲むこと。
【随意に(ずいいに)】⇒自分の思うままに。自由に。
【幻影(げんえい)】⇒まぼろしのような姿。
【衆に秀でる(しゅうにひいでる)】⇒多くの中で特にすぐれている。
【橋の袂(はしのたもと)】⇒橋のきわ。
【きわめて恰好な(かっこうな)】⇒非常にちょうどよい。都合がよい。
【舐る(ねぶる)】⇒なめる。舌で味わう。
【真砂(まさご)】⇒細かい砂。
【うら若い】⇒年が若く初々しい。
【不可思議(ふかしぎ)】⇒人の理解を超えた不思議なこと。
【憧憬(しょうけい)】⇒あこがれ。
【鼓吹(こすい)】⇒元気づけ、励ますこと。
【諸相(しょそう)】⇒さまざまなありさま。多様な姿。
【阻害(そがい)】⇒邪魔して妨げること。
【鼓舞(こぶ)】⇒元気づけて奮い立たせること。
【変痴奇論(へんちきろん)】⇒奇妙な説。へんてこりんな説。
【抹殺(まっさつ)】⇒完全に消し去ること。なかったことにすること。
【到底(とうてい)】⇒どうみても。どうしても。
【旋風(せんぷう)】⇒つむじ風。強い風。
【卑賎の者(ひせんのもの)】⇒身分や地位の低い人。
【腑に落ちない(ふにおちない)】⇒納得できない。理解できない。
【脚部(きゃくぶ)】⇒足の部分。
【玩具(がんぐ)】⇒おもちゃ。
【穿入(せんにゅう)】⇒穴をあけて入る。突き刺さって入る。
【下賤(げせん)】⇒身分が低いこと。下の立場の人。
【浅薄(せんぱく)】⇒考えが浅く、薄っぺらいこと。
【唯物論者(ゆいぶつろんしゃ)】⇒精神より物質を重視する考えを持つ人。
【僻見(へきけん)】⇒かたよった見方。
【何某(なにがし)】⇒だれそれ。なんとかという人。(特定の人の名をぼかしていう語。)
【遭遇(そうぐう)】⇒思いがけず出会うこと。
【退散(たいさん)】⇒逃げ去ること。立ち去ること。
【顔貌(がんぼう)】⇒顔つき。表情。
【面相(めんそう)】⇒顔のようす。顔立ち。
【際限がない(さいげんがない)】⇒終わりがない。きりがない。
【道程(どうてい)】⇒道のり。物事の進み具合。
【繙く(ひもとく)】⇒書物などを開いて読む。
『化物の進化』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①時代がスイイする。
②宇宙のシンピに感動する。
③集中をソガイする音。
④先生の言葉にコブされた。
⑤雨で人がタイサンした。
次のうち、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)化物は、科学が発達する以前の人々が作り出したものであり、科学の進歩によって完全に否定された。
(イ)化物は、科学の発展を妨げる迷信であり、人々はその存在を忘れるべきである。
(ウ)化物は、人間が自然の不思議を理解しようとする心から生まれたもので、科学もその想像力の表れである。
(エ)化物は、科学的事実と同じように実在するものであり、科学では説明できない存在である。
まとめ
今回は、『化物の進化』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。