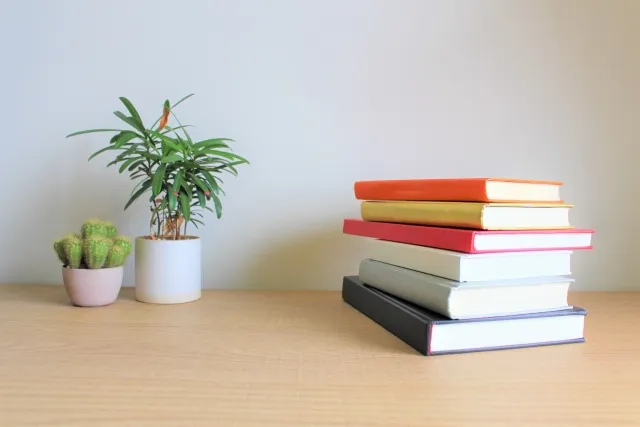『隠れん坊の精神史』は、教科書・文学国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと内容や主題が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『隠れん坊の精神史』のあらすじや要約、意味調べなどをまとめました。
『隠れん坊の精神史』のあらすじ
この文章は、大きく四つの段落に分けることができます。以下に、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①隠れん坊は、私たちに漠たる空白の体験を与える。仲間たち全員が隠れてしまうことは百も承知なのに、空白の広がりの中に、突然一人ぼっちの自分が放り出されたように感ずる。隠れん坊とは、急激な孤独の訪れ・一種の砂漠経験・社会の突然変異と凝縮された急転的時間の衝撃、といった一連の深刻な経験を、陽気な活動の底でぼんやりと確実に感じ取るようにできている遊戯である。つまり、隠れん坊は、こうした一連の経験を単純化し、細部の諸事情や諸感情を切り落として、原始的な模型玩具のごとき形にまで集約し、それ自身の中に埋め込んでいる遊戯なのである。では、隠れん坊の主題は何か。それは、「迷子の経験」「孤独の経験」「流刑の経験」「彷徨の経験」「旅の経験」である。
②「隠れん坊」は、「おとぎ話」の寸劇的翻案であり、身体の行為で集団的に再話した「おとぎ話」であり、遊戯の形で演じられた「おとぎ話」の実践版である。両者は、同じ主題が形態を全く異にして現れたものにほかならない。隠れん坊が模型化している一連の深刻な経験は、実際の事実世界における経験から写し取ったものではない。それは、すでに「おとぎ話」固有の構図の中で物語られ昇華されている経験からの写しである。私たちはすでに、「孤独な森の旅」「追放された彷徨」「眠りの後に起こる異変や別世界の事」などを、子供に向かって物語っている様々な「おとぎ話」の数々を思い起こしているはずである。おとぎ話が主題として語る経験は寸劇化されることにより、重苦しさから解き放たれたエキスとなって、知らない間に子供の心身の底深くに注ぎ込まれ蓄積されていく。将来訪れるであろう経験に対する胎盤が、抗体反応を起こすことなく形成されるのだ。
③おとぎ話の主題は、隠れん坊に翻案して遊ぶことによって、「聞く」ことと「演ずる」こと、という次元を異にした二つの通路を通して、心身の奥深くに受け入れられる。経験が、心身全体の行う物事との交渉である限り、心身一体の胎盤が備わっていないところには経験の育つ余地はまずない。おとぎ話と隠れん坊、話と遊戯の統合的対応が失われている状態を放置することは、経験の消滅を促進することにほかならない。
④おとぎ話と隠れん坊の世界が映写しているものは、人間の経験の「粋」であり、最も純粋な「形相」である。その世界性は、どんな作家の力も及ばない。おとぎ話と隠れん坊の作者は誰と問われれば、それは「歴史」であり「社会」と答えるべきだろう。人間の社会の歴史の中に普遍性をもって「作者」が住んでいて、それぞれの地域に特徴的な道具立てと仕草を持ちながら、同じ主題を同じ構図で展開しているのが、おとぎ話と遊戯の世界なのである。
『隠れん坊の精神史』の要約&本文解説
この文章で筆者が言いたいことは、「隠れん坊という遊びは、実は人間の深い経験を“模型”のように小さくした形で子どもに与える装置になっている」ということです。
単なる遊びに見えても、隠れん坊には「突然ひとりになる不安」「どこかへ追放されたような感覚」「自分ひとりで世界に向き合う体験」といった、人生で誰もが出会う根本的な経験の“エッセンス”が詰まっています。
しかし、子どもはそれを重苦しく感じません。なぜなら、隠れん坊はそれらの経験を単純化して、安全に模擬体験できるように“遊びの形”に変えているからです。
この考えをより理解するには「おとぎ話」と比較すると分かりやすいです。おとぎ話には、「森を旅する孤独」「追放」「眠りの後に異世界が開ける」など、人生の深いテーマが象徴的に表れています。隠れん坊は、そのおとぎ話を身体を使って演じる“実践版”なのです。
つまり、子どもは 「物語として聞く経験」と「遊びとして演じる経験」 の両方を通して、将来直面するであろう孤独や不安に対する“心の準備”をしていることになります。筆者が「胎盤」という比喩を使うのも、こうした人生経験を受け止める準備を静かに育てている、という意味です。
さらに筆者は、「おとぎ話や隠れん坊のような伝統的な遊びは、歴史と社会がつくりあげた普遍的文化であり、人間の経験のもっとも純粋な形を伝えるものだ」と強調します。もし現代人がこれらを忘れたり軽視したりすると、子どもが経験を受け止める力そのものが弱くなると警告しているのです。
『隠れん坊の精神史』の意味調べノート
【打って変わって(うってかわって)】⇒がらりと変わって。一変して
【漠たる(ばくたる)】⇒ひっそりと静まりかえって。
【遊戯(ゆうぎ)】⇒遊び。
【百も承知(ひゃくもしょうち)】⇒十分によく理解していること。
【路傍(ろぼう)】⇒道ばた。
【すっからかん】⇒中身が完全に空であること。
【急転(きゅうてん)】⇒状況が急に変化すること。
【突然変異(とつぜんへんい)】⇒遺伝子が急に変化する現象。
【凝縮(ぎょうしゅく)】⇒ぎゅっと詰まってまとまること。
【一連(いちれん)】⇒ひと続きの流れ。
【抽象画(ちゅうしょうが)】⇒具体物を描かず形や色で表現する絵。
【集約(しゅうやく)】⇒まとめて一つにすること。
【原物(げんぶつ)】⇒もとの実物。
【形質(けいしつ)】⇒生物の見た目や性質の特徴。
【核心(かくしん)】⇒物事の中心となる大事な部分。
【実物(じつぶつ)】⇒本物。現物。
【隔離(かくり)】⇒離れた所に分けておくこと。
【流刑(るけい)】⇒遠い地へ流される刑罰。
【彷徨(ほうこう)】⇒あてもなく、さまよい歩くこと。
【荒涼たる(こうりょうたる)】⇒荒れはててさびしい様子。
【瞑目(めいもく)】⇒目を閉じること。
【暗示(あんじ)】⇒それとなくほのめかすこと。
【同輩(どうはい)】⇒同じ仲間・同年代の人。
【おとぎ話】⇒子供に聞かせる昔話。
【寸劇(すんげき)】⇒短い劇。
【翻案(ほんあん)】⇒既存の作品を元に、その大筋を変えずに、人名や地域、時代背景などを変更して新しい作品を作ること。
【模倣(もほう)】⇒まねること。
【固有(こゆう)】⇒そのものだけが持つ性質。
【構図(こうず)】⇒物事全体の姿や形。
【昇華(しょうか)】⇒より高い段階へ発展させること。
【先ほど来(さきほどらい)】⇒先ほどから。
【煩雑(はんざつ)】⇒手間が多くて込み入っていること。
【細密描写(さいみつびょうしゃ)】⇒細かい所まで丁寧に描くこと。
【明快簡潔(めいかいかんけつ)】⇒わかりやすく無駄がないこと。
【即物性(そくぶつせい)】⇒対象を直接的・現実的に扱う性質。
【倍加(ばいか)】⇒倍に増やすこと。
【粘着的(ねんちゃくてき)】⇒ねばりつくようにまとわりつくさま。
【抑揚(よくよう)】⇒声や表現の強弱・高低。
【韻律(いんりつ)】⇒文章や詩のリズム。
【知覚(ちかく)】⇒感覚によって物事を感じ取ること。
【自生的(じせいてき)】⇒自分の中から自然に生じるさま。
【感得(かんとく)】⇒深く感じ取り理解すること。
【余地(よち)】⇒まだ残された空間・可能性。
【放置(ほうち)】⇒そのままにしておくこと。
【促進(そくしん)】⇒物事を早く進むようにうながすこと。
【通念(つうねん)】⇒一般に広く信じられている考え。
【抽出力(ちゅうしゅつりょく)】⇒必要なものを抜き出す力。
【杳として(ようとして)】⇒行方や様子がまったくわからないさま。
『隠れん坊の精神史』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①サクイのない自然な文だ。
②ショウシンして責任が増す。
③ネンチャク質で扱いにくい。
④コウショウは難航している。
⑤イシュウが部屋に漂う。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)おとぎ話や隠れん坊は、歴史的事実をそのまま描写するものである。
(イ)おとぎ話や隠れん坊は、現実の歴史や社会とは関係ない。
(ウ)おとぎ話や隠れん坊は、歴史や社会とは関係なく、自由に解釈できる。
(エ)おとぎ話や隠れん坊の作者は、人間社会の普遍性と結びついている。
まとめ
今回は、『隠れん坊の精神史』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。