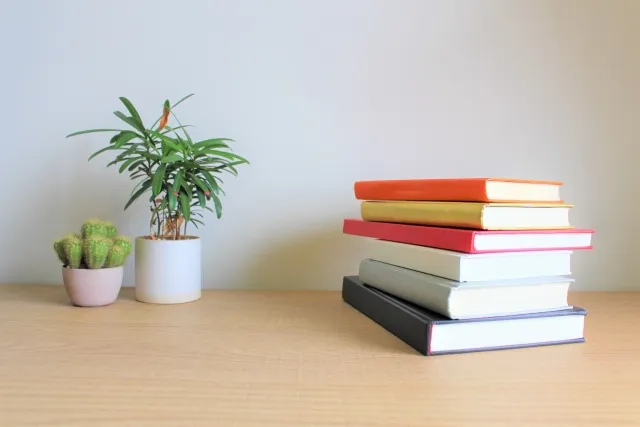『絵画は紙幣に憧れる』は、教科書・文学国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと作者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『絵画は紙幣に憧れる』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『絵画は紙幣に憧れる』のあらすじ
本文は、三つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①紙幣が人物画や風景画のように、図画の工夫に精を出すのは、紙幣が非実体的な信用に支えられているからこそである。つまり、紙幣自体が物質として価値を持つように見えなければならないからだ。紙幣は近代的であるからこそ、実効的には前近代的な絵画を擬装している。美術は、学校教育が可能となることによって、はじめて近代化された。知識と技芸の有機的な結合によって、誰でも色彩や造形に関する一定の判断と再現(創作)・反復(伝授)が可能になる次元では、絵画の署名には意味はない。
②しかし、実際にはその次元で創作される抽象絵画にさえ、画面の隅に署名が施される。それは、紙幣における事情と似たものがあるからだ。優れた美術作品が、誰にでも作れる再生産可能なものになってしまえば、一枚一枚の絵は固有の経済的な価値実体がないことが暴露されてしまう。署名が施されることで、二度と再現することができない一回性(オリジナリティー)を植えつける。つまり署名とは、近代的な絵画の真の意味での民主化に抵抗するための、一種の因襲的な「くさび」なのである。ただし、日本画は、絵の具の質などで価値が決まってくるところがあり、近代絵画と比べると依然として前近代的である。
③近代において、紙幣と絵画は一種の双子、もっと言えば共犯関係にある。紙幣は、美術作品を擬装することで価値の無根拠さを隠蔽し、反対に、絵画は大量の紙幣と交換されることで高尚さを演出し、みずからが一点物の紙幣にすぎないことを隠している。それぞれの物質としての実体的な価値の無さを相互の形式的な価値を利用し合って保証し合う関係になっているのだ。千円札を模写して一枚の絵画にすることで、紙幣と絵画の共犯性を見事に暴いた赤瀬川原平の作品のような、高度な次元で物質と形式が絡み合う非実体的な知のメカニズムこそが、アートの名に値する。
『絵画は紙幣に憧れる』の要約&本文解説
この文章が示している中心的なテーマは、「紙幣と絵画が、どちらも実体としての価値の弱さを補うために、形式的な装いによって価値を演出している」という点です。
筆者はまず、紙幣の外観に注目しています。紙幣は、本質的にはただの紙であり、物として特別な力を持つわけではありません。価値の根拠は、国家が保証する信用に支えられているにすぎません。
そのため、精巧な人物画や複雑な模様を施すことで、「特別なもの」であるように外観を整え、私たちが安心して使用できるよう工夫されているのです。
筆者は続いて、「絵画」についても同様の構造が見られると述べています。近代に入り、美術教育が普及したことで、多くの人が一定の表現力を身につけられるようになりました。その結果、作品の見た目だけでは価値の差が分かりにくくなりました。
そこで絵画には「署名」が添えられます。署名は、「この作品は作者固有のもので、二度と同じものが生まれない一点物です」という証明として機能します。これは、作品の価値を形式的に保証する仕組みであり、紙幣が外観によって価値を補強している状況とよく似ています。
筆者はさらに、紙幣と絵画が互いの形式を利用し合う関係を「共犯関係」と説明しています。紙幣は美術作品のような姿によって権威性をまとう一方で、絵画は市場で高額で取引されることで紙幣的な価値体系に結びつきます。両者は、それぞれの形式的価値を利用しながら、自らの価値の根拠の弱さを覆い隠しているのです。
この構造を鋭く明らかにした例として、赤瀬川原平による千円札の精密な模写作品が紹介されています。紙幣を絵画へと置き換えるこの試みは、紙幣と絵画が共有している価値の仕組みを可視化する象徴的な作品といえます。筆者は、このように価値のあり方そのものを問い直す姿勢こそ、アートが備えるべき重要な役割であると結論づけているのです。
『絵画は紙幣に憧れる』の意味調べノート
【手が込む】⇒作り方や方法が複雑である。
【根幹(こんかん)】⇒物事の中心となる大事な部分。
【産物(さんぶつ)】⇒ある原因や働きによって生み出された結果やもの。
【擬装(ぎそう)】⇒本当の姿を隠して別のもののように見せること。
【抽象絵画(ちゅうしょうかいが)】⇒具体的な形を描かず、抽象化した色や形の要素で表現する絵画。
【合理的(ごうりてき)】⇒無駄がなく、理論や道理に基づいているさま。
【革新的(かくしんてき)】⇒古い考えにとらわれず、新しく変革をもたらすさま。
【素地(そじ)】⇒物事が成り立つもとの性質や基盤。土台。
【王侯(おうこう)】⇒王や貴族など高い身分の人々。
【選別(せんべつ)】⇒多くの中から基準に沿って選び分けること。
【有機的(ゆうきてき)】⇒部分同士が関連し合い、全体として機能しているさま。
【結合(けつごう)】⇒二つ以上のものが結びつくこと。
【再生産(さいせいさん)】⇒同じ性質のものを繰り返し作り出すこと。
【因襲(いんしゅう)】⇒昔から続く古いならわし。(多くは悪い場合に使う。)
【隠蔽(いんぺい)】⇒見られて困る事実を隠すこと。
【非実体的(ひじったいてき)】⇒形や物質としての実体をもたないさま。
『絵画は紙幣に憧れる』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①物事のコンカンを見直す。
②ショメイが作品を左右する。
③カクシンには勇気が要る。
④イゼンとして課題が残る。
⑤バクロで真実が広がる。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)紙幣は偽造防止のため人物画が使われ、絵画の署名も作者確認の実務的役割を担う点で共通している。
(イ)紙幣は実体的価値を持つが、絵画は複製されやすいため署名で価値を補うだけで、両者に共通点はない。
(ウ)紙幣は信用の無根拠さを図像で覆い、絵画は署名で一回性を作る。両者は形式的価値で互いを補完する共犯関係にある。
(エ)紙幣も絵画も物質的価値が本質で、図像や署名は装飾にすぎないため、価値構造は大きく異なる。
まとめ
今回は、『絵画は紙幣に憧れる』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。