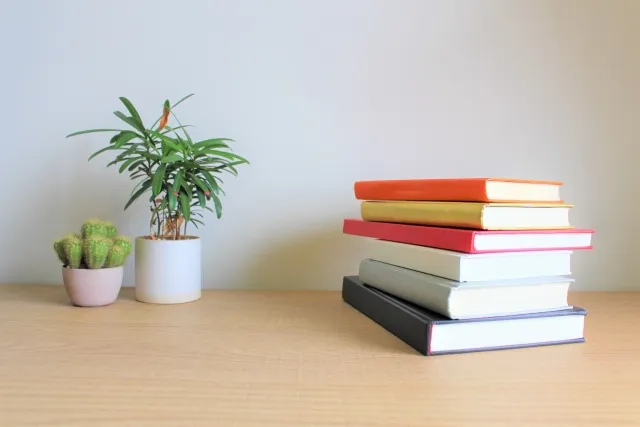『鞄』は、安部公房によって書かれた文学作品です。高校教科書・文学国語にも掲載されています。
ただ、本文を読むとその内容が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『鞄』の主題や考察、語句の意味などを解説しました。
『鞄』のあらすじ
本文は、大きく二つの段落に分けることができます。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①雨に濡れたままのくたびれた格好だが、どこか正直そうな青年が、半年も前に出した私の求人広告を見て事務所へ現れた。今になって応募してきたことに私は呆れるが、青年は「やはり駄目でしたか」とほっとしたように帰ろうとする。私は事情を知りたくなり青年を引き留めた。理由を問うと、青年は足元の大きな鞄を指して「この鞄のせいです」と言う。重すぎて坂や階段を登れず、行ける道が限られるため、結果的に私の会社に来るしかなかったというのだ。鞄を手放せばよいと言っても、青年は「いつでもやめられるからこそ、やめない」と奇妙な理屈を述べ、鞄の中身も明かそうとしない。不可解さを感じつつも、私は彼の事情を認め、採用を決める。ただし、事務所へ鞄を持ち込まないことを条件とした。青年は承諾し、下宿が決まればそこに置くと言って下見へ出かけた。自然な流れで、鞄だけが私の事務所に残されることになった。
②私は残された鞄を持ち上げてみた。重いが歩けないほどではない。試しに数歩進むと最初は問題ないが、やがて肩に負担がかかり、突然背骨に衝撃が走って全く歩けなくなる。そのとき、私はいつの間にか事務所を出て急な上り坂に立っていた。方向を変えれば歩けるが、事務所へ戻る道を思い浮かべても、坂や段差ばかりが邪魔をして道がつながらない。私は歩ける方向に進むしかなく、次第に自分がどこにいるのか分からなくなっていく。しかし、行き先は「鞄」が導いてくれるので不安は感じなかった。選べる道がない分、迷う必要もない。私は嫌になるほど自由だった。
『鞄』の考察&本文解説
安部公房の『鞄』で重要な役割を果たす大きな鞄は、単なる荷物ではありません。この「鞄」は、人間から主体性を奪うような存在の象徴として描かれています。
青年は「自分で鞄を持ち歩いている」と語りながら、実際には行き先を自分で決めていません。青年は、「鞄の重さが、ぼくの行き先を決めてしまう」と言います。つまり、選択しているようでいて、選ばされている状態なのです。
青年は「鞄を手放すなんて、あり得ない仮説だ」と断言します。この言葉から分かるのは、青年にとって鞄は絶対に必要な存在であり、なくてはならないものになっているということです。
しかし、その「必要性」は、本来自分が自由になることを妨げています。鞄に導かれるまま歩くことで、判断しなくて済むという気楽さは得られますが、そこには本当の自由はありません。
この作品が示すのは、人がこうした鞄のような存在に頼り切ってしまうと、主体的に考える力を失い、管理された社会の一員として生きることになるという危機です。
選択せずに済むことは、一見すると楽で自由のように感じられます。しかし、それはあくまで何かに操作された“見せかけの自由”であり、真の意味での自由ではないのです。
このような観点から、本作の主題は「人間の主体性を奪うものに身を委ねてしまう危険性」にあるといえます。そして「鞄」は、主体性を奪う力を持った管理社会の象徴として機能しています。
「鞄」は、一見すると奇妙な会話劇ですが、現代社会にもつながる深いテーマを含んでいます。私たちが無意識のうちに頼っている習慣、情報、制度、それらが“鞄”になっていないかを考えさせる作品なのです。
要点まとめ
- 「鞄」は「人間の主体性を奪う存在」の象徴として描かれている。
- 青年は行き先を自分で決めているように見えて、実際は鞄に選ばされている。
- 青年は判断を鞄に任せて気楽さを得ているが、それは本当の自由ではない。
- 鞄に依存する青年の姿は、「人が管理される社会」の危険性を示している。
- 作者は、私たちの身近にも主体性を奪う“鞄のような存在”がないかを問いかけている。
『鞄』の意味調べノート
【くたびれた】⇒使って古くなった。
【求人広告(きゅうじんこうこく)】⇒働く人を募集する広告。
【ぬけぬけと】⇒ずうずうしく。あつかましく。
【非常識(ひじょうしき)】⇒社会の常識に反しているさま。
【引き延ばした(ひきのばした)】⇒期限などを遅らせた。
【言わんばかり(いわんばかり)】⇒今にも言いそうな様子で。
【尻目(しりめ)】⇒問題にしないこと。無視すること。
【肩の荷をおろす(かたのにをおろす)】⇒責任や不安から解放される。
【唐突さ(とうとつさ)】⇒思いがけず急であるさま。
【引き返しかける(ひきかえしかける)】⇒帰りそうになる。
【はぐらかされた】⇒ごまかされ、話をそらされた。
【欠員(けついん)】⇒人が不足していること。
【新規(しんき)】⇒新しく始めること。
【補充(ほじゅう)】⇒足りないものを補うこと。
【矢先(やさき)】⇒ちょうどその時。
【考慮の余地がある(こうりょのよちがある)】⇒まだ検討できる部分がある。
【消去法(しょうきょほう)】⇒条件に合わない選択肢を消して絞り込む方法。
【思わせぶり(おもわせぶり)】⇒意味ありげで相手に期待を持たせる様子。
【口上(こうじょう)】⇒口で言うあいさつ。話しぶり。
【さりげなく】⇒自然に。何気なく。
【妙に(みょうに)】⇒不思議に。奇妙に。
【いささか】⇒少し。ちょっと。
【不似合い(ふにあい)】⇒つり合わないこと。ふさわしくない様子。
【さしかかる】⇒ちょうどその場所に来る。
【おのずから】⇒自然に。ひとりでに。
【制約(せいやく)】⇒行動や言論を制限する条件。
【気勢をそがれる(きせいをそがれる)】⇒やる気や勢いをくじかれる。
【かならずしも】⇒きっと~とは限らない。
【仮説(かせつ)】⇒仮に立てた説明や考え。
【自発的(じはつてき)】⇒自分から進んで物事を行うさま。
【振り出し(ふりだし)】⇒最初の状態。出発点。
【あらためて】⇒もう一度。再度。
【宅地造成(たくちぞうせい)】⇒住宅用の土地にする工事。
【あつかましい】⇒遠慮がなく、ずうずうしい。
【肌身離さず(はだみはなさず)】⇒いつも身につけて持っていること。
【腕っぷし(うでっぷし)】⇒腕の力。腕力。
【お手上げ(おてあげ)】⇒どうにもできず、あきらめること。
【年よりじみた(としよりじみた)】⇒年寄りのように見える。
【持ち込み(もちこみ)】⇒自分で物を持って入れること。
【下宿(げしゅく)】⇒お金を払って、他人の家の一部を借りて住むこと。
【下見(したみ)】⇒前もって見て調べること。
【なりゆき】⇒物事が移り変わっていくさま。また、その結果。
【なんということもなしに】⇒特に理由もなく。
【腕にこたえる(うでにこたえる)】⇒腕が疲れるほど負担になる。
【方向転換(ほうこうてんかん)】⇒進む方向や方針を変えること。
【寸断(すんだん)】⇒細かくずたずたに切ること。
【やむを得ず(やむをえず)】⇒仕方なく。
【ためらう】⇒決断できず迷う。
『鞄』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①部屋の空気がカンソウしている。
②ムダな努力はやめなさい。
③違法品がオウシュウされた。
④仕事を終え、キトにつく。
⑤友人をショウカイされた。
次のうち、本文の内容を表したものとして 最も適切なもの を選びなさい。
(ア)青年は鞄の処分を相談しに来たが、その件は採用に直接つながらなかった。
(イ)私は鞄を持って歩けたことで、青年の話が誇張だと判断し採用を控えた。
(ウ)私は青年の鞄を持つと軽かったため、説明が不自然だとして採用を見送った。
(エ)青年は重い鞄で通れる道が限られ、結果として会社にたどり着いたと説明した。
まとめ
今回は、『鞄』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。