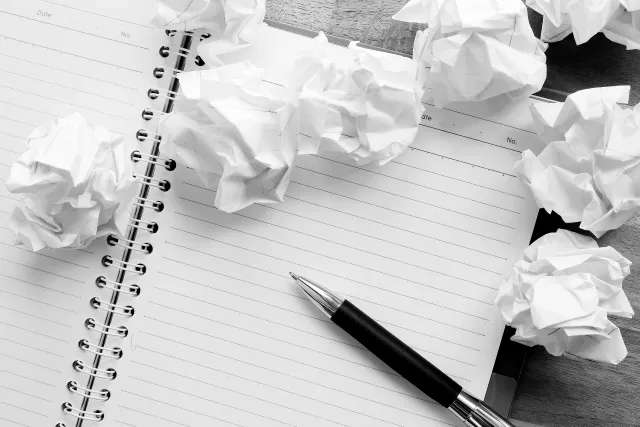
『捨てない女』は、教科書・文学国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むとその内容が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『捨てない女』のあらすじや要約、テスト問題などを解説しました。
『捨てない女』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①今までは、私は書き損じた原稿用紙を束にして「もえるゴミ」として捨てていた。わたしは「燃えるゴミ」という言い方が、捨てられる者の燃える情熱を表しているようで、なんだか好きだった。だが、処理費を払ってゴミを引き取ってもらうようになってからは、もう気軽に小説の筋を変えることもできなくなった。わたしは「処理」という言葉が好きになれない。
②ゴミばかり出て小説ははかどらない。家具屋の大売り出しの広告もゴミになる。その写真を切り抜いて遊んでいたが、ひとりで遊んでいてもつまらないので、隣の家の姉妹を呼び入れて遊んだ。これでゴミがオモチャになったとひそかに喜んでいたところ、母親が子供を迎えに来た。母親からもらい物の箱を手渡され、私はしまったと思ったがもう遅かった。このお菓子もよくみるとあさってでゴミになる。わたしは、もらい物のおせんべいを包んでいた包装紙を切り、一枚一枚に文章を書いて、おせんべいを入れていたビニール袋に入れた。そして、缶のふたを閉めて出版社に持っていこうとした。そうすれば、それはゴミではなく立派な小説なのだから、まさか受け取るのが嫌だとは言わないだろう。
③料理もゴミが大切で、作りながら出てくる生ごみをテーブルに並べていって、そのゴミの姿が美しければ料理はおいしい。材料の品数が少なく栄養が片寄っていれば、ゴミは味気ない。わたしもワープロを使って小説を書けばゴミは出ないが、ゴミが出ないと、物を考え続けることができない。
④ゴミの処理費が払えないので、法律違反だが、昨日、書き損じを裏庭でこっそりと燃やした。ゴミはなくなったが、後味が悪かった。焼かれた紙はあの世に行くという話を聞いたことがある。死者たちは、わたしの書き損じた原稿をあの世で読むのだろうか。そんな失敗作は読んでもらいたくないので、後から完成した本を一冊燃やして届けようかと思った。書き損じた原稿用紙を塩と酢を入れた湯の中で煮ると、文字が湯の中に溶けだして原稿用紙はまた白くなるらしい。それをやってみた私は、湯の中で浮かび上がってきた文字をおたまですくって裏庭に捨てた。くしゃくしゃになった文字たちは土の中へ染み込んで消えていった。春が来て、ここに種子をまいたらどんな花が咲くのだろう。
『捨てない女』の本文解説
『捨てない女』で筆者が伝えたい事は、「捨てることの中にも意味がある」という発想の転換です。
主人公の「わたし」は、書き損じた原稿用紙や生活の中で出る「ゴミ」と向き合う中で、ものの価値や命の循環について考えていきます。単なる「ゴミ」も、見方を変えれば創作の材料になったり、新しい命を生む存在になったりするというのが、筆者の核心的な主張です。
たとえば、第一段落では、「燃えるゴミ」という言葉に「燃える情熱」を感じ取っています。普通なら嫌われる「ゴミ」にも、まだ何かを生み出す力があると見る点が特徴的です。
また、第二段落では、ゴミで遊んだり、小説の素材に変えたりする姿が描かれています。これは、価値のないと思われたものを再利用し、創造の源に変える行為です。つまり「捨てない」という行為は、創造とつながっているのです。
第三段落では、料理中に出る生ごみにも「美しさ」を見出しています。ゴミの姿が整っていれば料理はおいしい、という考えは、物事の「過程」そのものに価値を見いだす姿勢を示しています。作品づくりや人生においても、「完成品だけでなく、その途中にある失敗や無駄こそが大切である」という筆者の思いが表れています。
第四段落では、「ゴミを燃やす罪悪感」や、「書き損じた文字が土に染み込み、花になるかもしれない」という想像が描かれます。これは、失敗や不要なものも、時間をかけて新しい命に変わるという希望の象徴でもあります。つまり筆者は、「すぐに捨てずに、もう一度見つめ直すことで、新しい価値が生まれる」と読者に教えているのです。
この作品は、物を簡単に捨ててしまう現代社会への問いかけでもあります。私たちが「不要」と決めつけてしまうものも、見方を変えれば「再び生まれ変わる可能性」を持っています。筆者は、ゴミに向けるまなざしを通して、人間の創造力や命の循環を静かに描き出しているのです。
『捨てない女』の意味調べノート
【廃棄物(はいきぶつ)】⇒不要になり、捨てられる物。
【書き損じる(かきそんじる)】⇒書きそこなう。書くときに間違える。
【排泄物(はいせつぶつ)】⇒体内から排出される不要物。尿や便など。
【味気ない(あじけない)】⇒おもしろみや魅力がない。つまらない。
【着想(ちゃくそう)】⇒考えやアイデアを思いつくこと。
【つらみ】⇒つらいこと。苦しいさま。
【愚痴(ぐち)】⇒不満や文句をこぼすこと。
【はかどらない】⇒仕事や作業が思うように進まない。
【粗大ゴミ(そだいごみ)】⇒大きくて普通のゴミとしては捨てられない不要物。家具など。
【賞味期限(しょうみきげん)】⇒おいしく食べられる期限。安全性ではなく品質の目安。
【屑(くず)】⇒値打ちがなく役に立たないもの。
【断片(だんぺん)】⇒全体の一部分。切れ端。
【醍醐味(だいごみ)】⇒そのものの持つ深い味わい。本当の楽しさや魅力。
【天女の帯(てんにょのおび)】⇒「天女」とは「天上の世界に住むと言われる美しい女性」のこと。ここでは、生ごみのにんじんの皮が横たわる様子をたとえている。
【再編成(さいへんせい)】⇒もう一度組み立て直すこと。編成し直すこと。
【後味(あとあじ)】⇒物事が終わった後に残る感じや印象。
『捨てない女』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①トウコウした写真が話題になる。
②ソソウをしてしまい、平謝りした。
③彼は上司にゲイゴウして評価を得た。
④父のボンサイが玄関に飾られている。
⑤彼は事件のカチュウに巻き込まれた。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)筆者は、ゴミの処理費を払うようになってから、むしろ気軽に原稿を書き直せるようになった。
(イ)筆者は、ゴミを単なる不要物ではなく、創作や生活に関わる大切な存在としてとらえている。
(ウ)筆者は、ワープロで書けば効率が上がるので、できるだけ紙の原稿を使わないようにしている。
(エ)筆者は、ゴミを燃やすときのにおいが好きで、よく裏庭で原稿を燃やしている。
まとめ
今回は、『捨てない女』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。