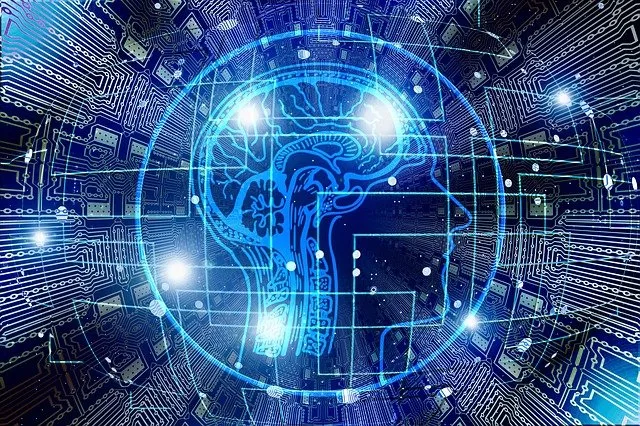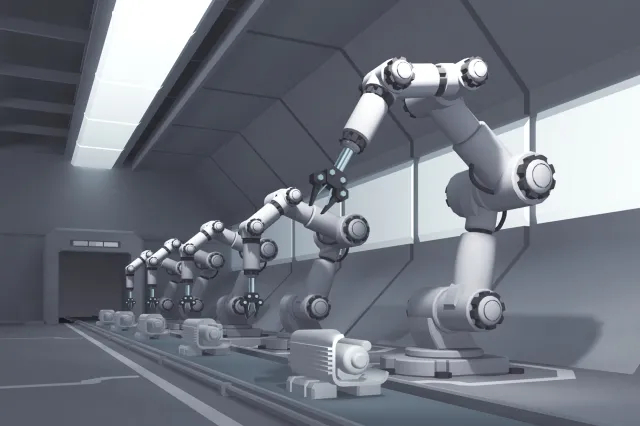
『科学技術は暴走しているのか』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、本文のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『科学技術は暴走しているのか』のあらすじ
この文章は、5つの段落から構成されています。以下に、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①人工知能(AI)やロボット技術の発展は、暗い未来像を予想する人もいる。AIが全人類を上回る知能を獲得する技術特異点が到来するという予想や、人類が富裕支配層と被支配層に二分されるという予想もある。生命や人間の側を操作する技術も、人間の倫理観を置き去りにして発展している。
②科学技術は大昔からずっと暴走してきた。農耕は、栄養状態の改善をもたらしたが、人々が密集して生活することで感染症が拡大した。武器や運搬、移動技術なども戦争や事故といったデメリットをもたらした。技術には負の側面が常につきまとうのだ。AIやロボットなどの先端技術が人類社会に与える影響も、一部は予想がつく。
③AIやロボットなどの先端技術が過去の技術革新とは異なる点もある。第一に、機械から人へ情報発信する「自立化」、第二に、メディア技術や通信技術などの「(外部)環境化」、第三に、マイクロマシーンや人工臓器などの「内部化」、第四に、人の代わりに仕事をする「代理性」である。これらは従来の技術にはほとんど見られなかったか、見られたとしてもごくわずかだった。言い換えると、もともと人と共生体を形成していた人工物は、ここに来て人体との一体化の度合いが高くなってきたということだ。
④人間の新しい技術に対するイメージは、常にアンビバレントだった。昨今の自律的技術や生命操作技術に関しては、四つの新しい特性ゆえに、ことにその度合いが強いように思う。
⑤古来日本では、人工物と人の距離が近く、ロボットなどの技術に対しても西洋社会よりも友好的だった。その背景には、アニミズム的心性があると指摘する学者もいる。フィクションの世界で描かれるロボットの姿も、日本では友好的であったり、人間の完全な道具であるものが多い。これは、西洋とは対照的である。人と人工物の距離が近いという日本の文化や社会の特性は、AIやロボット技術との共存を目指す際に、一つの拠り所となる。豊かな社会の実現のため、AIやロボットをてなづけ、飼いならさねばならない。
『科学技術は暴走しているのか』の要約&本文解説
本文は、「科学技術は暴走しているのか」という問いを軸に、人間と技術の関わりを考察しています。
筆者の主張は、「科学技術には常に負の側面があり、確かに暴走しているようにも見えるが、人類はそれを制御し、共存の道を探らねばならない」ということです。
まず、冒頭では、AIやロボットの進歩が人類を不安にさせると述べられています。AIが人間を超える「技術的特異点」が来る、富の格差が拡大するなど、暗い未来像が語られるのはよくあることです。
また、遺伝子操作や生命技術など、人間そのものに介入する技術は倫理観を置き去りにして進んでいるという問題点もあります。
次に筆者は、科学技術の「暴走」は今に始まったことではないと指摘します。歴史上、農耕が進めば感染症が広がり、武器や交通の発達は戦争や事故を生みました。
このように、科学技術は常に利点と欠点をあわせ持ってきたのです。AIやロボットもその延長線上にあると考えられます。
しかし、AIやロボットは従来の技術と異なる特徴も持っています。自ら情報を発信する「自立化」、環境と一体化する「環境化」、人体に入り込む「内部化」、人の仕事を代行する「代理性」がそれです。
これらの性質によって、人と技術の一体化が今まで以上に進みつつあります。そのため、人々の心には強い期待と恐怖、つまりアンビバレントな感情が生まれるのです。
最終的に筆者は、日本社会の特性に注目します。日本では古くから人工物と人の距離が近く、ロボットも友好的に描かれることが多いとされます。これは西洋とは対照的であり、AIやロボットとの共存を考えるうえで重要な背景になります。
つまり、私たちは恐怖に支配されるのではなく、文化的特性を活かしながら技術を「飼いならす」ことが必要だ、というのが筆者の結論です。
この文章のテーマは、「科学技術の進歩は危険を伴うが、人間はそれを乗り越え、共存の方法を模索すべきだ」という点にあります。
受験勉強にたとえるなら、スマホやAI教材は便利ですが、依存すれば集中力を失います。大事なのは、それをうまくコントロールし、道具として生かす姿勢なのです。
『科学技術は暴走しているのか』の意味調べノート
【簿記(ぼき)】⇒企業の経済活動を帳簿に記録し、管理する技術。
【冒涜(ぼうとく)】⇒神聖なものや尊いものを汚すこと。
【農耕(のうこう)】⇒田畑を耕し、農作物を栽培すること。
【茫漠(ぼうばく)】⇒広々として果てしないさま。内容がはっきりしないさま。
【恩恵(おんけい)】⇒ありがたい恵みや利益。
【類推(るいすい)】⇒似ている点をもとにして、他の事柄を推し量ること。
【帰結(きけつ)】⇒最終的に行き着く結末や結果。
【時報(じほう)】⇒時刻を知らせること。または、その放送。
【喪失(そうしつ)】⇒大切なものを失うこと。
【象徴(しょうちょう)】⇒抽象的な事柄を、具体的な物で表すこと。
【普及(ふきゅう)】⇒広く一般に行き渡ること。
【傑作(けっさく)】⇒非常によくできた作品。
【喝破(かっぱ)】⇒間違った説を排し、真実を説き明かすこと。
【災厄(さいやく)】⇒災難や不幸な出来事。
【余地(よち)】⇒まだ残っている可能性やゆとり。
【戯曲(ぎきょく)】⇒演劇用に書かれた脚本。
【厳然(げんぜん)】⇒おごそかで動かしがたいさま。
【拠り所(よりどころ)】⇒行動や判断の根拠となるもの。支え。
【翻弄(ほんろう)】⇒思いのままに操ること。振り回すこと。
『科学技術は暴走しているのか』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①カクトクした技術を活かす。
②ミッシュウした人々で賑わう。
③新しい制度がフキュウする。
④先生が誤りをシテキした。
⑤必要な情報をチュウシュツする。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)科学技術は常に人間に利益だけをもたらしてきたため、暴走と呼ばれることはない。
(イ)AIやロボット技術は、従来の技術と同じ性質を持ち、人間との関係性に特別な変化はない。
(ウ)科学技術には常に負の側面があり、AIやロボットは「自立化」「環境化」「内部化」「代理性」という新しい特性を示す。
(エ)西洋社会と比べ、日本では人工物に不信感が強く、ロボットは脅威として描かれることが多い。
まとめ
今回は、『科学技術は暴走しているのか』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。