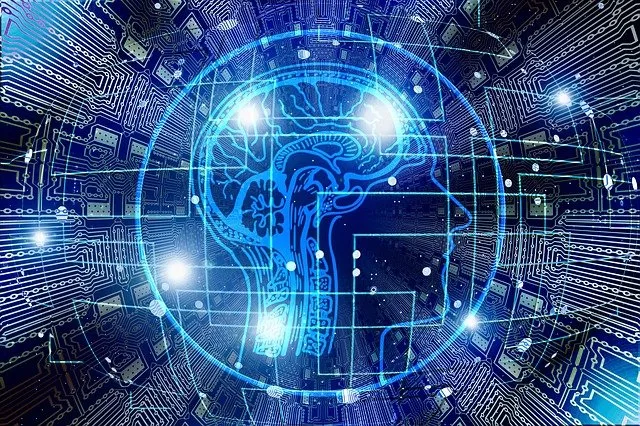『枯野抄(かれのしょう)』は、芥川龍之介による文学作品です。高校の教科書・文学国語にも取り上げられています。
ただ、本文を読むと内容が分かりにくいと感じる部分も多いです。そこで今回は、『枯野抄』のあらすじや要約、登場人物の心情などを解説しました。
『枯野抄』のあらすじ
この作品は、背景や登場人物の描写によって八つの段落に分けることができます。以下に、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介します。
①芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」の成立について記されている『花屋日記』からの引用を置く。元禄七年十月十二日の午後、大阪の町は薄明るく静まり返っていた。
②このとき、御堂前南久太郎町の花屋仁左衛門の裏座敷で、五十一歳の松尾芭蕉が、門下の者たちに囲まれながら静かに息を引き取ろうとしていた。彼は昏睡状態で、その目は「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる。」という辞世の句のごとく、とりとめもなく遠い所を見やっていた。
③やがて医者の木節に促され、末期の水をとることになり、門弟一同は、緊張と一種の弛緩に包まれた。其角は、師の臨終の姿に堪え難い嫌悪を覚え、ほとんど何の悲しみもなかった。
④其角に続いて水をとった去来は、満足と悔恨が入り混じった心境にあった。一身をあげて師匠の介抱に没頭した無意識の満足と、それを卑しく思う気持ちという矛盾を内心に抱えて興奮し、落ち着かないまま羽根楊枝を手にした。
⑤次に老実な丈草に順番がまわると、正秀はまるで不気味な笑い声のようにも聞こえる凄絶な慟哭をあふれさせた。そこに一種の誇張を感じつつ、乙州も嗚咽の声を発した。
⑥支考は、いつもながらに横風で、名聞、利害、自分一身の興味打算など、師匠の死とは無関係なことを考えていた。師匠の死よりも、師匠を失う自分自身を悼むという、自分たちを非難できないのだという厭世的な感慨に沈むことを得意とする彼は、冷然とした態度をとった。
⑦惟然坊は、死別の悲しさとは縁のない死そのものへの恐怖に襲われた。次に亡くなるのは自分かもしれないと思い、師匠の顔を正視できなかった。
⑧門弟たちが末期の水をとる間に、丈草は悲しみと共に安らかな心持ちを感じた。それは芭蕉の人格的圧力からの解放の喜びだった。丈草はかすかな笑みを浮かべて芭蕉に礼拝し、こうして芭蕉は最後のときを迎えたのだった。
『枯野抄』の要約&本文解説
『枯野抄』は、芥川龍之介が、俳聖・松尾芭蕉の最期をめぐる弟子たちの姿を描いた作品です。
中心にあるのは、芭蕉が詠んだ辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」と、それを取り巻く門弟たちの心の揺れです。作者は芭蕉本人よりも、むしろ弟子たちの心情に焦点を当てて描き、別れをめぐる人間の多様な感情を浮き彫りにしています。
物語の流れを追うと、まず弟子の其角は、師の臨終に直面しながらも「嫌悪」を感じ、深い悲しみを覚えませんでした。次に水をとった去来は、師の介抱に尽くした充実感と、その行為を卑しいと思う後悔の気持ちが入り混じり、複雑な感情を抱きます。
さらに丈草や正秀、乙州らの泣き方には、悲嘆と同時に誇張や演技めいた要素が見られます。支考は冷ややかに計算高い思索にふけり、惟然坊は「別れの悲しみ」よりも「死への恐怖」にとらわれました。そして最後に丈草は、芭蕉の人間的な圧力から解放される安らぎを覚えるのです。
ここから見えてくるテーマは、師を失う場面においても、人は必ずしも「純粋な悲しみ」だけを抱くわけではない、ということです。
人間は状況に応じて、「嫌悪・満足・虚栄・恐怖・解放感」といった多様な感情を同時に抱きます。つまり、人生の終わりの場面は「生きている人間の心の鏡」でもあるのです。
作者は、最期を美化するのではなく、むしろ人間の弱さや矛盾を直視することで、人間存在の真実に迫ろうとしました。
本作の最大のポイントは、「芭蕉の臨終」そのものよりも「弟子たちの多様な心情」が描かれている点です。たとえば、現代でも大切な人との別れに直面したとき、人は必ずしも悲しみだけを感じるわけではありません。
安堵や苛立ち、あるいは現実的な損得を考えることさえあるでしょう。『枯野抄』は、そうした人間の複雑な心のあり方を鮮やかに描いた作品だといえます。
『枯野抄』のまとめポイント
作者:芥川龍之介(大正時代の作家)
内容:松尾芭蕉の最期の様子を、弟子たちの心情を通して描いた作品
作品名の意味:
- 枯野=草木の枯れた野原、つまり人生の終わり・老い・死の象徴
- 抄=出来事や事柄を抜き出してまとめたもの
- 枯野抄=「芭蕉の晩年や最期の場面を選んで描いた作品」というニュアンス
中心となる描写:芭蕉の臨終の場面と弟子たちの心情
- 其角⇒嫌悪、悲しみはほとんどなし
- 去来⇒満足と悔恨の混ざった心境
- 正秀・乙州⇒慟哭、感情の誇張あり
- 支考⇒冷然、打算的思考
- 惟然坊⇒死への不安、自己への恐怖
- 丈草⇒悲しみと同時に解放・安らぎを感じる
主題と結論:
- 最期の場面は純粋な悲しみだけではなく、人間の多様な感情を映し出す
- 個々の生き方・考え方が、人生の終わり=「枯野」を象徴的に表現している
- 師の最期は人間存在の真実や矛盾を示す「心の鏡」となる
『枯野抄』のテスト対策問題
次のうち、本文の内容として最も適切なものはどれか?
(ア)芭蕉の最期に直面した弟子たちは、全員が同じように深い悲しみを抱き、その悲しみを互いに共有していた。
(イ)芭蕉の臨終に際して、弟子たちは各自異なる心の動きを示し、悲しみだけでなく嫌悪、安堵、悔恨、恐怖など、複雑な感情を同時に抱いた。
(ウ)弟子たちは芭蕉の最期に接しながらも、名誉や打算など個人的な利害を優先し、感情はほとんど表に出さなかった。
(エ)芭蕉の辞世の句の意味や最期の状況よりも、医師や周囲の描写に重点が置かれ、弟子たちの心情は控えめに描かれている。
まとめ
今回は、『枯野抄』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。なお、本文中の重要語句については以下の記事でまとめています。