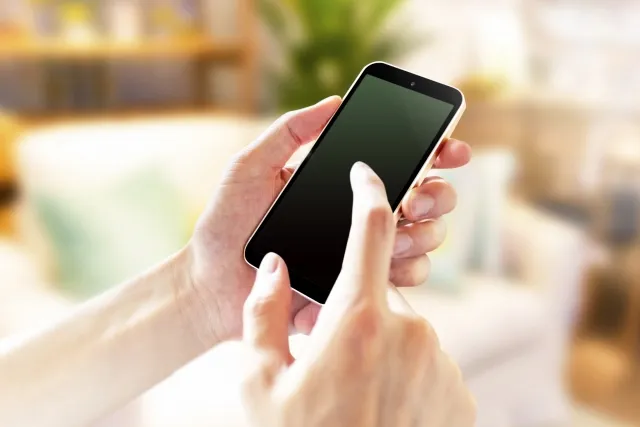
『SNSと意見の分極化』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『SNSと意見の分極化』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『SNSと意見の分極化』のあらすじ
本文は、五つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①ここ二十年の情報環境の変化は、インターネットの普及である。SNSは、多くの人に対して情報を発信できる。こうした中では、正しい情報だけでなく誤情報や偽情報も横行する。加えて、SNSは世論の分極化を助長して人々の対立を深めているという議論も耳にする。これは事実だろうか。
②誤った情報は、正しい情報よりもずっと速く広く拡散しやすいことがわかっている。誤情報はこれまで目に触れていない真新しさがあるので、でっちあげられやすく、人々の関心を引きやすい。それは、動機付けられた推論や記憶が都合のいい方向にゆがむ確証バイアスが影響している。確認が不十分な情報をSNSに投稿すれば、それは一人歩きするのだ。
③心理学の実験では、集団分極化と呼ばれるものがある。それは、賛否が分かれる問題について、何人かで話し合いをすると、その場で多数意見に引きずられる形で結論が極端になりやすいという現象である。集団分極化は、いろいろな理由で生じる。説得力のある議論の積み重ねによる極論化(議論の積み重ね)、皆に理想的と思われる意見への接近(理想化)、自分だけが責任を負わなくてよい状況(責任の回避)などである。
④分極化に影響する別の要因としては、「沈黙の螺旋」が挙げられる。人々は自分が多数派だと思えば発言する。また、多数派の意見には同調しやすい。一方で、少数派だと思うと発言しない傾向がある。すると、多数派は似通った意見を耳にしやすいからどんどん発言するが、少数派はますます発言を控えることになる。その結果、多数派の意見がさらに強まっていく。これが、沈黙の螺旋理論である。
⑤誤情報への対策はどうすればいいだろうか。極端化した意見を持つ人々に対して、それを訂正する情報を与えるという場合は、「受け手が信頼している情報源を与える」「具体的なデータや画像を示す」などの対応が有効である。フェイクニュースに影響されることを防ぐには、情報の提供者であるポータルサイトが、怪しい情報を明示し、マスコミや独立した機関がファクトチェックをする必要がある。また、事実か虚偽かを検証していく構えを持ち、自分の判断にはバイアスがあり得るという自覚が重要である。フェイクニュースへの対抗は、いろいろな方向から構築することが可能なので、どのような手法が有効かを今後はさらに検証していく必要がある。
『SNSと意見の分極化』の要約&本文解説
筆者の主張
筆者の中心的な主張は、 「SNSは誤情報の拡散や意見の分極化を引き起こし、人々の対立を深めやすい。だからこそ、その問題にどう対処するかが重要である」 という点です。
つまり筆者は、単に「SNSは便利だ」という話ではなく、
- 誤った情報が広まりやすい仕組み
- 意見が極端に分かれやすくなる心理的・社会的な要因
- それにどう対応すべきか
を整理して説明しているのです。
2. 各段落の意味を簡単に整理
① 問題提起
インターネットとSNSが普及した結果、正しい情報も誤情報も簡単に広がるようになった。さらに、「SNSは人々の意見を分裂させているのでは?」という問いを読者に投げかけている。
② 誤情報が広がる理由
誤情報は、目新しく関心を引くため正しい情報よりも速く広まる。人間は自分に都合のいい情報を信じやすい(確証バイアス)ので、検証不足のまま拡散されやすい。
③ 集団分極化の心理
人が集団で議論すると、結論が極端になりやすい。これは「説得力のある意見の積み重ね」「理想的に見える意見への同調」「責任を分散できる安心感」などの心理が働くためである。
④ 沈黙の螺旋の影響
少数派は発言を控え、多数派は発言を続けるので、多数派の意見がさらに強くなる。これも分極化を進める原因である。
⑤ 解決策・対処法
誤情報への対抗策として、
- 信頼できる情報源を使う
- 具体的なデータや証拠を示す
- ポータルサイトやマスコミがファクトチェックする
- 個人も「自分にバイアスがある」と意識する
などを挙げている。
3. 筆者の最終的なメッセージ
筆者は、
- SNSの仕組みや人間の心理が「誤情報の拡散」や「意見の極端化」を後押ししている
- しかし、対処法は存在し、今後さらに有効な方法を検証していく必要がある
という立場をとっています。
つまり、 「SNSの問題点を理解し、社会や個人が多面的に対応することが重要だ」 というのが結論です。
『SNSと意見の分極化』の意味調べノート
【普及(ふきゅう)】⇒広く行き渡ること。
【横行(おうこう)】⇒良くないものが盛んにはびこること。
【拡散(かくさん)】⇒広がり散らばること。
【自明(じめい)】⇒説明するまでもなく明らかなこと。
【目新しさ(めあたらしさ)】⇒今までにない新しさ。
【一人歩き(ひとりあるき)】⇒本来の意味から離れて、独立して広まること。
【目に留まる(めにとまる)】⇒注意が引きつけられて印象に残る。
【拒絶(きょぜつ)】⇒強く断ること。
【回避(かいひ)】⇒避けること。
【拍車がかかる(はくしゃがかかる)】⇒物事の進行が一段と強まること。
【露骨(ろこつ)】⇒ありのままをむき出しにするさま。
【提唱(ていしょう)】⇒考えや主張を示して、広めようとすること。
【促進(そくしん)】⇒物事を進めるように働きかけること。
【虚偽(きょぎ)】⇒事実でないこと。
『SNSと意見の分極化』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①シテキを受けて考え直す。
②相手からキョゼツされる。
③危険をカイヒする行動。
④販売活動をソクシンする。
⑤シエンを得て挑戦できた。
次の内、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)SNSでは正しい情報が誤情報よりも早く広まり、人々の意見は中立的にまとまりやすいとされる。
(イ)SNSでは誤情報が広がりやすく、集団分極化や沈黙の螺旋によって人々の意見が極端化する傾向がある。
(ウ)誤情報は人々にとって関心が薄いため、SNS上ではあまり影響を及ぼさない。
(エ)フェイクニュースは完全に防ぐことが可能であり、個人の判断に頼る必要はない。
まとめ
今回は、『SNSと意見の分極化』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







