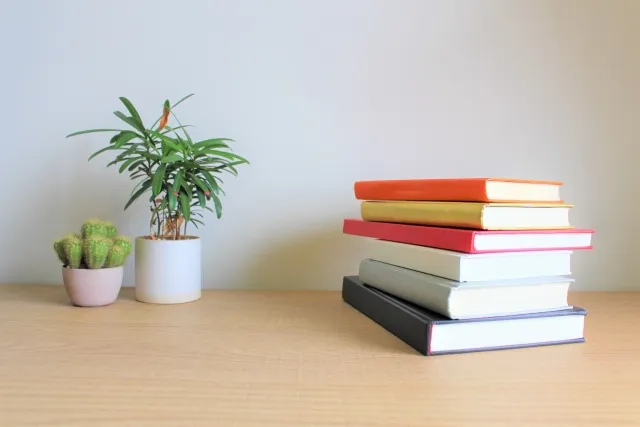『過剰性と稀少性』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『過剰性と稀少性』のあらすじ
本文は、6つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを紹介していきます。
①貨幣は、生活の中において有用性という経済原理に服さないものである。それは、貨幣が特定の使用価値や有用性を持たない「セロ・シンボル」だったからだ。一方の極限に「ゼロ・シンボル」(純粋な記号表現)としての貨幣があり、他方の極限には、人間の生存を維持するために必要不可欠な食糧などがある。貨幣を頂点とする極限へと接近するにつれ「過剰性の原理」が支配し、生活の基本物質へと接近するにつれ「有用性の原理」が支配する。では「稀少性の原理」とは何か。「稀少性」とは「見せかけ」であるので、「稀少性の原理」とは何か、という問題は見せかけの問題である。
②社会的な地位や威信をめぐる競争であるポトラッチの原理は、現代の文明でも支配している。高い社会的地位や名誉を得ることは「類いまれなるもの」であり、この「類いまれなるもの」を求めて、欲望は相互に模倣しあう。他人のほしがっているモノを人はほしがる。
③「欲望」は距離によって生み出される。他者がほしがっているモノをほしがるという相互模倣的な欲望は、それ自体がいっそうの「欲望」を生み出す。そもそも、欲望の対象は不特定で不確定な何かなので、だからこそ「他者の欲望」を模倣しようとするのである。欲望の模倣は社会的な名誉や地位や虚栄をめぐる競合的な模倣的競争をもたらす。それは、ゴールのない無限の競争を自動的に生み出すものである。
④生活の必要や個人の事情によってどうしても必要とされる「欲求」と、社会的な次元を持ち、相互模倣によって生み出される「欲望」は、区別することができる。それは、「有用性の原理」と「過剰性」の原理に対応している。
⑤相互模倣の社会的材を求める欲望が強まるほど、財貨は稀少となる。過剰性の原理のなかで稀少性が生まれるのだ。稀少な財貨を得るには貨幣が必要となり、貨幣は欲望の対象との距離を測るものとなるが、同時に距離を生み出す。いいかえれば、「貨幣」こそが「欲望」を作り出す。より多くの貨幣が必要な対象ほど「距離」が大きくなり、同時に「欲望」も強度になる。
⑥人間の象徴作用のなかから「過剰性」が生み出される。すなわち「ポトラッチの原理」であり、それが「模倣的競争」を生む。「模倣的競争」はいっそうの「貨幣」を必要とし、貨幣によって距離ができると稀少性が生まれる。貴重なものがますます「稀少」となり、「欲望」が膨らみ、より多くの「貨幣」が必要となる。このため、人は経済成長へと強制される。「過剰性の原理」と「稀少性の原理」は対立するものではない。「過剰性の原理」が「稀少性の原理」をもたらすのである。
『過剰性と稀少性』の要約&本文解説
1. 貨幣はなぜ特別なのか?
まず筆者は、「貨幣」はふつうのモノとは違うと述べています。たとえば、食べ物や衣服は、私たちの生活に直接必要な「有用性(役に立つこと)」を持っています。一方で貨幣は、それ自体では何の役にも立たない「ゼロ・シンボル」(=ただの記号)です。
それでも貨幣は「一番価値がある」とされます。なぜなら、どんなモノとも交換できるし、社会的に非常に重要だからです。
このように、実際には役に立たないのに特別扱いされるモノの世界に、筆者は「過剰性の原理」が働いていると考えています。
2. 欲望は「人まね」から生まれる
私たちは、本当に必要なもの(食料や衣服など)だけを求めて生きているわけではありません。たとえば、「友達が持っているブランドバッグがほしい」と思ったことはありませんか?
このような「他人のほしがっているモノを自分もほしくなる」現象を、筆者は「相互模倣的な欲望」と呼びます。
人は他人の欲望をマネして、自分の欲望を形づくっているというのです。そしてその欲望がエスカレートすると、「よりすごいモノ」「より目立つモノ」を求めるようになり、無限の競争が始まります。
3. 「過剰性」と「稀少性」はつながっている
筆者は、「過剰性」と「稀少性」は対立するものではなく、むしろ連動していると述べています。
●「過剰性」とは?
- 本来必要以上のモノや価値を求めること。たとえば、生きるのに必要ないほど高価な時計や車を求めること。
●「 稀少性」とは?
- 手に入りにくい、数が少ないという「見かけ」。実際に少ないかどうかではなく、「貴重そうに見えること」が重要。
そしてこの「稀少性」は、過剰な欲望(=過剰性)によって生まれるのです。たとえば、みんながほしがる限定商品が「稀少」に見えるのは、「欲望」が集中するからです。
4. 貨幣が欲望をつくる
では、なぜ人は「過剰性」に引き込まれていくのでしょうか? ここで再び貨幣が登場します。貨幣は、ほしいモノとの「距離」を測る道具であり、「距離を生み出す」ものでもあると筆者はいいます。
どういうことかというと、より高価なモノほど手が届きにくいため、そのぶん人は「欲望」がかき立てられるのです。結果として、人はより多くの貨幣を得ようとし、より強く競争し、社会全体が「経済成長」へと駆り立てられていくのです。
5. 筆者の主張は何か?
筆者の主張を簡潔にまとめると、以下のようになります。
人間の欲望は「他人のマネ」から生まれ、それが「過剰なモノ」を求める力となる。そしてその欲望が「稀少性」という錯覚をつくり、貨幣による無限の競争社会を生み出している。
つまり、「過剰性の原理」が「稀少性の原理」を生み、両者は互いに作用し合いながら、社会の競争・経済活動・消費行動を動かしているということです。
この文章は、「なぜ人間は必要以上のものを求めるのか」「なぜモノは稀少に見えるのか」という問いに対して、貨幣や欲望、模倣という観点から答えようとしています。
形式は難しくても、伝えたいことはとても現代的です。SNSでの承認欲求、ブランド品への執着、経済成長への焦燥、それらはすべて「過剰性」と「稀少性」のサイクルに私たちが巻き込まれていることの表れなのかもしれません。
『過剰性と稀少性』の意味調べノート
【服す(ふくす)】⇒従う。従属する。
【極限(きょくげん)】⇒これ以上ないぎりぎりの状態。
【稀少(きしょう)】⇒めったにないこと。珍しいこと。
【承認(しょうにん)】⇒正しいと認めて許すこと。
【優越(ゆうえつ)】⇒他よりもすぐれていること。
【威信(いしん)】⇒他人が自然と従うような力や名声。
【競覇(きょうは)】⇒覇権を競うこと。互いに勝ちを争い、支配を目指すこと。
【模倣(もほう)】⇒まねをすること。
【競合(きょうごう)】⇒同じ分野で競い合うこと。
【合理的(ごうりてき)】⇒むだがなく、理にかなっているさま。
【代補(だいほ)】⇒代わりに補うこと。
【虚栄(きょえい)】⇒見かけだけの栄誉。
【有閑階級(ゆうかんかいきゅう)】⇒財産があり、働かずにゆとりある生活をする社会階級。
【奢侈品(しゃしひん)】⇒ぜいたく品。生活必需品でない高価な品。
【階層(かいそう)】⇒社会などでの地位や立場による区分。
【動因(どういん)】⇒ある出来事を起こす原因やきっかけ。
『過剰性と稀少性』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①親からカジョウな期待を受ける。
②彼はユウエツ感にひたっている。
③ケンイある教授の講義を受ける。
④ショウダクを得て契約を結ぶ。
⑤イシンをかけた試合が始まった。
次のうち、本文の内容を最も正確に表しているものはどれか?
(ア)人間の欲望は本来個人の内面から生まれる自然なものであり、貨幣や社会構造はその欲望を抑制する手段にすぎない。
(イ)貨幣は実際に使える有用性を持つことが本質であり、生活必需品に近づくほど過剰性の原理が働くようになる。
(ウ)人間の欲望は他者の欲望を模倣することから生まれ、貨幣がその媒介となって過剰性と稀少性の循環を生み出す構造を形成している。
(エ)稀少性の原理は過剰性の原理と対立しており、現代社会はこの対立を乗り越えるために消費を抑える方向に進んでいる。
まとめ
今回は、『過剰性と稀少性』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。