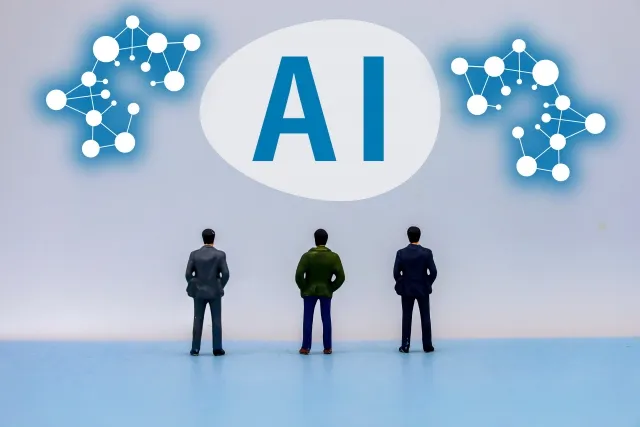
『AIの判断』は、船木亨による評論文です。教科書・現代の国語にも収録されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『AIの判断』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『AIの判断』のあらすじ
人はAIの普及について、管理社会を生み出す、個人のプライバシーがなくなる、人間が機械に支配される、仕事が奪われるなど盛んに警鐘を鳴らしている。だが、もっと大きな問題は、これらの人々の不安を、AIは解消してくれそうにないということだ。AIは合理的な判断を下すが、人間は非合理な存在であり、愚行権を持っている。AIには、人類の未来や個人の将来を心配し、社会的諸条件と一人一人の意識を調停しようとする性質が原理的にない。そのことのほうが問題である。
AIは判断を創出しているのではなく、人々のあらゆる判断を、人が感覚できないものまでさまざまなデータを集め、ネット上のクラウドを介して、大量のデータを用いてシミュレートするだけである。正しい判断をするのではなく、正しいとされる判断をデータとしてインプットし、正しいとされる基準の確率を上げていくだけだ。正しさを判断するのは人間であり、「正しさ」は人間にとってのものでしかない。したがって、もしAIにあらゆる判断を任せてしまうと、そこに「未来」はない。
未来とは、現在よりもよい状態になっているはずの、これから先のある時点のことである。AIの説く未来は、現在の延長でしかない。それは、時間測定法における未来であって、我々の「未来」ではない。そこに夢や希望はなく、似たような要素が繰り返し姿を現す退屈な現在か、至る所、現在の廃墟としての破滅と悲惨が組み込まれた擬似過去が待ち受けるばかりである。
AIの判断はルールがあり、条件の変化しないものに対しては最強だが、あり得ないことに挑戦する、いつもと違ったことをやってみるという判断は、そこにはない。だが、そうした異例のことをなそうとする判断の向こうにこそ、人間の考える「未来」がある。
AIが普及した社会では、判断に意義を与えてきた「未来」を考える人間がいなくなる。だから、AIに心配するのは、AIが人類を未来の消失から救ってくれそうもないということなのだ。むしろ、それに荷担する装置ではないかと考える。
『AIの判断』の要約&本文解説
この文章では、AIの発展が人間社会に与える影響について深く考察されています。筆者は、AIが仕事を奪う、プライバシーを脅かすといった不安よりも、もっと根本的な問題に注目しています。それは、AIには「未来を夢見る力がない」ということです。
AIは、大量のデータを分析し、過去や現在の傾向をもとに「もっともらしい答え」を出すことは得意です。しかし、それはあくまでも“現在の延長線上”にすぎません。
AIは「合理的」な判断はできますが、「理想」や「希望」など、感情や価値観に根ざした判断はできないのです。たとえば、「ありえないことに挑戦してみよう」という発想は、AIにはありません。これは、ルール外の発想や人間の愚かさ(愚行権)を前提とした行動であり、未来を切り開くために重要な要素です。
また、AIが判断する「正しさ」は、あくまでも人間が作ったデータの平均値や多数派意見であり、絶対的なものではありません。つまり、AIにすべてを任せると、「本当の正しさ」や「新しい価値」は生まれにくくなるということです。
筆者の主張は、「AIが進化しても、人間が“未来を考える存在”であり続けなければ、真の意味での未来はなくなる」という点です。AIが進化する中で、人間が判断する力や夢を見る力を失わないようにすることこそが大切だと筆者は伝えているのです。
『AIの判断』の意味調べノート
【普及(ふきゅう)】⇒広く行き渡ること。広まること。
【警鐘を鳴らす(けいしょうをならす)】⇒危険や問題があることを強く知らせる。
【服用(ふくよう)】⇒薬などを飲むこと。
【資本主義(しほんしゅぎ)】⇒利益を目的として、個人や企業が自由に経済活動を行う仕組み。
【合理的(ごうりてき)】⇒無駄がなく、理にかなっているさま。
【愚行権(ぐこうけん)】⇒他人に迷惑をかけない範囲で、自分にとって不合理なことを選ぶ権利。
【成り行き(なりゆき)】⇒物事の自然な流れ。経過。
【放置(ほうち)】⇒そのままにして構わないこと。
【なし崩し(なしくずし)】⇒物事を少しずつくずしていき、結果的に全体をだめにすること。
【破滅(はめつ)】⇒完全にこわれたり、だめになったりすること。
【確執(かくしつ)】⇒人と人との間に生じる対立や争い。
【調停(ちょうてい)】⇒争いや対立を仲立ちして、おさめること。
【原理的(げんりてき)】⇒物事の基本となる考え方や法則に基づいているさま。
【シミュレート】⇒現実に近い状況を仮想的に再現し、予測や分析をすること。
【抽出(ちゅうしゅつ)】⇒多くの中から必要なものを取り出すこと。
【妥当(だとう)】⇒適切で、筋が通っていること。
【廃墟(はいきょ)】⇒壊れたまま放置されている建物や町などの跡。
【擬似(ぎじ)】⇒本物に似せているが、本物ではないこと。
【帰結(きけつ)】⇒最終的にある結果に行き着くこと。
【意義(いぎ)】⇒物事の意味や価値。
【加担(かたん)】⇒よくないことに関わって助けること。
『AIの判断』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①裁判のチョウテイが行われる。
②社会ホショウが充実している。
③新たな価値をソウシュツする。
④タイクツな時間を過ごす。
⑤ギジ体験でも効果がある。
次のうち、本文の内容を表したものとして最も適切なものを選びなさい。
(ア)AIは人間の感情を模倣できるため、未来に希望を与える存在になりうる。
(イ)AIの判断は膨大なデータから「正しさ」を導くことができるため、人間より信頼できる。
(ウ)AIにとって未来とは、現在の延長線上にあるものであり、希望や夢を含まない。
(エ)AIは予測だけでなく、価値判断や倫理の判断まで自律的に行う能力を持つ。
まとめ
今回は、『AIの判断』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







