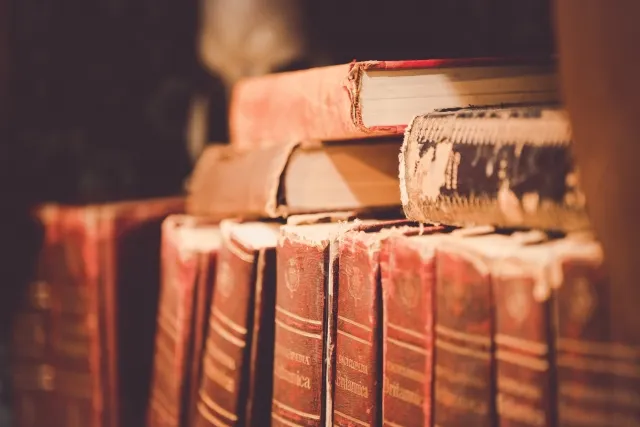
『物語と歴史のあいだ』は、教科書・論理国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『物語と歴史のあいだ』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『物語と歴史のあいだ』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを紹介していきます。
①歴史は過去の出来事を「解釈学的に再構成」すること、つまり「物語る」ことしかできない。すべての歴史的出来事を、ありのままに描写する能力を備えた歴史学者がいたとしても、それは「歴史叙述」とはならない。なぜなら、そこには出来事と出来事をつなぐ脈絡、つまり「物語」が欠落しているからだ。小林秀雄は、このような歴史学者のことを「一種の動物にとどまる」と喝破した。彼は、一滴の水が乾いた舌にしたたり落ちるその瞬間を捉えて、それを歴史と呼んだ。
②小林の思い入れに反して、「思い出」はそのままでは「歴史」に転成することはできない。思い出が歴史に転成を遂げるためには、「物語行為」による媒介が不可欠である。「物語る」という言語行為を通じた思い出の構造化と共同化こそが、歴史的事実の成立条件である。歴史的事実は、ありのままの「客観的事実」であるよりは、むしろ物語行為によって幾重にも媒介され、変容された「解釈学的事実」と呼ばれねばならない。
③文献史料は、ありのままの過去を再現する手段ではなく、すでに「解釈」の産物である。われわれが言語によって記述を行うとき、そこには関心の遠近法が働いており、記録に値する有意味な情報の取捨選択がなされている。その意味で、文献史料はすでに一つの「物語」を語っている。考古学的資料ですら、「解釈」の汚染を免れてはいない。歴史の「史料」もまた、過去の「客観的事実」そのものではなく、そこにはすでに「解釈」の鑿(のみ)が刻み込まれている。歴史叙述は「解釈の解釈」の行為とならざるをえない。その観点からすれば、歴史叙述は「記述」であるよりは、むしろ「制作」に似ている。
④歴史的出来事は、歴史叙述から独立に論じることはできない。歴史的出来事は、物語行為によって語り出されることによってはじめて、歴史的事実としての身分を確立することができる。「歴史」と「物語」は「事実」と「虚構」のように対立するものではなく、むしろ両者は表裏一体のものである。
『物語と歴史のあいだ』の要約&本文解説
歴史は「語る」ことで初めて成り立つ
まず、筆者が最も強調しているのは、「歴史とは物語ることによって成り立つものだ」という点です。つまり、過去に起きた出来事を単に事実として記録するだけでは、それはまだ「歴史」にはならない、ということです。
仮に、すべての出来事を完璧に記憶し、正確に描写できる人がいたとしても、その人が何の脈絡もなく情報を並べてしまえば、それはただの「情報の羅列」でしかありません。歴史と呼ぶには、出来事と出来事を結びつけ、「なぜ起きたのか」「何が変わったのか」という筋道を示す必要があります。
そうした筋道——つまり「物語性」こそが、歴史叙述に不可欠だというわけです。
思い出はそのままでは歴史にならない
人の記憶、いわゆる「思い出」も、単なる過去の経験にすぎません。その思い出を「歴史」にするためには、言葉によって構造化し、他人と共有可能なものにする必要があります。
筆者はこれを「物語行為」と呼んでいます。個人の思い出を、語るという行為によって他者と共有し、文脈のある形にすることで、初めてそれが歴史的な意味を持つのです。
つまり、歴史的事実とは、客観的な真実というよりも、「語ること」を通して構成される「解釈された事実」なのです。
史料もまた「解釈」の産物である
このような主張をすると、「でも、歴史には文献や史料がある。あれは過去の客観的な証拠では?」と思う人もいるかもしれません。
しかし筆者は、そうした史料もすでに「解釈されたもの」だと指摘します。たとえば、日記や記録文書には、書いた人の意図が反映されており、「何を書くか」「何を書かないか」が選び取られています。
このように、史料の段階ですでに“物語的な構成”が入っているのです。さらに歴史家がその史料を使って新たに歴史を書くとき、そこにまた別の解釈が加わることになります。言い換えれば、歴史叙述とは「解釈の解釈」にほかならないのです。
「歴史」と「物語」は切り離せない
こうした議論の結論として、筆者は「歴史」と「物語」は本質的に結びついていると述べています。私たちはしばしば、「歴史=事実」「物語=フィクション」と考えがちですが、歴史という営みは、その“物語性”を前提として成り立っています。
つまり、「事実を語ること」と「物語を語ること」は、まったく別のものではなく、むしろ表裏一体なのです。歴史は物語として語られることで初めて「意味ある過去」になるというわけです。
『物語と歴史のあいだ』の意味調べノート
【駆使(くし)】⇒自由自在に使いこなすこと。
【解釈学(かいしゃくがく)】⇒解釈の方法や理論を取り扱う学問。
【太古(たいこ)】⇒大昔。
【能う限り(あたうかぎり)】⇒できる限り。可能な限り。
【超人的(ちょうじんてき)】⇒人間離れしているさま。
【脈絡(みゃくらく)】⇒物事のつながりや筋道。
【膨大(ぼうだい)】⇒数や規模が非常に多いこと。
【喝破(かっぱ)】⇒本質を鋭く見抜き、はっきりと言い当てること。
【人口に膾炙する(じんこうにかいしゃする)】⇒世間に広く知られ、評判になる。
【心をむなしくして】⇒心を空っぽにして。
【細大漏らさず(さいだいもらさず)】⇒小さいことも大きいことも、すべて漏れなく。
【なぞらえる】⇒あるものを他のものに見立てる。
【氷結(ひょうけつ)】⇒水がこおって氷になること。
【濾過(ろか)】⇒液体や気体から不要なものをこし取ること。
【些末(さまつ)】⇒とても小さくて取るに足りないこと。
【おのずからなる】⇒自然とそうなる。ひとりでにそうなる。
【転成(てんせい)】⇒形や性質が変わって別のものになること。
【甘美(かんび)】⇒うっとりするほど快いこと。
【間欠的(かんけつてき)】⇒一定の間をおいて断続的に起こるさま。
【因果(いんが)】⇒原因と結果。
【起承転結(きしょうてんけつ)】⇒文章や物事を組み立てる順序。
【構造化(こうぞうか)】⇒全体を構成するものとなるさま。
【共同化(きょうどうか)】⇒二人以上の者が力を合わせるさま。
【幾重(いくえ)】⇒たくさん重なっていること。
【変容(へんよう)】⇒形や性質が変わること。
【雄弁(ゆうべん)】⇒説得力のある力強い話し方。
【排除(はいじょ)】⇒いらないものを取り除くこと。
【紋様(もんよう)】⇒模様やデザイン。
【不可分(ふかぶん)】⇒分けることができないこと。
【虚構(きょこう)】⇒作りごと。事実ではなく想像で作られたもの。
【表裏一体(ひょうりいったい)】⇒二つのものが切り離せない密接な関係にあること。
『物語と歴史のあいだ』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①技術をクシして問題を解決する。
②ワインをチョゾウする部屋がある。
③彼はユウベンに意見を述べた。
④歴史をジョジュツする本を読む。
⑤この言葉のカイシャクは難しい。
まとめ
今回は、『物語と歴史のあいだ』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







