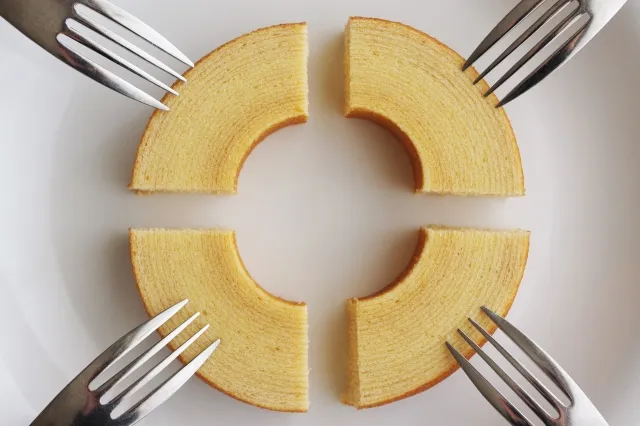
『分かち合う社会』は、教科書・論理国語で学習する文章です。そのため、定期テストの問題にも出題されています。
ただ、本文を読むと筆者の主張が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『分かち合う社会』のあらすじや要約、意味調べなどを解説しました。
『分かち合う社会』のあらすじ
本文は、四つの段落から構成されています。ここでは、各段落ごとのあらすじを簡単に紹介していきます。
①人類は、仲間と食事をともにするという食習慣を持っている。これは、人間以外の霊長類にとっては不思議なことである。さまざまな社会の中でも、とくに狩猟採集社会は、食物を徹底的に分配する社会である。
②食物の分配を、不安定な食物環境における一種の保障システムだとする考えもある。しかし、お返しの義務がないことや、一方的な譲渡が多いことなどを考えれば、互酬性や交換といった概念では説明しきれない。
③ピグミーやブッシュマンなどの狩猟採集民は、狩猟によって富が偏在しないような規範を社会のすみずみまで行き渡らせている。獲物をしとめたハンターは、控えめな態度をとるのが普通である。ピグミーの社会は、「分け与える」ことではなく、「分かち合い」の精神によって特徴づけられる。「分かち合い」の精神にもとづく社会では、所有することが徹底的に避けられる。食物の分配には、二者間の人格的な贈与関係を排除しようとする作法がある。それを竹内潔は、「われわれ」というコンテキストで食物が配分される「共在のイデオロギー」と呼んだ。
④「共在のイデオロギー」が、食物を介した二者間のコミュニケーションを否定しようとするのは、彼らが人々の関係に及ぼす食物の影響力をよく知っているからだ。いったん所有された食物は、分配を介して人々の関係に影響を及ぼす。人間は、食物を政治的な手段にすることを自らに禁じ、食物のルールを作ったのだ。狩猟採集民は、食物の分配が与える影響を極度に抑えた社会を作ったと言える。それは、私たちが仲間とともに食事をし、隣人に気前よく食べ物を与える原点といえる。
『分かち合う社会』の要約&本文解説
この文章のテーマは、「狩猟採集社会における食物の分配とその社会的意義」です。
現代社会では、個人が所有した食物を自由に使うのが一般的ですが、狩猟採集民の社会では「分かち合い」の精神が重視され、個人の所有が徹底的に避けられる特徴があります。
本文では、まず人類が仲間と食事をともにする習慣を持つことが、他の霊長類には見られない不思議な特徴であると指摘しています。特に狩猟採集社会では、食物は徹底的に分配され、互酬性や交換といった一般的な経済概念では説明しきれない仕組みがあります。
例えば、ピグミーやブッシュマンの社会では、狩猟で得た食物が特定の個人に富として蓄積されないような規範が行き渡っており、獲物を得た者も慎ましい態度をとることが求められます。
また、彼らの食物分配には「共在のイデオロギー」が働いています。これは、食物が人々の関係性を変えてしまう力を持っていることを理解したうえで、それを避けるために作られたルールです。
私たちが友人や家族と食事を共にし、隣人に食べ物を分ける文化の原点は、こうした狩猟採集民の社会にあると筆者は主張しています。
このように、本文では人間社会における食物の分配が単なる経済行為ではなく、社会のあり方を決定づける重要な要素であることを明らかにしているのです。
『分かち合う社会』の意味調べノート
【分配(ぶんぱい)】⇒分けて配ること。
【執拗(しつよう)】⇒しつこいさま。
【嬉々として(ききとして)】⇒喜びを感じながら、楽しそうに行動するさま。
【徹底的(てっていてき)】⇒最後までやり抜くこと。徹底して行うこと。
【傾向にある(けいこうにある)】⇒何かの方向や状態に向かう傾向が見られる。
【説がある(せつがある)】⇒ある問題についての意見が存在する。
【互酬的(ごしゅうてき)】⇒互いに与え合うさま。
【貯蔵(ちょぞう)】⇒物を保存しておくこと。特に、食物や資源の保存。
【保障(ほしょう)】⇒ある状態がそこなわれないように、保護して守ること。
【贈与(ぞうよ)】⇒他者に物や金銭を無償で渡すこと。
【負い目(おいめ)】⇒負担や罪悪感を感じること。
【負債(ふさい)】⇒借金などの支払い義務を持つこと。
【概念(がいねん)】⇒物事の大まかな考えや捉え方。
【移譲(いじょう)】⇒権利や責任などを他者に譲ること。
【偏在(へんざい)】⇒一部の場所や人に集中して存在すること。
【慣わし(ならわし)】⇒伝統的に行われている習慣。
【称賛(しょうさん)】⇒ほめること。高く評価すること。
【威信(いしん)】⇒人に示す威厳と、人から寄せられる信望。
【素っ気ない(そっけない)】⇒冷たく、無愛想な態度。
【排除(はいじょ)】⇒除外し、取り除くこと。
【コンテキスト】⇒文脈。物事の背景や前後の状況。
【営為(えいい)】⇒人間が日々いとなむ仕事や生活。いとなみ。
【イデオロギー】⇒政治や社会に対する考え方・思想。
【顕著(けんちょ)】⇒際立って目につくさま。はっきりとあらわれているさま。
【人為的(じんいてき)】⇒自然のままでなく、人の手が加わるさま。
【憎悪(ぞうお)】⇒ 激しい嫌悪や敵意を持つこと。
『分かち合う社会』のテスト対策問題
次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。
①ハンショクの速度が速い。
②サバクでは水が貴重だ。
③キハンを大切にする。
④国家のイシンに関わる問題。
⑤ケンチョな成果が出た。
「負債のイデオロギー」=贈与をすることで、受け取った側にある種の負い目を感じさせ、相応のものを送り返す行為を生み出すこと。
「共在のイデオロギー」=与える者と受け取る者という二者関係で完結するのではなく、食物を参与者みなで分かち合い、ともに生きていこうとすること。
次のうち、本文の内容を最も適切に表しているものを選びなさい。
(ア)狩猟採集社会では、獲物を仕留めた者が全てを所有し、必要に応じて分け与えることが一般的である。
(イ)狩猟採集社会では、食物の分配は個人の判断に委ねられ、分配のルールは特に存在しない。
(ウ)狩猟採集社会では、食物の分配が徹底され、個人の所有を避けるために様々な工夫がなされている。
(エ)狩猟採集社会では、他人の槍を借りることは効率の良い狩猟のためであり、食物の分配とは無関係である。
まとめ
今回は、『分かち合う社会』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。







